
「写真週報」S13.8.31号より
7年間この繰り返しだったわけだ…
空襲以前の空襲被害予測
「空襲のハナシなんぞ書きたくないけど書かんとイカン」と以前書いた。その後しばらく「兵器生活」本編の更新をしていなかったために、「できもしないダイエット予告だ」とさんざんな目にあっている。資料まるごとコピーでオリジナルが無いのは毎度の事であるが、それをテキスト化する手間ときたら、仕事か道楽じゃなかったら、とてもやってられないのである。
日本の空襲については、戦後様々な書籍が出ているのであるが、その手の本ばかり読む人が、そもそも「兵器生活」などと言うふざけたページを読みに来るわけも無い。つまり、書いている私も、読んでいるあなたも、空襲の実相についての知識は、たいして変わらない、と言う前提で以下の文章は続くのである。
さて、本土空襲というと、昭和20年に入ってからの壊滅的大空襲、という刷り込みが出来てしまっているわけだが、日本領土への空襲は、中国空軍によって、すでに昭和13年に行われている(支那事変の勃発は昭和12年7月であり、帝国海軍による南京への渡洋爆撃が同年8月15日から開始されている)。戦争当事国が互いの国土を爆撃しあう、と云う当時の『未来戦争』の姿を実現させたのは、実は日本と中国なのであった。
しかし、日中双方が爆撃の応酬を行った、と云ってみても、日本側のそれは<戦略爆撃の先駆け>として評価されているが、中国側のそれは、宮崎駿のマンガで取り上げるまでは(取り上げた今でも)<知る人ぞ知る>レベルのものである。まあ実際のところ、中国空軍の行った空襲は3回(「防空」S17による)で、爆撃されたのは台湾2回、九州1回であり、マンガになった九州のそれで投下されたのは、紙の爆弾(宣伝ビラ)なのであった。
そう云う時代の状況から見れば、現代の我々の持つ空襲観と、当時のそれとがはまったくの別物であってかまわないわけで、帝国日本が、何故空襲に対して無力さを露わにしてしまったのかを理解するには、そのあたりの事情を知っておくのもよかろう、と今回の長い出だしは終わる。
空襲=焼夷弾、という図式から未だに逃れられない筆者には、未だに理解出来ないのだが、戦前の防空を説いた書籍で取り上げられるのは、焼夷弾よりも毒瓦斯弾の方が分量として多い。
手元にある「われ等の空軍」(S12.6)では<都市防衛戦>という項で、都市防衛について述べているのであるが、その内容の大部分は灯火管制と防毒である。毎度の「写真週報」29号(S13.8)では<防空おぼえ帖>という特集記事を掲載しているが、そこでも灯火管制と防毒が大きく取り上げられている。
記事が掲載されてから、すでに60年以上経過してしまっているので、その背景は推測するしか無いのだが、第一次大戦での毒瓦斯戦の記憶が、書き手、読み手双方に残っていた事が大きいようである。現代の我々が、<戦争=核戦争>を即座に連想するようなものである。
だからといって、当時の人が焼夷弾攻撃をまったく想定していない、というわけではない。「われ等の空軍」でも
殊に日本の都市は、紙と木の寄木細工のようなものだ。焼夷弾でも落とされたときは、四方八方に飛火していよいよ危険である。
若い諸君は知らないだろうが、大正12年の9月1日のあの大震災のときの東京市民の慌てぶりを思い浮かべてみれば、くどくど言わなくてもよく分かることだ。
と書かれているし、「写真週報」にも、ちゃんとモンペ姿の女性陣による、焼夷弾防火実演の記事が掲載されている。少なくとも、日本の都市が防火上(焼夷弾空襲は、空からの放火以外の何物でもない)問題がある事は、充分知られていたのである。そうでもなければ、市民参加の焼夷弾消火実演なんて事を、警視庁、東京市主催、内務省後援でやるわけが無い。

「写真週報」S13.8.31号より
7年間この繰り返しだったわけだ…
いざ戦争! となった時に、国家国民がそれに耐えられるか、などという事は、自由主義の現代日本でも断言出来ないし、ましてや当時の帝国日本であれば、少なくとも公的には「耐えられる」と言うしか無い。エライ人の発言は、多少割り引いて(あるいはその逆)評価した方が良いのは昔も今も変わらない。
さて、いよいよ支那事変が大東亜戦争に発展しそうな昭和16年、「画報躍進之日本」10月号に「空襲の実相を知れ!」(東部軍司令部防空参謀中佐 難波 三十四)いう記事が掲載された。分量が多いため、その一部を抜粋して紹介する。
敵は日本を3時間で全滅するという 笑止千万!我に鉄の護りあり!
(略)
(一)(註:本当は二となるのだが、原文ママ)空襲機数および空襲回数:では、敵機は何機で何回空襲するか! というと、、人心に衝撃を与え、かつ潰滅威力を発揮するためには、なるべく多くの飛行機を集結しての空襲が有効だが、また人心に絶えざる不安を与え、神経を悩まし能率を低下させるためには、少数で頻繁に空襲するのが敵にとって有利であるから、空襲の目的によって、何機で何回来るかがちがう。
また空襲する飛行機の性能や、操縦者の技量などいろいろの原因で異なるので、一がいに何機で何回とは断定できないが、一応大都市の夜間では1回10数機、昼間では1回2、30機ぐらいで全戦争間(或は戦争の一段階間で、一年半か二年)に数回か、多くても10回くらい空襲はあるものと考え、中小都市は1回数機で数回くらい空襲をうけると思えばよい。
(三)投下弾の種類、数量、効力:まず焼夷弾が多く一部爆弾も併用されよう。問題は毒ガス弾であるが、これは全然使用しないとはいえないが、ごく稀であってたとい攻撃されても、大した心配はいらない。
焼夷弾の種類を大きさで区分すると、5キロ、10キロ、20キロ、50キロ級のものがあるが、多く使われるのは5キロ級、10キロ級のものだろう。またこれを性能によって区分すると油脂焼夷弾、エレクトロン焼夷弾、黄燐焼夷弾などがある。爆弾には1トンとか5百キロとか大きいものがあるが、現在は50キロ、百キロ程度のものを使い、稀に250キロ級が使われる。投下弾の数量は一機の搭載量、同時に空襲する機数、投下弾の種類が決まれば簡単に算出できる。
例えば1機の搭載量が1トンで、5キロの焼夷弾のみ積んでくれば1機2百発、50キロの爆弾のみ積んでくれば1機20発で、これが同時に10機来襲したとすると焼夷弾の場合は2千発、爆弾の場合は2百発となる。なお焼夷弾、爆弾、ガス弾の効力は概ね前頁(略)の表の通りである。
空襲に恐怖は禁物
われわれは空襲に対する経験がない。それでいろいろと惨禍を想像し、恐怖動揺する。その恐怖は何かというと、爆弾はあたるものだと考え、そしてむやみに死んだり、怪我をするものだと思いこんで、勝手に恐ろしがる。では弾はそうやすやすと命中するか?
いま東京が20機の敵機で10回空襲されたと仮定する。
この敵機が5キロの焼夷弾のみを搭載してやってきたとすると、1回4千発、10回で4万発だ。また50キロの爆弾のみを積んでやってきたとすると1回4百発、10回で4千発を落とされる。その焼夷弾の全弾が一人に一発づつ命中したとすれば1回で4千人、10回で4万人が死ぬ。また爆撃の場合、一発で5人づつ死んだり、重傷をうけたりしたと考えれば1回に2千人、10回に2万人の死傷者ができる。これを東京市の人口7百万と比較対照すると焼夷弾のときは一回で1700人の中の一人が、10回では170人中の一人が死ぬ。爆弾の時は1回に3500人中の一人、10回では350人の中の一人が死傷する。
投下弾の全部が全部命中したものとしての計算がこれだから心構えと準備がありさえすればけっして恐ろしくない。普通百発に一発、大まけにまけても五十発に一発が建物なり人なりに命中すれば空襲は上出来とされている。したがって実際の死傷者は1回20機の空襲(焼夷弾4千発または爆弾4百発)をうけても直撃弾そのものでは40人乃至80人、或は20人乃至40人の死傷ができる程度で、まことに微々たるものである。また戦争している以上、これくらいの犠牲は当然忍ぶべきだ。鉄道事故でもこの程度の死傷はザラにある。
戦争といえばむやみに人が殺されると考えるのはまちがいで、砲煙弾雨の下で満四年以上闘っている支那事変の尊い人柱は11万、日露戦争では10万人である。またロンドンはじめイギリスの都市は連日連夜、ドイツの猛爆をうけているが、その損害はまた5千人だ。しかもドイツの猛爆は地理的条件がいいので日本を目標にするほど生やさしくはない。この4月一ヶ月の例をみただけでも、6千機が26日間猛爆し、爆弾6500トンを落としている。ではあの関東大震災の犠牲はどうか! タッタ2、3日のうちに十数万の生霊と百億の富を失ったではないか。
要は国民の心構えと準備さえあれば災害を最小限度に防げるのだ。空襲の威力を過大視せず、怖れず慌てず、一にも消火、二にも消火、手不足の官設消防に頼らずに”隣組は隣組で…”消火につとめることだ。
帝国が、対米英戦争の方針を決定した時期に出た、防空に関する記事の一つである。これとほぼ同じ文章は、「現時局下の防空−「時局防空必携」の解説」(難波 三十四)にも掲載されている。
この記事の持つ胡散臭さについては、山中 恒・山中 典子、「間違いだらけの少年H」P622〜、山中 恒「ボクラ少国民と戦争応援歌」P144〜に詳しいので、深入りはしない。むしろ山中氏の文章のトーンが、この二冊の本で、かなり異なっていることの方が、オモシロかったりするのである。と云うわけで、少し横道にそれる。
1985年に出た「ボクラ少国民と戦争応援歌」では、
(略)これは専門家にしては甚だ荒っぽい意見である。(略)
それよりも、もっと腹立たしいのは、数字のパズルをやって、この程度の犠牲は当然忍ぶべきだと、けろりといってのけてる点である。
と、あきらかに難波中佐に怒りをぶつけているのだが、1999年の「間違いだらけの少年H」では、
(略)難波中佐の論理は火災の恐怖を刺激しないように配慮してある。根拠の無い数字にすがりつき、(略) 誰かは死ぬに違いないが、それは私ではない、私は大丈夫と思わせるのである。
おそらく難波中佐も国民も、あちこちに焼夷弾が落ちて火災が発生するだろうし、そうなったら手に負えないだろうと予測していたはずである。(略)たしかに難波三十四はよくしゃべっているが、軍の防空や空襲専門のスポークスマンとして当然の任務を忠実に果たしただけなのである。
と、こちらでは同じ難波中佐を擁護に走っている。私は1999年の山中氏の姿勢を支持する。「少年H」に対する文句の書き方さえ感情的でなければ、本当に役に立つ本なのだ(笑)…。
官僚的文章における、数字のトリックについて書くはずだったのだが、山中 恒氏がすでに答えを出してしまったので、この文章については何も書けない。しかし、非常にわかりにくいように書かれているが、難波中佐が焼夷弾空襲の危険性を無視しているわけではない事は、認識していただけるものと思う。問われるのは、それを読んだ国民(実際は国民指導者、というべきであろう)が、そこまで深読みをしてくれていたか、なのである。
今回の本題は、実はこれから始まるのである(笑)…。
今の文章は、大東亜戦争が始まる前のものである。実際に戦争が始まった後(いうまでもないが、中国とはすでに実質的には戦争状態であり、その戦争は帝国の敗戦まで継続している)の昭和17年8月、難波中佐は「防空」(ダイヤモンド社)と云う本で、以下の文章を書いている。
消防ポンプは多々益々弁ずる。然し単なる多々主義は消防力の整備を促進する迫力に乏しく、且つ又現在消防力の実際能力を至当に判断し、克服し得ざる被害対策を確立する所以でない。
従って現在の消防力の根拠ある基礎に基いて検討して、其の能力を判定し、延いては将来整備すべき具体的数量を算出し、之に向かって整備に邁進することが必要である。
此の意味に於て、消防能力検討の一例を記述することにする。
今都市の消防隊が、自動車ポンプ360台を現有し、之を消防戦術上120台の3群に分ち、各群は第一線と予備隊とに分かって配備したものとする。3群に分かち且つ予備を持ったのは、敵の空襲は状況により、或いは都市内の一局地を集中爆撃し、或いは全市を分散爆撃し、或いは第一次に引き続き、第二次、第三次と続行せられる場合のあることを考慮したからである。
従来の実験により、間口15米、奥行15米の3階以下の建築物が火災を発した場合、自動車ポンプが15分以内に着手した場合に於いて、之が消火に要するポンプは、火勢小なるときは1台、中なるときは2台、大なるときは3台が必要とすれば、此の際の消防隊の能力は平均各群60箇所、全部で180箇所の家屋消防能力を持っていることになる。
又1ヘクタールの地域が火災となった場合には、其の地域の家屋の粗密度、其の他に依って異なるが之が消火に要するポンプは50戸なれば約12台、80戸なれば約20台が必要すれば各群は概ね10箇所内外、全部では30箇所内外の小地域火災の消防能力を有することとなる。
5ヘクタールの地域が火災となった場合に、其の外周より之を消火する為には、ポンプ60台を必要とすれば、各群約2箇所、全部では6箇所内外の中地域火災の消防能力を持って居ることとなる。次に之を空襲の一想定の下に研究検討してみよう。
我が軍防空部隊の撃墜を免れて、1瓲搭載の敵爆撃機が5機都市上空に進入したと想定する。この敵機が、5瓩の焼夷弾1千発を全市に分散投下した場合はどうなるか。投下弾の約3分の1の3百発は空地に落達し、火災発生の憂なく、又昼間では約5分の2の4百発、夜間では約5分の1の2百発を、隣組防空群や警防団で消火したものと仮定する。然るときは昼間では約3分の1の3百発、夜間では約2分の1の5百発の消火は消防隊の担任となる。然るに其の消防能力は前述の研究により約180箇所であるから、昼間では120箇所、夜間では320箇所は消火することが出来ない。之が延焼拡大して小地域火災程度となる。この時再び消防隊が消火するとせば、其の能力は30箇所であるから、昼間では90箇所、夜間では290箇所は消火せられず、中地域火災に拡大する。
又5瓩焼夷弾1千発を局地(例えば正面2百米、奥行1千米)に集中投下した場合はどうなるかといえば、右の計算によると、昼間では240箇所、夜間では440箇所は焼失することを得ず、延焼拡大することとなる。
今度は25瓩の焼夷弾2百発を投下した場合はどうなるか。約4分の1の50発は空地に落達、約10分の1の20発は隣組防空群、警防団で消火したものとすると、約130箇所の消火が消防隊の担任となる。之を全市に分散投下した場合は、概ね消火し得る。局地に集中投下した場合には60箇所は消火し得るが、70箇所は消火することが出来ないで、延焼して小地域火災となる。更に其の内10箇所内外は之を消火し得るものと見倣しても、60箇所から延焼拡大することとなる。
この要領によって都市の特性と、消防隊の従来の実験値とを基礎として検討すれば、今後其の都市の整備すべきポンプの所要数量も具体的に算出せられ、又現在消防隊に期待し得る戦闘力も探求し得られ、破壊消防の必要性とか、消防戦術の要領が、確立せられることとなるのである。
これも「根拠の無い数字」の一つとされてしまうわけなのだろうが、昭和17年4月18日の本土初空襲後に公刊された書籍の中で、もう官設消防力の限界について語ってしまっているのである。大規模な焼夷弾爆撃に対して、官設消防だけでは手に負えないことは、後の歴史が証明している。難波中佐の意図が、破壊消防、建物の強制取り壊しによる防火地帯の設置にあることは明白である。
では、実際に帝都の消火にあたる官設消防の体制はどうだったのか? 「東京の消防百年の歩み」(東京消防庁、S55.6)によれば、昭和15年10月のポンプ車定数は205台、16年は267台となっており、「防空」発行時に難波中佐がシミュレーションしている360台に達してはいないが、17年10月には570台、18年では783台まで定数上では増強されており、当局が防空体制強化に勉めていたことは評価しても良いだろう。さらに昭和19年には18の県よりポンプ車と手引きガソリンポンプの供出を受けてさえいる(ポンプ車317台、手引きポンプ925台。ただし、このすべてが東京に配置されたわけではなく、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡にも供給されている。実際東京に何台供給されたのかは不明)。
先のシミュレーションの数式を利用して、当時の消防力がどれくらいのものなのかを立証してみる。
ちなみに昭和16年11月時点における東京市の消防体制は、以下の通りである。
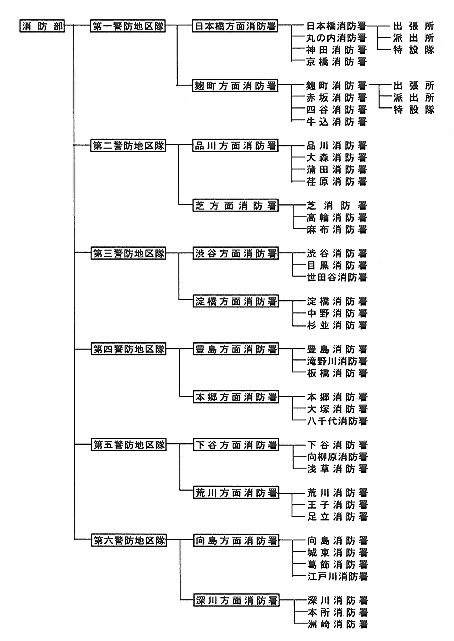
昭和17年10月29日時点での定数570台を基準にする。まず、17年11月に発足した特別消防隊(皇居および中央官庁防護専門部隊、ポンプ車50台を擁する)分のポンプ車50台を除いた520台を、上の図の第一〜第六の警防地区に等分に配備したものと仮定すると、1警防地区あたり、87台を使用出来る。
難波中佐云うところの、火勢「中」時におけるポンプ所要数は平均2台であるから、1警防地区は、理屈の上では同時に43箇所の火災に対応出来ることになる。先の空襲予想(5機×1トン=焼夷弾1000発投下)では300発=300箇所が消防の対応となるから、43×6=258+特別消防隊の25箇所で283箇所を鎮圧出来る。残った17箇所はそのまま延焼して、当然火勢は大きくなるわけだが、1ヘクタール火災の鎮圧に12〜20台必要との数式にのっとれば、(7から12箇所)×6地区=(42〜72箇所)の対応が可能であるから、理屈上ではここまでで完全鎮圧である。
つまり、昭和17年11月時点においては、この空襲規模(1トン搭載爆撃機5機)の前提が確立されていれば、帝都を焼野原にするような事態は回避されていたのである。
では、来襲敵機が10機、2000発の焼夷弾を投下したらどうなるのか?
隣組、警防団が額面通りの消火にあたる、と云う前提をそのまま生かせば、先の場合の二倍、600発=600箇所の火災に対して消防隊が消火にあたる事になる。
600−283=317箇所が引き続き延焼。1ヘクタール火災に対しては最大で72箇所への対応が可能であるから、さらなる延焼地域は245箇所(!)となる。5ヘクタール火災に対しては一箇所あたり60台が必要となるため、ここまで火災規模が大きくなると、10箇所対応するのがやっととなる。
となると、残り235箇所はどうなるのか? 火勢が収まるのを待ちながら、反復しつつ、引き続き消火活動にあたるしかないのである…。つまり、敵爆撃機10機が帝都上空を飛行する事態になると、官設消防力をもってしては、帝都を護りきる事は出来なくなってしまう、と云う困った状況が現れてしまうのである。この「防空」以外の防空読本に、官設消防に関する記述が無い理由と、ことさらに隣組での消火活動を重要視している理由がようやく解った。
今度は実際の空襲規模をもとにして、難波中佐の数式を検証してみよう。
<東京大空襲>として有名な昭和20年3月10日の空襲を例にとる。「東京の消防百年の歩み」に記載された資料(元ネタは『警視庁消防部空襲被害状況』)によれば、ポンプ車の出場はのべ844台、手引きポンプは538台であった。攻める米軍は「日本防空史」記載の表によれば、爆撃を行った機数で298機、投下された焼夷弾は4.5キロ油脂焼夷弾8,545発、2.7キロ油脂焼夷弾180,305発、1.8キロエレクトロン焼夷弾740発とされている(其の他100キロ爆弾16発、ただし機数は米軍数値、爆弾数については日本側での数値)。
(註:同書の別な記述では、4.5キロ油脂焼夷弾408,000発、2.7キロエレクトロン焼夷弾133,200発、1.8キロテルミット焼夷弾70,000発、其の他とあるのだが、とりあえず最初にあげた数値に基づいて検証してみる)
さて、投下されたとされる焼夷弾の総数189,590発のうち、官設消防割り当て分の1/3を抽出すると、63,197発となってしまい、これを一度の出場で鎮圧するためには、31,598台のポンプが必要との結果となってしまうのである。ちなみにポンプ車1台あたりの乗員は7名(これを1分隊とする)とされているので、これだけの台数を稼働させるには、221,188人が必要となってしまう。昭和19年4月時点の東京都消防部職員定数は12,108人であった。
参考ついでで紹介すると、内務省の消防力の基準は人口1万人に対してポンプ車1台とされていた。昭和15年国勢調査の東京の人口は約730万人で、つまり平時であれば、ポンプ車は730台あれば充分なのであった。先に出した221,188人は、東京の人口33人に1人が、プロの消防士と云う勘定になる。どう考えても現実的ではない。
つまり、帝都防衛のためには、敵機を帝都上空に入れないか、市民の消火能力をプロ並みに向上させる事が絶対必要で、それが不可能であれば、もう建物をあらかじめ取り除き、防火地帯を方々に設置するしか無いのである。
消防能力の話が長くなってしまったが、ここまでの検証を頭に入れて、最初の難波中佐の記事に戻ってみる。
一応大都市の夜間では1回10数機、昼間では1回2、30機ぐらい
と云うのが、日米開戦前の読みである。最初から消防能力の限界を越える敵機がやってくるのである。その半数は軍防空(防空戦闘機、高射砲)が撃退してくれるとしても、この数字の意味は大きい。この数字には根拠があるのだろうか?
「防空」に記載してある、日本軍による、南京爆撃の記録では、最大規模で約50機。実際の規模に関しては機密事項であるから、正確な数字は別な資料を見ないといけないのだが、50数回の攻撃に、のべ1200機余とされている。つまり平均で24機強、どうやら日本軍による空襲と、同規模での空襲を予想していたものと考えてよさそうである。
あえて今まで言及しなかったが、焼夷弾が1000発落ちたからと云って、本当に1000箇所で火災が発生するかどうかは、落ちた場所、投下のやり方、気象、其の他の条件によって異なることは云うまでもない。所詮は数字遊びであると云われても仕方の無い話である。しかし、こうやって愚直に数字と格闘することで、あらためて米軍による空襲の凄さを知っていただけたものと思うのである。
今後、日本が焼夷弾空襲に見舞われる可能性は低い。しかし大規模地震による火災の発生が、あたかもかつての空襲の脅威のごとく語られて久しい。備えるも、開き直るも、読者諸氏の心次第である。