人権意識が今日とはまったく違う―天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス(刑法第七十三條)―時代のものであるから、読む方によっては不快の念を抱き、主筆の人間性を疑う向きもあるだろう。「兵器生活」は、そう云う機微が(ある程度)解る方向けに書いているので、そこについては御容赦願う次第だ。
第20号である。

ズロース盗人の/エロ狂武雄
古知野でポーとなる
丹波郡古知野町大字髙屋 矢野庄五郎二男武雄(一九)は 去る二日午前十一時同町酒場メガミ女給とセン端的エロ気分にポーとしていたところを 巡邏の古知野署員に発見せられ風紀上面白からずと調べあげたところ 前記武雄は八月中旬より髙屋製糸工場の女工寄宿舎に忍び入り 女工のアレにいたづらをなし悦に入り 更に物ほし場にあったズロースを失敬しては自宅の机の引出しに入れ 書籍と同様に取出しては嬉しがっていた変態性欲のものと判明、係員ダァ……(六、九、六、尾州新聞)
酒場で女給とエロ遊戯に及んでいたのを咎められたのか、町中で酒場の女給とよろしくヤッていたのを捕まったのか判然としない文章だ。そこからドー締め上げると、女子寮侵入・下着ドロボーの事実が発覚するのか、官憲の取り調べが怖ろしくなる。

女と女が/二十年/同棲していた/嘘のような話
香川県大川郡白島町田中政一(四四)は 内縁の妻大阪北河内郡楠葉村小道ふさ(五五)と小豆島巡りの途中十二日午前六時頃 同島四十二番西の瀧山上で妻に塩酸を飲ませ自分も之を嚥下して心中を企てたが 女は一命を取止め政一は死亡した 検視の結果政一は男装していたが珍しい中性で 二人は二十年前から大阪の合同紡績にて共稼をしていた所 本年三月解雇され男の郷里へ帰っていたものであるが 最近生活難に苦しんでいたもので ふさは稍低能で夫が男装した女であったことと 二十年間同棲しながら少しも気付かなかった 嘘のような事実が判明した(六、五、一七、伊勢日日)
生活苦による心中事件が、グロ趣味満点な記事に化ける。「少しも気付かなかった」は、さすがに無いだろう。そのあたりの事情を説明しようがなく、低能のふりをしたんぢゃあないのか。取調官が面倒がってそのように供述させたようにも思える。
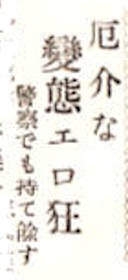
厄介な/変態エロ狂/警察でも持て余す
中津警察署は夏季一斉取締を施行中だが この警戒網にかかった捕物はルンペンとエロ犯罪等で 就中中津町本町玉井正夫(四一)と称するは 変態エロ狂で 各所で長襦袢、腰巻等を窃取しこれを眺めたり異臭をかいで或る種の満足をなし 果てはかみさいて喜び 又は白昼でも夫人の裸体等を見ると飛びついて強姦に等しい振舞(ふるまい)を行うので 此程署では検事局へ事件を送致せるに半無能者として不起訴となったが 最近又狂的に犯し廻るので中津署も手古ずって監置保護を加えているが 両親が変わり者で人の迷惑を顧みず 警察署や被害者を恨みわが子を溺愛しているので世人は困っている(六、七、二二、岐阜日日)
「こまった人」の話だ。「強姦に等しい振舞」と「強姦」の差は、犯罪行為として立件出来るか否かにあるのですね。両親に八つ当たりしてもドーにもならぬ。「赤い人」は治安維持法で取り締まれても、「アブナイ人」を拘束することは出来ぬのだと思うと、興味深いものがあります。
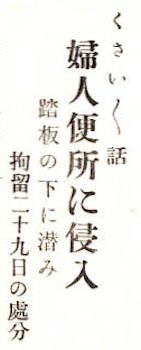
くさいくさい話
婦人便所に侵入/踏板の下に潜み/拘留二十九日の処分
去る一日夜 高山喜多座劇場婦人便所の汲取口より忍び入り 踏板の下に座りこんで臭いのもかまわず女の○○を眺めて 自慰にふけり悦に入っていた高山郊外片野周右衛門長男蜘手春一(二二)は 同便所横を通行中の高山町八幡町三川孝吉に発見され逃走し 付近の江名子川水中でぬれ鼠になって格闘、急をきいてかけつけた巡査に遂に逮捕されたが 同人は本年六月二十五日吉城郡古川町自動車業山下方に助手としてやとわれ中 主金数十円を横領、解雇されて浮浪していたもので、今まで数回同便所に入りこんだという変態性窺視病患者で 三日即決をもって拘留二十九日に処せられた(六、八、五、岐阜日日)
日本のトイレの大多数が、排泄物を「汲んで取る」構造だったことを知らなければならぬ(集めた屎尿は肥料として利用される)。つまり便所には出したモノを一定期間溜めておくところがあり、便器を覗けば暗がりに何かが蠢いているのを目にするコトもあり得る。よって「くさい」。衛生・美観それぞれの観点から、水洗便所に改めるべきだの声は挙がるものの、下水道の普及は進まなかったのが戦前から経済成長期頃の話である。
「汲取口より忍び入り」とはあるが、汲取便所の構造をすこし調べたこともある主筆としては、無理があると思っている。もっとも、劇場の便所は家庭のモノとは構造が違う可能性はある。
「踏板の下」とある。糞溜の瓶の廻りはモルタルで固めてあるから、うまくすれば糞を踏まずに済むかも知れない。便器の下から見上げた事は無いので、ホントに見えるのか? と思ってしまう(屎尿を浴びるのが目的だとなれば、それはそれで興味深い事例と云える)。
便所の横を通行中の人に見つかったとあるから、女子便所の中から出て来たトコロだったのだろう。そうなるとますます汲取口から忍び入ったのではなさそうだ。
便所覗きが見つかって川まで逃走、すぶ濡れになって逮捕、夏場でよかったなァと、なんか長閑に感じられてならぬ。
エロ三面記事から、「人間いろいろだなァ…」以上のモノを汲みあげようとするのは難しい、と云うより時間のムダな気がしてならぬ。
今なら「おっちょこちょい」「変わった人」くらいで済まされる人から、お近づきにはなりたくない方まで様々である。自分にはそんな趣味は無いから正常だ無関係だと思っていても、別なトコロからアブナイ人と見られている可能性は誰にでもある、と心に留めておくべきだろう。
(おまけのおまけ)
戦前エロ記事の背景には、エロで喰わねばならぬ当時の貧困と女性の地位の低さがある。
辛気臭い話は大嫌いなのだが、何も知らぬのもドーなのよ、と云うわけで、本屋で『芸者』(増田小夜、平凡社ライブラリー)を買ってくる。
小学校にも通えず、地主のもとに子守り仕事に出される。冬でも足袋はない。地面の冷たさから逃れるため、片足をいつも脚につけていたので「鶴」と綽名されていた少女が、置屋に売られ芸者となり土地の顔役に囲われる身となる。男のもとを出て辛酸を嘗めるものの、立ち直り、子守りの仕事を世話されるまでを綴った自伝だ。
15歳の半玉時代に「可憐な色気を感じさせる研究」をし、土地の顔役に身請けされた19歳には「男の関心をひきつけることには充分の自信を持っていました」と綴るひとが、戦時下で世間体が悪いからと働きに出た工場で、同僚女子たちが憧れていた男を、惚れさせて捨てるつもりで近づいたら、自分も惹かれて旦那をしくじってしまう。それが昭和19年頃と云うのに驚く。もうひとつの『この世界の片隅に』(こうの史代、双葉社)の世界と云える。
敗戦後の選挙で、持っていったスイトンを「人様の厚意は何でもいただく」と語った、候補者に投票するために文字を習い、やがて婦人雑誌に自身の考えを投書して、それが自伝執筆につながった由。
その解説に引かれていた、金子文子『何が私をこうさせたか』(岩波文庫)も読む。
朴烈「怪写真」事件の当事者(ひざに載ってる方)が、予審訊問中に綴った手記であり「遺書」。
こちらも小学校にすらまともに通えず(無戸籍だった)、朝鮮に渡った「祖母」に「跡取り」にと引き取られたものの、見限られて、使用人としてこき使われる。日本の縁者に引き渡されるため帰国。自立を志して上京、出会った「不逞鮮人」朴烈の存在そのものに「自分の仕事」を見出し、彼とともに生きて、ともに死ぬことを決意する。
朴烈と出会い同棲を申し出るくだりの文章は、それまでの辛酸までがすべてプラスに転じたような幸福感に満ちあふれ、ここで終わったらハッピーエントぢゃあないか! とさえ思う。手記はそこで完結するのだが、有罪となれば死刑になるしかない状態で、これを書いていたのかと思うと、やりきれない。
朴と暮らし始めてからの話は書かれていないので、金子の評伝小説、瀬戸内寂聴『余白の春』(岩波現代文庫)まで読んでしまう。
市井に埋もれて行った増田小夜(1926/大正15/昭和元年生―『すずさん』と同世代ですね)、「大逆事件」の当事者として自死を選んだ―死刑判決直後に恩赦で無期懲役に減刑―金子文子(1903/明治36年生)と来て、同じように底辺の暮らしをやりながら、そこから抜け出して邸宅まで建てた人に林芙美子がいたぢゃあないか、と『新版・放浪記』(中公文庫)にも手を伸ばす(再読になるのだが、中身なんか覚えていない)。
増田、金子両女史に比べると、女学校時代すでに文才を認められているだけあって文章は巧みだ。
林は、『放浪記』で売れっ子となり、稼ぎで外遊をやり、支那事変に際しては戦地の取材に飛び、敗戦後も活躍しつつも47歳で亡くなるのだが、実は1903/明治36年、金子文子と同じ年の生まれと知り驚愕している。
何が二人を別けたのか。
(おまけの余談)
『余白の春』のタイトルだけは知っていた。
沢木耕太郎『バーボン・ストリート』(新潮文庫)の一編に、若き日の沢木が、テレビで瀬戸内寂聴(当時は晴美)と山崎朋子の対談を司会した際、瀬戸内の作品名をど忘れして絶句した時、「余白の春、なのよね」と助け船を出してもらったエピソードが記されていて、『バーボン・ストリート』を高校の図書室で借りて読んだ1984年以来、タイトルだけは覚えていたのだ。
小説は読まないので(人生損している自覚くらいはある)、この先手に取ることも無いなんて思うことすらないまま、齢50を過ぎ、唐突に「必要に迫られて」、「本屋で探して」、「新本で買って」読んだことに感動すら覚える。
読み物としては、元ネタのひとつである『何が私をこうさせたか』での、「自分の仕事」に出会った喜びを語る高揚感に軍配を上げてしまうのだが、朴烈「大逆事件」(世間をアッと云わせるため、皇太子―のちの昭和天皇―に爆弾を投げつけようと思いつき、爆弾を入手しようとしたもの。実弾が飛んだ『虎ノ門事件』とはレベルが違う)の顛末は、こちらの方に詳しくあるので、両方読むに越した事はない。
(おまけの余白)
『バーボン・ストリート』、今回の「余談」のために買い直す。東中野のブックオフで310円。その前に買ったのは古本屋の100円均一棚だったので、釈然としない思いは正直ある。しかし、沢木が絶句したのはラジオと記憶違いをしていたのが、今回判明して恥をかかずに済む。