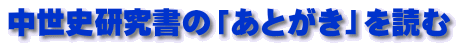
◎私はこれまで専門である日本中世史の先学が書かれた多くの研究書(論文集)を拝読してきました。もちろん
そのなかみを学ぶことが一番重要なのですが、それとともに個人的に思い入れがあるのが「あとがき」を拝読
することです。「あとがき」には、著者がその本を書かれた経緯、恩師への感謝、自らの研究生活の回顧、研究
内容への思い、などが吐露されており、これを拝読するとその先学の真実の姿をうかがい知れるのです。かく
いう私も拙著の「あとがき」は、こうした先学のものに影響を受けて、自分なりの思いを込めて書いたつもりです。
ここでは、それらの中で感銘を受けたものをご紹介したいと思います。
【1】佐藤進一『鎌倉幕府訴訟制度の研究』 初版:昭和18年(1943)畝傍書房 再版:平成5年(1993)岩波書店
・日本中世史の泰斗、佐藤進一先生(1916〜2017)の第1論文集です。現在、教科書や概説書などに記されている
鎌倉幕府・室町幕府に関する記述の基礎的な部分は、ほとんど先生の研究に基づくものといっても過言ではあ
りません。
・史料の徹底的な読み込みに基づく実証主義を貫きつつも、それが政治史のダイナミックな把握と見事に結びつき、
今なお他の追随をまったく許さない、まさに「中世史家の中の中世史家」ともお呼びすべき方なのです。十数年前、
私は佐藤博信先生、小国浩寿氏とともに先生のご自宅に伺い、親しくお話をお聞きする僥倖を得ました。この時の
思い出は、私の心の宝物となっています。
・さて、この本のあとがきの中で何より感銘を受けたのは、日付である「昭和十七年九月十九日」に続けて「醜の御楯
(しこのみたて)と出立つべき日を明日に迎へて」と記した部分です。「醜の御楯」とは、天皇を守る盾となる自らを卑下
した表現です。だいたい想像がつくと思いますが、これに関し、あとがきの最終段落に次のように記されています。
「今や祖国の振古未曾有の盛業大東亜戦争は、新段階に入らんとしつゝある。その時に当って、私はこの日本国に
生を享け、この聖代に会うた者の無上の栄光を担うて、勇躍入隊する事となった。この栄光の日を明日に迎へて、さ
さやかながらも、私にとっては感慨に満ちたこの研究の序文を認め得ることは、まことに一身の至福、喩ふべきもの
あるを知らない」
・再版時のあとがきによれば、この昭和17年9月に佐藤先生のところへ召集令状が届いたのでした。先生は「一瞬ギクリと
はしたけれども、至極当然のこととして受け入れることができた。この戦争に行かなければ、友人・知人に、そしてみ
んなに申しわけないと思っていたからである」と述懐しておられます。しかし、「出立たん日」とはせず、「出立つべき日」
としたのは、「ただ一人の人(つまり天皇)のためだけに死にたくはない、その思いだけはどうしてもいい遺しておきたい」
との思いからだったといいます。自らの思いをそのままに表現できなかった戦時下における、先生のせめてもの意地
だったのでしょう。
・佐藤先生はまことに幸いなことに復員され、戦後に仰ぎ見るような業績をあげられましたが、戦陣に散り学問を全うでき
なかった先学がどれほどいらしたことでしょうか。私はこの「醜の御楯と出立つべき日を明日に迎へて」の一文を拝読する
たびに、戦争のない自由な社会のもとで学問ができる有り難さを再確認し、同時にもっとまじめにやらねば、とも思うのです。
【2】小川 信『足利一門守護発展史の研究』 昭和55年(1980) 吉川弘文館
・室町幕府及び守護、さらには中世都市の研究で偉大な業績をあげられた小川信先生(1920-2004)。私が最も尊敬する
研究者のお一人です。まことに幸いなことに、10年余りにわたって親しくさせていただき、研究会でご指導いただいたり、
史跡見学のお供をさせていただくことができました。私が平成13年(2001)に学位を取得できたのも、先生から激励をいた
だいたことが大きなきっかけとなっています。
・その学風は國學院大學史学科の本流ともいうべき実証主義の極致であり、論文に付された註記の一つ一つが、詳細な
考証結果を記した、あたかも小研究の如きものでした。
・さて、この本のあとがき「自跋」の中で、先生は研究者となるまでの歩みを記されています。すなわちシベリア抑留の後に
復員し、高校教師となる一方で荘園史研究を志しました。しかし渡辺澄夫氏の名著『畿内荘園の基礎構造』(吉川弘文館、
1956年)に接し、もう一度勉強をやり直すことを決意され、昭和33年(1958)に30代後半で國學院大學の大学院に入学、室
町幕府の管領を出した細川、斯波、畠山三氏の実証研究に着手されました。
・この時の様子について、小川先生の指導教授のお一人藤井貞文氏は、本書へ寄せた「序」の中で、「復員の後は、大学院
に入って再び学生に返り、猛然と勉強を始めた。その迫力は余人を圧した」と書かれています。私はこの一節に大変な刺激
を受けました。あの膨大で緻密な研究を成し遂げられた小川先生の気迫がまことに見事に表現されていると思います。この
一節を拝読する度に、遙かに無能で怠惰な私は、なお一層努力しなければ、と身が引き締まるのです。
・なお先生は本研究により、昭和56年度の日本学士院賞を受賞されました。
【3】市村高男『戦国期東国の都市と権力』(思文閣史学叢書) 平成6年(1994) 思文閣出版
・市村先生と初めてお会いしたのは、私が研究らしきことを始めた1980年代後半のことでした。南北朝時代の小山氏をテーマ
としていた私にとって、東国守護や鎌倉府に関する優れた論文を次々と発表されていた先生の存在は、まことに大きなもの
がありました。
・なかでも『歴史評論』81号(1982年)に掲載された「鎌倉公方と東国守護」は、私にとって最高の道しるべとなりました。先生に
はお会いした際や、手紙を通じて様々なことを質問させていただき、拙論については厳しくも暖かいご指摘を頂戴しました。
・その市村先生が、数多い論文の中の一部をまとめられたのが本書です。あとがきによれば、先生は私の住む宇都宮市にあ
る宇都宮大学に学ばれました。この時、中世史の泰斗峰岸純夫先生が助教授として指導されていたのは、市村先生にとって
も大きなことだったでしょう。この時の同輩・後輩には、和久井紀明さん、清水昭二さん、荒川善夫さんなど、後に栃木の中世
史を担う方々がおられたのです。
・市村先生は一度大学院受験に失敗され、『結城市史』や『関城町史』などの編纂の仕事に携わりながら研究者としての道を築
いていかれました。私が本書のあとがきの中で最も印象深いのは、次の部分です。
私は常日頃、研究というのはゴールのないマラソンのようなものであると思っている。もとより仮のゴールというべき当面の目
標は確かに存在するが、最終的なゴールは、結局のところその研究者の死以外にはないと思う。その間、研究者が研究者
であろうとする限り、苦しくても絶えず走り続けなければならない。このことを思うにつけ、学部の頃、「マルクスは『学問の途
は堕地獄の途である』といった」と語った峰岸先生の言葉が脳裏に浮かび上がってくる。
私はこの部分を初めて読んだ時、研究という仕事の計り知れない厳しさを感じ、同時に何とか少しでも先生に近づけるような仕
事がしたいと強く思ったことを今でもよく覚えています。
・先生はその後、中央学院大学や高知大学等に奉職され、赴任先の地域の中世史解明にも尽力しておられます。
【4】石井進『日本中世国家史の研究』 昭和45年(1970) 岩波書店
・石井進先生(1931-2001)は、鎌倉時代を中心とした中世前期の幅広い分野で大きな業績を残し、東京大学教授や国立歴史民俗
博物館館長などをつとめられました。この本は、先生の数多い著作を代表する論文集です。私がもっているのは昭和59年(1984)
刊行の第4刷です。 論文集で4刷って…(唯々すごい)
・平成元年(1989)8月、私は市村高男先生からの要請で、小山市内のホテルで開かれた小山鷲城跡シンポジウム「小山義政の乱と
下野守護職」のパネリストとして参加しましたが、同じパネリストの中に石井先生がいらっしゃいました。先生のこの時のご講演は、
後に「城・居館・宿−小山氏と鷲城−」として文章化されました(石井進『中世史を考える−社会論・史料論・都市論−』校倉書房、
1991年所収)。なお、この時の出演者は他に市村先生、齋藤慎一氏、峰岸純夫先生(司会)で、本当に今思い返してもびびりあがる
ような錚々たる方々ばかりです。
・確か以前から拙稿の抜刷などはお送りしていましたが、実際に石井先生とお会いしてお話したのは、この時が初めてでした。東大
教授でありながら、若輩者の私に対しても、にこやかに、そしてとても丁寧に接して下さったことが深く印象に残っています。
・さて本書のあとがきを拝読すると、石井先生の師匠である佐藤進一先生への畏敬の念が強く感じられます。
かつて私は…一論文の末尾に、次のように記したことがある。「筆をおくに当って私の能力があまりにも貧しく、結局『ここに書かれ
ていることがらのうち正しいことは今まで既に誰かがのべたところのくりかえしであり、新しく展開したことのすべては間違っている』
という言葉の実証に終ったに過ぎないのではないかというおそれが胸中を去らない」、と。いうまでもなく、この「誰か」とは佐藤先生
のことであった。…
・石井先生と比較するのも畏れ多い私でさえ、上記のような気持ちになることが度々ありました。しかし、あの石井先生ですら同じような
思いを抱かれていることを知り、私はあらためて佐藤先生の偉大さと、石井先生の学問に対する深い敬意を痛感したのです。
《トップページへ戻る》