CD再探訪-カンタータ-
宗教曲でバッハのカンタータは外すわけには行きません。とはいえ、教会カンタータだけでも200曲もあり、その中からここに書きたい曲を選出するだけで、数か月必要な作業です。鈴木雅明のカンタータ全集が発売された時、発売元であるBISのプロデューサが特に好きな曲を聞かれ、選ぶことは不可能といった主旨のコメントをしていましたが、まったく同感です。今から思えば、その全集が安くなったタイミングで買っておけば良かったと思いますが、すでに66枚のCDからなるコープマンの全集があり、更にその倍のCDとなると、ほとんどがお蔵入りになるのは目に見えています。そんな背景もあり、ヘレヴェッヘが録音した、比較的良く知られたカンタータを中心に、個人的にもお気に入りの曲をランダムに抽出することにしました。最終的にどれを掲載するか、まだ決めていませんが、これまでのスタイルではかなりのスペースを占めそうなので、まず対象のCDを取り上げ、それらについて、まとめてコメントすることにします。
上記は「宗教曲」のページのカンタータのセクションに書いた序文です。つまり、当初は「宗教曲」の一部とするつもりで進めていました。ところが、いざカンタータについて書き始めると、それが「宗教曲」のページの半分以上を占めてしまい、結局、「カンタータ」のページとして独立させることにしました。この「カンタータ」のページのスタイルが他と異なるのは、そのような経緯のためです。本来ならCD毎にコメントするスタイルに統一するのが望ましいのですが、フォーマットを合わせるために書き直すのは、いかにも無駄な作業です。そこで、「宗教曲」のページの一部として、すでに作成済みの部分は、そのまま生かすことにしました。一方、変更が容易な部分と、独立させてから追記した部分については、従来の構成にしています。独立させたメリットは「カンタータ」のページの作成が「宗教曲」と切り離して進められることで、とりあえず10曲ほど選んだところで「宗教曲」より先にアップすることにしました。
この「CD再探訪」はアマティで保有CDを聞き直すという主旨ですが、書いている過程で思うのは、スピーカーによる違いがわかるほど聴き込んでいないCDが如何に多いかということです。カンタータは特にその傾向が強く、こうして集中して聴く機会を作ったことに意義があると思ったほどです。アマティは人の声の再生にとても適していますが、声の質、その鋭さや柔らかさを過不足なく再現してくれるのも優れた点です。それを痛感するのは、書斎で試聴記を書く時です。まずオーディオ・ルームでメモして、それを書斎でまとめるのですが、確認のために書斎のオーディオ装置で聞き直すことがあります。その際、基本的な情報は同じでも、歌手の声質やバックの演奏など、アマティで聞いていなければ絶対分からない、と思うことが多々あります。ハイエンド・オーディオの存在価値は、まさにここにあるということを再認識しています。
「霊と心は驚き惑う」BWV 35

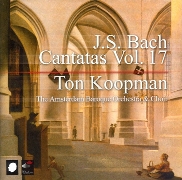

ランダムという意味はBWV順ではないということですが、最初はこのHPでも何度か登場している「霊と心は驚き惑う」BWV 35です。この曲は2曲目のアルトのアリアが有名ですが、第1曲のシンフォニアも一度聞いたら忘れられないような名曲です。ということで、アルトを誰が歌っているかが、このカンタータの注目点なのですが、この3つのCDはその点でも突出しています。まずはカンタータ選出のリファレンスにしたヘレヴェッヘはカウンター・テナーのアンドレアス・ショル。次のコープマンですが、このCDのみ、カウンター・テナーではなくアルトで、かのナタリー・シュトゥッツマンが歌っています。最後の鈴木雅明は珍しく、カウンター・テナーのロビン・ブレイズが表紙を飾っているように、いかにこの曲でアルトが重要か物語っています。なお、コープマンはVol.17とありますが、所有しているのは全集で、ジャケットは皆同じですので、こちらを借用した次第です。
まず第1曲のシンフォニアですが、鈴木とヘレヴエッヘは、ドラマチックという点で双璧で、甲乙つけがたい演奏です。調子の良い高揚感のある曲ですが、バッハらしいリリシズムも感じられます。第2曲のアリアでは、当然ながら歌い手の個性が出て、ショルの方が積極的な印象を受けます。存在感のある歌唱ですが、伸びがあり、宗教曲という縛から解き放たれた、通俗性さえも感じます。一方のブレイズ、ショルよりずっと控えめなのですが、柔らかい歌唱で引き込まれます。抑え気味な歌唱ゆえでしょうか、きらびやかなオルガンの音色が冴えて、絶妙なコントラストを形成しています。この中で、一番淡々としているのが、コープマンです。第1曲からして落ち着いた雰囲気ですが、オルガン協奏曲とも云われるこの曲の特徴が良く聞き取れ、各楽器の動きも良くわかります。

アルトのナタリー・シュトゥッツマンといえば、オーディオ評論家の柳沢氏のリファレンス・ディスクである、シューベルトの歌曲集を思い出します。ステレオサウンドの読者ならすぐ気づくと思いますが、「優秀録音と称せる部類ではなく、声量豊かな彼女の強声では、ともすると硬質な響きを強調しがちでもある」という柳沢氏のコメント。このCDは聞いたことがありませんが、それでもこのカンタータを聞けば、柳沢氏の云いたいことはわかります。一聴、男性かと思うくらい、カウンター・テナーより太く、力強い声です。まさに静かに語るといった感じなのですが、余裕がありすぎて、切迫感が足りない印象を受けます。もちろん、それは比較の話なのですが、二人の優れたカウンター・テナーを聞いてしまうと、時代背景は抜きにしても、宗教曲でカウンター・テナーが活躍している理由が分かります。もちろん、コープマンのカンタータに不満があるわけもなく、バッハの真髄はこうあるべきという演奏ながら、聞いていて楽しいという、音楽の本質的なものも過不足なく伝えてくれる演奏です。
「試練に耐うる人は幸いなり」 BWV 57
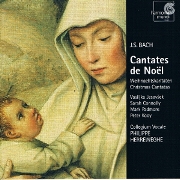
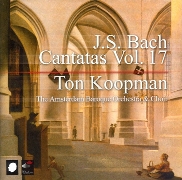

次は「試練に耐うる人は幸いなり」 BWV 57です。最初のヘレヴェッヘのCDは、試聴用リファレンスとして、すでに何度もこのHPに登場している「クリスマス・カンタータ集」です。試聴に使っているのは「笑いは、われらの口に満ち」BWV
110ですが、このBWV 57がカップリングされています。コープマンはBWV 35と同じく、Vol.17に含まれています。鈴木雅明は「ライプツィヒ時代1725年のカンタータ」と題したVol.43となります。このCDにはBWV
110も含まれていて、異なるテーマなのに何故同じ曲の組み合わせなのか、という疑問が生じますが、BWV 110と57は、ライプツィヒのクリスマス・フェスティバルのために作曲されたカンタータということで、偶然ではありません。
そんなわけで、BWV 110はここでは取り上げませんが、ヘレヴェッヘの後で鈴木を聞くと、演奏以前に録音がクリアで、広大な音場と音数の多さで圧倒されます。ヘレヴェッヘでは遠くから聞こえてくるテノールが、そこで歌っているかのような実在感があります。今更ながら、試聴用には鈴木の方が適していると認識した次第です。
前置きが長くなりましたが、BWV 57の聴きどころは第3曲のソプラノのアリアです。特に第2曲の、同じくソプラノによるレチタティーヴォは感動的で、最後の「Und
voller Trauren sprechen(悲しみのあまり次のように歌うことでしょう)」から第3曲のアリアへの入り方が受難曲かと思うほど切ない。ということで、比較もこのアリアがどのように聞こえるかに注目せざるを得ません。これらの中で最も劇的なのはコープマンで、ソプラノはシビラ・ルーベンスというドイツ出身の歌手。経歴は知りませんが、古楽器の楽団との共演は多いようです。確かに、宗教曲に適した透明感のある声ですが、声自体もチャーミングですが、加えて肉声らしい存在感が感じられる点が、このアリアをより魅力的なものにしています。
コープマンと並んで魅力的なアリアが聴けるのがヘレヴェッヘで、こちらもドイツ出身のソプラノ、ヴァシリカ・イエゾフセクです。この人もバッハやヘンデルなどを得意にしているようですが、コープマンのルーベンスに負けないくらいチャーミングで、柔らかく優しい声に魅了されます。変調部のポップ調の旋律も浮き立つような雰囲気で、いつもながらヘレヴェッヘの演奏は楽しめます。
鈴木のVol.43のソプラノはハナ・ブラシコヴァ。この人は先の二人より大分若いようで、日本語の関連サイトも多くあります。チェコ出身ですが、ヘレヴェッヘとも共演しているようです。一聴、日本人かと思えるほど、ストレートな歌声です。宗教曲に相応しい透明感があり、しみじみとした歌唱が聞けます。ただ、アリアでは淡白な感じがあり、切迫感という点では物足りない印象です。もちろん、それは比較の話で、これだけ聞いていれば、不満には感じないでしょう。わずか2曲だけの比較ですが、BWV
35の時とは異なる結果となり、カンタータではソリストの違いが大きいということを改めて知らされます。実はこの曲ではソプラノに加えて、バスも重要な役割を持っています。それらの比較も書き始めるときりがないのですが、ヘレヴェッヘと鈴木はペーター・コーイ、コープマンはクラウス・メルテンスが歌っています。いずれも定評のある歌手ですが、メルテンスの方が隙がなく、充実している印象を受けます。
「主イエス・キリスト、真実の人にして神よ」BWV 127
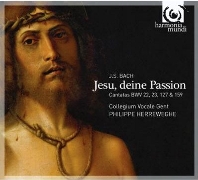


BWV 57がソプラノのアリアが聞きものと云えば、次はソプラノのアリアの双璧とも言える「主イエス・キリスト、真実の人にして神よ」BWV 127でしょう。ヘレヴェッヘはBWV
22、23、159とのカップリングで、コープマンはVol.11になります。鈴木雅明はBWV 1と126とのカップリングです。特に組み合わせのテーマは設定されていないようで、それぞれ独自の構成となっています。ソプラノのアリアは第3曲で、ヘレヴェッヘはドロテー・ミールズ、コープマンはBWV
57と同じシビラ・ルーベンス、鈴木は個人的にお気に入りの、キャロリン・サンプソンの登場です。まずはコープマンです。第1曲は合唱ですが、管弦楽の軽快な運びの中に寂しさが漂う曲で、最初から引き込まれます。第3曲のアリアは序奏から、すでに哀愁を感じる曲です。面白いというか、いささか不可解なのは、BWV
57でドラマチックな歌唱を聞かせてくれたシビラ・ルーベンスが、ここではとても控えめなことです。哀愁というよりも、静かに祈るという感じです。カンタータの役割を意識した演奏ということでしょうか。次のレチタティーヴォも激しさは弱まり、物語を語っているかのようです。
ヘレヴェッヘのドロテー・ミールズ、宗教曲での出演が多いようですが、コープマンとの違いはカンタータという枠組みにとらわれず、純粋に音楽として聞かせる点です。とにかく聞いて幸せな気持ちにさせてくれるのが素晴らしいところで、カンタータでヘレヴッヘが欠かせない理由でもあります。アリアのオーボエによる伴奏もまた聞きものです。次のレチタティーヴォは激しく、アリアとのコントラストを強く打ち出した演奏です。教会に相応しい演奏と、演奏会での演奏の違いと云ったらよいでしょうか、アプローチの違いは興味深いものがあります。
最後に聞いた鈴木雅明ですが、第1曲から明るく、伸び伸びした演奏を聞かせます。低音の動きが良く把握でき、各楽器の音が明瞭に聞き取れます。合唱のスケール感や抜けの良さがあり、一人一人が見えるようです。第3曲のキャロリン・サンプソンは期待に応える歌唱で、このなかでは出色のアリアです。透明感があって、それでいて肉声の暖かさを感じさせる声です。表現は抑え気味で、コープマンの「静かに祈る」雰囲気に近い、ひっそりとした感じがします。ミールズで時折気になる耳を刺すような発声はなく、余裕のあるソプラノで、死を覚悟した決意さえも感じます。鈴木を聞いた後では、ヘレヴェッヘの演奏は、やや表現過多かと思うところもあり、コープマンと鈴木のアプローチが、本来のカンタータの姿という気がします。
「泣き、歎き、憂い、怯え」BWV 12

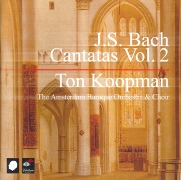
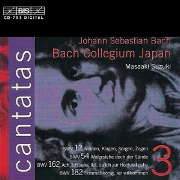
BWV 35のシンフォニアと同じく、聞き応えのあるシンフォニアで始まるのが「泣き、歎き、憂い、怯え」BWV 12です。ヘレヴェッヘはBWV
38、75とのカップリングで、コープマンはVol.2になります。最初のBWV 35でも触れたように、拙宅のは全集なので、代わりにこちらを引用していますが、各巻はCD3枚組みですので、購入には不適かもしれません。鈴木雅明はBWV
54, 162, 182とのカップリングです。まず、第1曲のシンフォニアですが、まるで物語の開始を告げるかのような期待感に溢れています。次の合唱もその雰囲気を引き継いで行きますが、どこかで聞いたことがあると思ったら、ロ短調ミサに流用されていました。この2曲だけでも、カンタータとしての存在価値があると思える名曲です。
今回は鈴木から聞き始めましたが、第1曲から聞き応え十分で、第2曲の合唱が美しく、虚飾を排した純粋で、悠然とした演奏です。演奏時間もこの3枚では最も長い、つまりゆったりしたテンポが、その印象を裏付けています。第4曲のカウンター・テナーは米良美一で、第2曲までの雰囲気を保つかのように、癖のない歌唱を聞かせます。このアリアはBWV
127と同様、オーボエの伴奏が印象的です。第6曲のアリアはテノールの櫻田 亮。こちらもトランペットが旋律を歌うのですが、それより、通奏低音のファゴットが実に楽しく、ちょっとユーモラスな雰囲気もあります。櫻田のテノールも素直な歌い方で、好感が持てます。全体的に、表現は抑えつつも、内に秘めた感情が表出されるという感じです。
意外なのが、コープマンです。これまでのカンタータと違い、第1曲から表情が豊かで、濃い音楽となっています。もちろん比較の話ですが、次の合唱も美しさよりも、力強さが勝っています。録音の影響もあるのでしょうか、フォルテでは耳にきつくなる傾向もあります。第4曲のカウンター・テナーはカイ・ヴェッセルで、米良に比べて味付けが濃く、伴奏のオーボエも雄弁です。第6曲のテノールはクリストフ・プレガルディエン
ですが、ちょっと自慢の喉を聞かせるような雰囲気もあり、共演のトランペットやファゴットが埋もれてしまいがちです。全体に彫りが深い印象で、コープランらしくない印象です。
最後はヘレヴェッヘですが、鈴木同様、抑えた演奏でありながら、表現がより豊かです。合唱もフォルテできつくなることはなく、余裕があります。第2曲までは鈴木と甲乙つけがたいのですが、違いは、やはり独唱陣が登場する第4曲以降です。カウンター・テナーのダニエル・テイラー、テノールのマーク・パドモアが表情豊かな歌唱を聞かせます。とはいえ、コープマンでのプレガルディエンと違い、目立ち過ぎることはなく、トランペットのメロディーがより明瞭に聞こえ、ファゴットもしっかりと支えます。日本人だからというのは短絡的ですが、こうして比較してみると、やはり淡白さというのが、どうしても意識されてしまいます。
「乏しき者は食らいて」BWV 75
次はヘレヴェッヘのBWV 12と同じCDに収録された「乏しき者は食らいて」BWV 75です。もう一つのBWV 38も、小品ながら一度聞いたら忘れられない名曲で、このCD1枚でバッハのカンタータのエッセンスが楽しめる優れものです。加えて独唱陣が最高レベルなのも嬉しい限りです。
BWV 75は2部構成の比較的規模の大きなカンタータですが、第1部は劇的な合唱から開始され、第3曲の喜びを表現したテノールのアリアに続きます。第5曲のソプラノのアリアでは、伴奏のオーボエがもの悲しい雰囲気を醸し出します。内省的な第1部に対して、第2部は外交的というか、明るい曲が多く、大分雰囲気が違うと思われましたが、第2部もただ明るいだけではなく、憂いがあります。

ということで、まずはヘレヴェッヘですが、第1曲の合唱は劇的であるのはもちろん、リズム感にも溢れていて、壮大な物語の開始を予感させます。第3曲のテノールはマーク・パドモア。イギリス出身でバッハの受難曲などで実績のある人ですが、安定しているだけでなく、説得力があります。第5曲のソプラノはキャロリン・サンプソン。透明でありながらチャーミングな歌声が魅力的で、神秘的な雰囲気さえ感じられます。第1部最後のコラールは、明るい中にも寂しさが漂う曲です。第2部の第1曲、シンフォニアは輝かしいトランペットが主役ですが、管弦楽の楽しさも味わえます。アルトのレチタティーヴォを経て、第10曲のアリアは宗教的な説得力を感じる曲。第12曲のバスのアリアも、トランペットが活躍する勢いのある曲ですが、高揚感を高めていく演奏はヘレヴェッヘならではのものです。最後のコラールは時間がなかったのか、それとも第1部と一貫性を持たせるためなのでしょうか、歌詞は一部異なるものの、第1部の終曲が繰り返されます。

コープマンは最初の合唱は、ヘレヴェッヘより丁寧な描き方ですが、余計な演出は避けた自然体そのもの。第5曲のソプラノはルート・ツィーザクという、ドイツ出身の歌手。オペラで活躍しているようですが、コープマンのカンタータ全集もいろんな歌手が登場します。親しみやすい、身近な存在を意識させる歌声で、神秘的は言い過ぎにしても、やはりヘレヴェッヘのサンプソンの良さが際立ちます。第8曲はヘレヴェッヘと大きく違うのはトランペットが目立たないこと。バランスを重視したのでしょうか、同じ曲とは思えないほど地味ですが、第2部の開始にはこちらの方が相応しい気もします。第10曲のアリアとその前のレチタティーヴォにはカウンター・テナーではなく、アルトのエリーザベト・フォン・マグヌスを起用しています。やはり発声が自然で音域での安定感がありますが、ソプラノ同様、身近な存在に感じられる歌声です。第8曲では目立たなかったトランペットですが、第12曲のバスのアリアでは存在感を示します。となると、はやり最初は抑え気味で、イエスを讃える後半に向けて高揚感を高める演出ということなのでしょうか。ただし、コープランらしく演奏自体は控えめで、最後の合唱も極めて自然体で聞かせます。
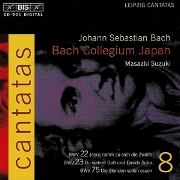
鈴木雅明は第1部の合唱での管弦楽が表情豊かで、劇的と思ったヘレヴェッヘより更にワクワク感があって、引き込まれます。いつもながら、鈴木のCDでまず気づくのは録音の良さ。これは初期の録音なのでCDですが、SACDと遜色なく、低音が良く聞き取れ、まるで楽譜が見えるようです。第3曲のアリア、テノールはゲルト・テュルクですが、歌声が強調されることはなく、バックが良く聞こえるので楽しめます。第5曲のソプラノは初期の録音でよく登場する鈴木美登里。素直で優しい歌い方は好感が持てますが、いささかインパクトが弱く、平板的に聞こえます。比較するのは不適切かもしれませんが、サンプソンの場合、優しさのなかにも力強さがあり、そういった表現力が加わると、曲の良さが更に生きてくるように思います。第8曲のシンフォニアは、早いテンポで軽快ですが、トランペットはヘレヴェッヘほど目立たず、絶妙なバランス。第12曲のバスのアリアも勢いがあり、バックの管弦楽の存在が際立つためでしょうか、他の曲に比べあまり印象に残らない第3曲のテノールと、このバスのアリアが、色彩感豊かに感じられます。
「神よ、われら汝に感謝す」BWV 29
ここでアーノンクールの登場です。拙宅のコレクションはヘレヴェッヘ、鈴木雅明、そしてコープマンに偏っていて、アーノンクールのカンタータはこれ一枚のみです。カンタータはとにかく曲数が多く、ある程度絞らないとCDの枚数が膨大になりますので、アーノンクールまで手が回らなかったということで、避けているわけではありません。

このアーノンクールには、「目覚めよとわれらに呼ばわる物見らの声」で有名なBWV 140と、BWV 61及び29が収録されていますが、ここで取り上げるのは「神よ、われら汝に感謝す」BWV 29です。このCDは2006/2007年の録音ですが、まったく同じ曲の1974/1976/1984年の旧録音との2枚組という、珍しい構成のCDです。新旧比較はともかく、これまでの3人の指揮者とは異なり、同じ古楽器でも分厚い響きで、悠然と歌いあげるというイメージの演奏です。
第1曲はオルガン協奏曲と云っても通じるようなシンフォニアで、カンタータというより管弦楽組曲の印象です。第2曲の合唱は名曲ですが、BWV 12と同様、ミサ曲ロ短調に引用されています。第3曲のテノールのアリアはバックの管弦楽が聞きもので、ハレルヤの歌詞通り、晴れやかな歌唱が楽しめます。第5曲のソプラノのアリアはこのカンタータの聴きどころのひとつ。何とも切ない曲で、ソプラノはクリスティーネ・シェーファー。この人も透明感のある声ですが、伸び切らないというか、やや抑圧されたような発声が気になるところです。第7曲のアルトのアリアもオルガンの伴奏という珍しい組み合わせ。最後の合唱は力強く、空間一杯に広がる合唱が心地よく響きます。アーノンクールの良さはアルノルト・シェーンベルク合唱団にある、と云っても良いくらい見事な合唱が楽しめます。録音も優秀で、低音が力強いので、バランスが良く、深々とした響きが楽しめます。合唱のみならず、独唱のエコーも強いので教会での録音かと思いきや、かのムジーク・フェラインでした。

ヘレヴェッヘはBWV 119、120とのカップリングです。第1曲はテンポが早く、軽快さが心地良く感じられます。第2曲の合唱はアーノンクールに比べると、ハイ上がりのバランスですが、スケール感のある響きが聞けます。第3曲のアリア、テノールはBWV 75のマーク・パドモアで、ただ晴れやかではなく、憂いも感じる歌唱です。第5曲のソプラノはデボラ・ヨーク。この人はコープマンとも共演していますが、素直な発声で、伸びのある心地よい歌声が楽しめます。このカンタータは、合唱が重要な役割を持っているのは言うまでもありませんが、この第5曲ソプラノのアリアもまた中核となる存在です。というのは、この後の第7曲のアルトのアリアは第3曲と同じ曲ですので、この第5曲の出来が全体の印象を大きく左右します。その観点では、ヘレヴェッヘが良くまとまっています。最後の合唱も輝かしく、豊かな響きですが、アルノルト・シェーンベルク合唱団の方がバランス良く聞こえるのは、録音の違いだけではなさそうです。
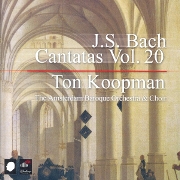
コープマンはVol.20になります。第1曲はリズム感があって、楽しく聞かせます。他の二人がオルガン協奏曲のように聞こえるのに対して、こちらはあくまでカンタータの枠から出ることはありません。第2曲の合唱も軽快なイメージが続きます。ところが、第3曲のアリア、テノールはジェイムス・ギルクリストですが、極めて早いテンポで演奏され、憂いを感じるどころか、急かされてる感じがあって、どうも落ち着きません。実際、演奏時間も上記二人より1分くらい早く、トータル5分強の曲で1分の差は大きな違いです。第5曲のソプラノは、サンドリーヌ・ピオーというフランス出身のオペラ歌手。バロック・オペラで実績を積んだ人ですが、第3曲とは逆にテンポが遅いこともあり、足取りが重い感じがあります。録音の影響でしょうか、BWV 12「泣き、歎き、憂い、怯え」でも感じた高域のきつさがあり、残念ながらあまり楽しめません。その後のアルトのアリア、合唱もテンポが早く、駆け込むような印象があって、コープマンにしては珍しく、この演奏については疑問が残ります。
「わがうちに憂いは満ちぬ」BWV 21
先のアーノンクールのBWV 140と並んで良く知られているカンタータが「主よ、人の望みの喜びよ」を終曲コーラルに含むBWV 147です。鈴木雅明のVol.12で、このBWV 147とカップリングされているのが「わがうちに憂いは満ちぬ」BWV 21です。ピアノでも良く演奏される「主よ、人の望みの喜びよ」ですが、それよりもBWV 21の方が圧倒的に名曲と思います。この曲は第1部と第2部からなる、数あるカンタータでも、その規模が大きいものですが、第1部に対して、第2部の方はインパクトがなく、当初は選曲リストから外していました。しかし、良く聞くと、第2部は趣こそ違いますが、音楽的な完成度がより高く、全体を通じて聞き応えのある曲であることを再認識しました。
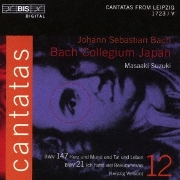
第1曲のシンフォニアも一度聴いたら忘れられない曲で、祈りというか、安らぎに満ちた音楽。次の合唱が、その雰囲気を更に高めて行くのですが、この2曲だけでもこのカンタータの存在価値があります。次の第3曲はソプラノのアリアですが、オーボエのノスタルジックな音色が、何とももの悲しさを醸し出します。鈴木のソプラノは、復活祭オラトリオで登場した野々下友加里。曲の雰囲気によく合った発声と歌い方で、オーボエとの掛け合いも楽しめます。第5曲のアリア、テノールはBWV 75のゲルト・テュルクで、歌詞は「荒波と戦う苦難の連続」といった主旨なのですが、柔らかい響きの曲で、むしろ前向きな明るさを感じます。第1部最後の合唱がまた魅力的で、壮大さと高揚感溢れる名曲です。第2部はソプラノとバスのデュエット。カンタータでもデュエットは珍しくはありませんが、第1部の深刻さとは打って変わって、まるで愛の歌かのよう。どう聞いてもカンタータらしくありません。バスは常連のペーター・コーイですが、彼の柔らかく優しい声と、野々下の素直な歌声がベストマッチです。第9曲では独奏と合唱が組み合わさり、複雑さを増すのですが、更にトランペットが加わり、力強さを増して行き、終曲の合唱である「神への賛歌」へと続きます。

ヘレヴェッヘはBWV 42とのカップリングです。第1曲は鈴木より更に味わい深いというか、静かに祈るといった雰囲気。第2曲の合唱は抑揚があり、感情がより深く表現されています。第3曲のソプラノはバーバラ・シュニック。野々下よりもいくらか肉声らしさを感じますが、大きな違いはなく、いずれも楽しめます。第5曲のテノールは、鈴木のゲルト・テュルクに対して、こちらはハワード・クルーク。クルークの歌唱は安定感があるので、安心して聴いていられる一方、テュルクの方が伸びのある歌声で、随所で力強さを感じます。合唱はいつもながら美しいハーモニーですが、録音の影響もあり、鈴木の方がスケール感を感じます。第8曲のデュエットは、バスは鈴木と同じくペーター・コーイですが、あたかも二人の距離が遠いように感じます。録音の影響もありそうですが、ソプラノが落ち着かないというか、声が脳天に抜けるようなイメージがあって、語りかけるバスとベクトルが違うような印象を受けます。
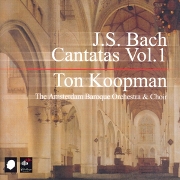
コープマンはVol.1になります。第1曲から静けさを感じる演奏で、音楽で祈りを表現したらこうなる、という感じで始まります。次の合唱も、あたかも教会にいるかのような雰囲気で、神聖さという観点では随一です。ひとつ前のBWV29は良さが感じられなかったので、これぞコープマンという感じです。第3曲のソプラノは何と、ヘレヴェッヘに登場したバーバラ・シュニック。ところがもっと驚くのは、次の第4曲のレチタティーヴォと、次の第5曲のアリアはテノールではなく、ソプラノ・バージョンであること。これもカンタータでは珍しくはないとはいえ、かなり印象が変わります。テノールより悲壮感は増すのですが、高域できつく感じる部分があり、いまいち楽しめません。録音の影響もありそうですが、次の合唱ではそういう部分はないので、やはりヘレヴェッヘでも感じた、脳天に抜けるような発声に原因がありそうです。第2部のデュエットの相手は、コーイではなくクラウス・メルテンスですが、シュニックの声に慣れたせいか、さほど違和感は感じません。なお、第10曲のテノールのアリアもまた、当然ソプラノに代わります。ごく一部でソプラノが耳に障ることを除けば、全体的に美しさと静寂さに満ちた演奏です。
「飢えたる者に汝のパンを分かち与えよ」BWV 39
あまり知られていないカンタータで、しかも全体的に地味ですが、滋味に溢れた曲が多いので、取り上げることにしました。地味とはいえ、最初の合唱と最後のコラールは名曲ですし、その間のアリアも目立たない曲ながら、味わい深いものがあります。第1曲の合唱は7分以上もあり、静謐そのものという開始から、徐々に盛り上がっていく様は、まさに聴きどころで、この曲だけで幸せな気持ちにさせてくれます。アルト、バス、そしてソプラノによる3つのアリアは、レチタティーヴォを経て、最後の充実感のあるコラールへの橋渡しという点で、重要な役割を担っています。聞いたのはいつもの3種で、表現は三者三葉とはいえ、表現の一貫性という点で共通しているのは、やはりカンタータに対する読みの深さの現れでしょう。

コープマンはこういう地味な曲で、その良さがより発揮されるようで、まさにこの曲の表題に相応しい、感謝の気持ちに溢れた演奏が聴けます。といっても、第1曲では、ひっそりした雰囲気から、力強い合唱に至る展開にみられるように、決して抑えた演奏ではなく、むしろ積極的な表現となっています。第3曲のアルトのアリアはボグナ・バルトシュというポーランド出身のメゾ・ソプラノで、アルトの特質を生かした落ち着いた歌い方。第4曲のバスのアリアもリズム感に溢れ、第5曲のソプラノのアリアはフルートが寄り添うように花を添えます。ソプラノはヨハネット・ゾマー。この人、バロック分野以外でも活躍しているようですが、澄んだ良く通る声はこの曲の雰囲気に合っています。コープマンに登場するソプラノは、BWV 57と127はシビラ・ルーベンスですが、これ以外は全て異なるという、たまたまでしょうが、興味ある結果となりました。このヨハネット・ゾマー、とてもチャーミングな声で、コープマンの中ではシビラ・ルーベンスと並ぶ存在と思います。最後のコラールはハーモニーが美しく、荘厳そのもの。

ヘレヴェッヘは、このBWV 39はハルモニアムンディではなく、バージン・クラシックスから発売されていて、しかもミサ曲も含む4枚構成のボックスです。第1曲はヘレヴェッヘにしては控えめな表現ですが、まるで深呼吸するような雰囲気で、深みと精神性を感じます。合唱もコープマンほど強調せず、落ち着いた運びとなります。ちょっと意外な感じを受けますが、演奏自体は充実感があり、訴求力も十分です。冒頭に書いたように、これらの指揮者に共通するのは表現の統一性で、次のアリアがいずれも、第1曲の控えめな雰囲気を保っていることです。第3曲のアリアはカウンター・テナーのチャールズ・ブレットですが、とても落ち着いた歌唱を聞かせます。第4曲のバスは鈴木と同じペーター・コーイですが、リズムを強調せず、静かに諭すという感じです。第5曲のソプラノはアグネス・メロン。この人も初登場ですが、高域も素直な発声で、刺激的なところはなく、静けささえも感じます。そして最後のコラールとなりますが、ここも力強さよりも説得力を感じる合唱です。

鈴木雅明はVol.45で、BWV 129、BWV 187とのカップリング。この3枚で最も「音楽的な」説得力のある演奏です。第1曲からアクセントが強めで、それがワクワク感をもたらし、圧倒的な演奏です。比較的地味な曲なので、あえてそのような演奏なのか、そのあたりはよくわかりません。ただ、他のカンタータでは、むしろヘレヴェッヘにそのような傾向を感じることが多いのですが、このBWV
39に限っては逆なのが面白いところです。第1曲のそうした積極的な姿勢が、次のアリアに引き継がれているというのが、これまた鈴木の素晴らしいところです。第3曲のカウンター・テナー、ロビン・ブレイズはメリハリのある表現で、第4曲のペーター・コーイもヘレヴェッヘの時とは違い、独特なリズム感のある歌い方。第5曲のソプラノは野々下友加里ですが、これまた彼女にしては積極的表現ですが、本来持っている声の優しさで聞かせます。冒頭述べた、このカンタータ演奏の「一貫性」ですが、それが最も明確な形で表出されたのが、この演奏と思います。
説得力のある鈴木、充実感あるヘレヴェッヘ、そして中道というか、「善と施しを説く」この曲のあり方を忠実に表現したのがコープマンといったところでしょうか。
「安らぎと喜びをもてわれは逝く」BWV 125
この「安らぎと喜びをもてわれは逝く」BWV 125は、この前のBWV 39と異なり、有名なカンタータで、当初から候補に入れていました。ところが、カンタータを集中して聞き直した過程で、他にも魅力的な曲が多く存在することを再認識して、ここに来てようやく記載することになった次第です。改めてBWV 125を聞き直してみると、確かに「死にゆく」の歌詞のとおり、劇的な第1曲と、続く第2曲のアルトのアリア、及び最後のコラールは間違いなく名曲です。一方、その間のアリア、特に第4曲のテノールとバスのデュエットなど、第1曲の「死にいく」雰囲気とはあまりに異なる明るさに満ちていて、いささか違和感があります。
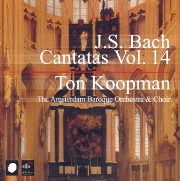
いきなり真打登場ですが、コープマンのBWV 125です。このカンタータの性格は、上述のように深刻さから明るさヘの変化が大きく、その変化をどのように表現するかが聞きどころです。その第1曲、物足りないくらい淡々とした表情で始まります。それでいて合唱の充実感は十分で、まさに絶妙なバランスです。第2曲のアルトはBWV 39と同じボグナ・バルトシュ。かなり遅めのテンポで、いささか悠長すぎる感じもないとは言え、静けさを感じさせる歌唱で、じっくり聞かせます。第3曲も力みがない歌唱で、第2曲までのイメージを引き継いでいきますが、大きく変わるのが第4曲のデュエットです。ここで急にテンポが早くなります。基調は明るいのですが、テンポが早い分、重くならず、軽快さが力強さを緩和するような印象です。テノールはイェルク・デュルミュラー、バスはBWV 36と同じクラウス・メルテンスで、いずれも力強い歌唱ですが、表情が俄然明るくなるようなことはなく、最後のコラールにつないでいく演出はコープマンならではです。

BWV 39で豊かな表現力を見せた鈴木ですが、このVol.32では名カウンター・テナーのロビン・ブレイズのアリアが聞きものです。なお、テノールはアンドレアス・ヴェラーで、この曲で初登場です。BWV 39の再現というわけではないのでしょうが、思わず身を乗り出すような、圧倒的な第1曲の開始。といっても表現が過剰という印象はまったくありません。鈴木の特徴である録音の良さが際立っていて、演奏の雰囲気が漏らすことなく伝わってくるので、そういう印象をより強く受けます。第2曲のロビン・ブレイズは持ち前の伸びのある歌唱ですが、やはりこの曲らしく、表現は抑え気味です。第3曲のペーター・コーイのバスはいつもながらの柔らかい声。次のデュエットですが、コープマンほどではないものの、やはり軽快なテンポです。違うのはテノールとバスの二人のやり取りが、より激しく表現されることですが、だからと言って、雰囲気がガラッとかわるようなことはなく、よくコントロールされている印象です。

最後はヘレヴェッヘです。実はこのヘレヴェッヘを最初に聞いて持った印象が冒頭に書いたことで、改めて聞いてみると、やはり当初とは印象が違います。まず第1曲からして、「劇的」と書いたのはあくまで曲自体のもつ性格で、演奏はむしろ流麗そのもので、まずそこから改める必要があります。思い起こせば、ひとつ前のBWV 39も、あまりインパクトがない曲と思ったけど、実はとても味わい深く、カンタータの世界の奥深さを知った次第です。第2曲のアルトは、ヘレヴェッヘにては珍しく、カウンター・テナーではなく、アルトのインゲボルク・ダンツ。柔らかく澄んだ声質が素晴らしく、しみじみとした歌唱に引き込まれます。第4曲のデュエットはマーク・パドモアとコーイですが、鈴木以上に二人のやり取りが激しく、これが一聴、違和感をもたらした要因なのは、よくわかりました。確かにやり取りは激しいものの、明るいというイメージはなく、そのあたりは鈴木同様、よくコントロールされています。最初の違和感は何だったのかと思う一方、カンタータも聞き込むことによって、真の良さが理解できる、奥深い音楽ということを実感しています。なお、このヘレヴェッヘに含まれているBWV138も名曲で、好きな曲をあげていくと、本当にきりがありません。
「喜び勇みて羽ばたき昇れ」BWV 36
当初目論んだ10曲目ということで、待降節カンタータから「喜び勇みて羽ばたき昇れ」BWV 36を取り上げます。この曲を知ったのは、待降節第1日曜日のカンタータを収録したヘレヴェッヘですが、他にBWV61と62がカップリングされています。これら3曲からどれを選ぶかだけでも悩ましいのですが、代表する曲ということでBWV 36としました。この曲にはかなり複雑な成立の経緯があるようですが、特徴はコラール「いざ来たりませ、異邦人の救い主」が形を変えて二度登場することです。ということで、コラールが主体なのですが、アリアも3曲あり、これら3曲のなかでも規模の大きなカンタータです。このBWV 36は待降節ということで、歌詞の通り明るいイメージが支配的ですが、そう単純でないのがバッハらしいところです。
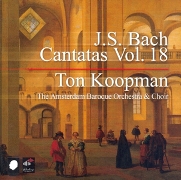
聞き馴染んだヘレヴェッヘとの比較ということで、まずコープマンです。全集を買ったものの、ボックスから1枚抜き出すのは面倒で、つい敬遠しがちですが、いずれリッピングしてサーバーに保存する使い方が良さそうです。第1曲から全身で喜びを表現するといった雰囲気で、いつものコープマンらしからぬ、活気に溢れた合唱です。とは言え、あくまで他の曲との比較であって、基本は節度ある演奏です。ただ、この合唱で気づくのは、バックの管弦楽が良く聞こえることで、喜びを表現している合唱だけではない、という意思表示かもしれません。第2曲はソプラノとアルトの二重奏のコラールで、ここで冒頭の「いざ来たりませ、異邦人の救い主」が登場します。ボーカルが二人ゆえでしょうか、バック、特に通奏低音の演奏がよく聞き取れます。これまでコープランのカンタータで管弦楽に注目することは少なかったのですが、アムステルダム・バロック・オーケストラの力量を見直しました。ただ、そのあたりは録音でかなり左右されますので、最近の録音と比べて損をしているように思います。第3曲、テノールはBWV 29で登場したジェイムス・ギルクリストですが、このアリアもややアクセントが強めです。加えて、オーボエと通奏低音が印象的で、こうなると、聴いている方も、カンタータという枠から離れて聞いてしまいがちですが、次のコラールで、キリストの世界に引き戻されます。

ヘレヴェッヘですが、合唱はリズムが立ち、より彫りが深い印象です。ただ、全体的にはこちらの方がソフトタッチで、全員で喜び歌うというより、地に足ついて歌うという感じです。第2曲のソプラノとアルトのコラール、いずれも美しいハーモニーを聞かせてくれますが、二人のやり取りに勢いを感じます。第3曲のテノールはBWV 12のコープマンで登場したクリストフ・プレガルディエン。先のコープマンほどアクセントを強めたりせず、待降節に相応しい、心に染み入るような歌唱が聴けます。第6曲のテノールによるコラールですが、ここで「いざ来たりませ、異邦人の救い主」が再登場します。ところが漫然と聴いていると気づかないほど、趣が違います。第7曲のソプラノのアリアは、この曲のハイライトの一つ。ヘレヴェッヘは、コープマンのBWV 57で見事な歌唱を聞かせてくれたシビラ・ルーベンス。ここでも思わず聞き耳をたてるような心地よい声を披露しています。ヘレヴエッヘは、このアリアを聞くだけでも価値があります。コープマンは第1部だけでスペースを費やしてしまったので、ここでコメントしておきます。ソプラノはサンドリン・ピアという人で、初登場と思いますが、やや早めのテンポで、軽快な歌声が心地よく響きます。

鈴木雅明のカンタータは、このページを書くにあたって購入したものも少なくないのですが、このBWV 36と次のBWV 95は、手元にあったヘレヴェッヘとコープマンを聞いてから発注したため、最後になりました。まず合唱はヘレヴェッヘよりさらにリズミカルで、力強いのですが、よく統制されています。第2曲のデュエットはアルトがこの鈴木のみカウンター・テナーなので、違った印象を受けるというか、ここはアルトの方がしっくりきます。コープマンはアルトが多いですが、ヘレヴェッヘは曲により使い分けているようで、そのあたりの考え方も興味あるところです。第3曲のテノールは、このVol.47と48のみに登場する水越 啓で、日本人ということをまったく意識させない見事な歌唱が楽しめます。ただし、第6曲のテノールによるコラールは、ちょっとのっぺりした感じで、もうひと工夫欲しいところです。第7曲のソプラノはBWV 57のハナ・ブラシコヴァ。BWV 57での印象そのままですが、宗教曲に相応しい透明感に加えて、しみじみとした歌声がこの曲に良くマッチしていて、ヘレヴェッヘに勝るとも劣らないアリアが楽しめます。それにしても、このBWV 36、合唱もアリアとも粒ぞろいで、聴いていて飽きることがありません。
「キリストこそ わが生命」BWV 95
予定していた10曲を超えてしまいましたが、第1稿の最後は「キリストこそ わが生命」BWV 95です。このカンタータはBWV 36のような待降節を祝うためではなく、「死」がテーマになっています。第1曲のコラールは「キリストに身を捧げ、安らかに逝きます」といった歌詞ですが、どう聞いても活気があり、死を覚悟したイメージとはほど遠い曲なのです。合唱につづいて、ソプラノのレチタティーヴォに導かれて、コラールに入るのですが、このあたりも感動的で、オペラを思わせるドラマ性があります。ところが第5曲のテノールのアリアは、それまでの劇的な音楽から、死を受け入れるべく、繰り返し自分に言い聞かすような趣で、この曲唯一のアリアにしてはインパクトがなく、曲想も異なります。その後、バスのレチタティーヴォを経て、最後は再び力強いコラールで締めとなります。この曲に込められた「死」の意味をどう理解すべきか、気になるところですが、そんなことを知らずとも楽しめるカンタータです。
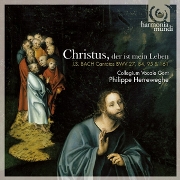
ヘレヴェッヘの演奏ですが、第1曲から、およそ「死」とは縁のない、晴れやかで躍動感のある合唱で始まります。もっとも、同じく「死にゆく」の歌詞を持つBWV 125も「劇的」な合唱で始まると書いていますが、共通するのは、喜びの表現ではなく、清々しい気持ちというのが相応しい表現です。第1曲と間に入るテノールも力強く、合唱をリードしていきます。そういった音楽性を追求する姿勢は一貫していて、冒頭述べた、ソプラノのレチタティーヴォからコラールへの移り方なぞ、ゾクッとするほどドラマティックです。なお、ソプラノはBWV 127で見事な歌唱を聞かせてくれたドロテー・ミールズです。第5曲はバックのオーボエの独特なリズムに特徴がありますが、冗長に感じるところもあります。テノールはハンス・イェルク・マンメルで、この人は初登場と思いますが、適度な抑揚を加えて、変化を与えています。次のレチタティーヴォから、最後のコラールへの流れは、「喜びをもって死におもむく」という悟りの境地への変化が感じられます。
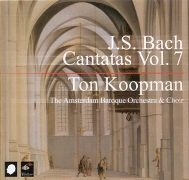
さすがコープマンという感じですが、第1曲はヘレヴェッヘのような高揚感はなく、落ち着いた入り方で、合唱には「死」の意識さえ感じられます。間に入るテノールもリードするというより、合唱がそれを追っていくといった印象です。第2曲のソプラノはリサ・ラーソン。この人もこの曲で始めての登場と思いますが、他の曲も聞いてみたいと思わせる見事な歌声で、愛らしい声ゆえに、コラールというよりオペラのアリアのような雰囲気があります。第5曲のアリアは春の日差しのような穏やかな演奏。テノールは鈴木雅明のBWV 21と75に登場したゲルト・テュルクです。一聴、ヘレヴェッヘのマンメルに比べて表現が乏しい感じがしますが、よく聞くと丁寧な歌い方に好感が持てます。コープマンは、最後のコラールの「喜びを持って死におもむく」に至る道筋をどう描くかに腐心したのではないでしょうか。冒頭の合唱が「喜び」よりも「安らぎ」に重心をおいた表現となっているのも、そういった解釈によるものと思います。聴いていて一番心の落ち着きを得られるのがコープマンで、それがこの演奏スタイルを良く表現していると思います。
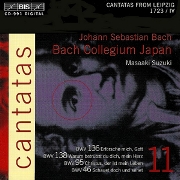
鈴木はVol.11で、BWV 46、136、138とのカップリングです。このCD、珍しく録音クレジットがありませんが、初期の録音らしく、ソプラノはVol.8と同じ鈴木美登里、テノールはVol.3と同じ櫻田 亮が担当しています。第1曲は早いテンポで、ヘレヴェッヘより控えめですが、テノールの入り方がやけに目立ち、その後、合唱が一気に盛り上がります。コープマンを聴いた後ということもあり、落ち着かない感じがあります。ソプラノの鈴木美登里は、伸び伸びした歌い方で、しかも声がチャーミングで好感が持てます。テノールの櫻田 亮ですが、第5曲のアリアは第1曲より落ち着いた感じで、曲自体の性格と良く合っています。いつもながら、録音が良いので、弦のピツィカートが良く聞こえ、この曲の単調さを補ってくれます。このVol.11の時は、海外からのソロの参加はバスのペーター・コーイと、カウンター・テナーのカイ・ヴェッセルのみですが、その後はトップクラスの歌手が参加するようになって、この全集が充実したのは、とても喜ばしいことです。(2023年7月)