CD再探訪-合唱曲-
CDのコレクションをアマティで聞き直すという試み、管弦楽曲から始め、次は声楽曲ということで、順次聞き始めました。ところが、管弦楽曲のコレクションはさほど多くなく、比較的短時間で全てのCDを聞き終えましたが、他のジャンルはそうは行きません。加えて、2021年からテレビの音楽番組の録画を開始したため、そのための時間も必要となります。更に、特定のジャンルばかり続けて聞くというのは、音楽の楽しみ方としても無理があり、長続きしません。そこで、声楽曲というジャンルは設定していても、それに拘らず、聞きたいと思うCDがあれば、その時点でアマティで聞き直すという、本来の目的に沿って進めることにしました。
ただこの方法ですと、ある程度まとまった時点でアップするにしても、設定したテーマのページがまとまるまで、多大な時間を要します。それを実感させられる出来事として、声楽曲を順次聴いている間に、「管弦楽曲」で引用した村上春樹の「古くて素敵なクラシック・レコードたち」の続編が出ました。その巻頭言に「毎日山ほどのクラシック・レコードをじっくり聴き返す作業は、もともと好きで自ら始めたこととはいえ、やはりそれなりに神経を使うし、けっこう時間もとられる」というくだりがあり、妙に共感した次第です。
「声楽曲」について書きたいと思ったのは、個人的に声楽、特に宗教曲が好きということもありますが、アマティで人の声が大きく変わったのも要因です。802SDでは、ともすればモニター的な音に傾きがちでしたが、アマティは、歌手の存在が感じられる、温度感のある声が聞けます。これぞ、アマティの真骨頂と思う一方、声楽曲という分野は、これまた宗教曲、合唱曲、リートと幅広く、CDのコレクションも多岐にわたります。次のターゲットとした「声楽曲」ですが、その範囲が広すぎて、いつ聴き終わるか見通しがたたない状況にて、まずは「宗教曲」というテーマに変更して、一区切りすることにしました。
ということで、「宗教曲」に的を絞って書き進めていましたが、カンタータについて書き始めると、それが余りに多くのスペースを占めて、このページが大きくなり過ぎることに気づきました。一つのページが余りに長いと読みにくいし、スクロールして目的の場所をさがすのも大変です。そこで、更に「カンタータ」というジャンルを、別ページとして設けることにしました。そんな経緯で、カンタータのページが先に投稿となり、「宗教曲」のページが後になってしまいました。
J.S.バッハ マニフィカート BWV 243
バッハの代表的な宗教曲といえば、マタイ受難曲ということになりますが、まずはマニフィカートを取り上げます。マニフィカートというのは、新約聖書の「ルカによる福音書」1章46〜55節の聖母マリアの祈りをテキストとするキリスト教聖歌で、ラテン語訳のルカ福音書1章46節の最初の言葉、Magnificat(=magnify、讃える)によるものです。全部で12曲で構成されていますが、切迫感と優しさの両面で、変化に富んだ魅力ある曲が多く、一度聞いたら忘れられない曲です。演奏時間は30分足らずですが、その分、凝縮された密度の濃い音楽となっています。どういういきさつで、この曲を知ったのかは覚えていませんが、個人的にはマタイを知る前から親しんできました。

バッハとくれば、まず鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパンのこのCDは外せません。いつもながら、楽器の音色が輝かしく、合唱も含めて、一体感が最も発揮された演奏です。最近は海外出身の歌手が多く登場するようですが、このCDではソプラノ、アルト(カウンターテナー)、バスが日本人です。ソプラノは、野々下由香里と、スエーデン出身のミア・パーションの二人で分担していますが、聞けばどちらが日本人かすぐわかります。ミア・パーションはオペラで活躍しているようですが、ここでは宗教曲に相応しい歌い方をしているものの、深みがあり濃い音楽を奏でます。カウンターテナーの太刀川昭は安定感があって、男性のアルトに感じる違和感はまったくありません。
鈴木雅明は、この曲でも、集中力や充実感のある、端正で威厳あるバッハを聞かせます。時にはあまりに整然として、もう少しゆるみがあっても良いのでは、と思う時がありますが、各曲の性格や特徴を見事に捉えた演奏で、引き込まれます。ともあれ、マニフィカートを聞くには、これ1枚あれば十分と思えるCD(ちなみに、後年のバッハ・コレギウム・ジャパンの録音は、ほとんどがSACDで発売されています)です。

古楽器の演奏では、鈴木の先駆者ともいえる、アーノンクールとコンセンタス・ムジク・ウィーンによるマニフィカートです。このCDはTELDECのDAS ALTE WERKシリーズで、珍しく録音に関するクレジットの表記がありません。発売は1984年なので、録音時期は恐らくデジタル録音が始まってすぐの頃でしょう。このマニフィカートの特徴は、合唱にウィーン少年合唱団が加わっていることです。アーノンクールのマニフィカートは、晩年の録音のような切迫感はなく、比較的ゆったりした始まり方ですが、とてもドラマチック。鈴木ほど宗教曲らしくなく、オペラを見ているような物語性を感じるものの、オペラほどの過度な感情移入はありません。特徴があるのはやはり、少年合唱団が加わることで、宗教曲としての純粋さ、あるいは神聖さを意識したのかもしれませんが、合唱としての統一感が弱い印象もあります。録音クレジットがないので、あくまで推測ですが、残響がかなり多いので、恐らく教会ではないかと思います。合唱がまとまりに欠けるように聞こえるのは、多分にその影響もありそうです。弦も荒く感じられるのは、全体にハイ上がりの録音も影響しているようで、それがこの演奏を素直に楽しむことから遠ざけている要因と思われます。

最後は個人的に好きなヘレヴェッへのマニフィカート。鈴木雅明のマニフィカートのところで、このCDだけあれば十分と書いたものの、これを聞くと、まずはゆったりした心地よいテンポに魅かれます。とはいえ、力強さや迫力に乏しいというのではなく、充実感があります。録音は鈴木より古いのですが、低音がよく聞き取れ、基底にある旋律の美しさを浮かび上がらせるような演奏です。第3曲目のアリアは切々と、といっても過剰ではなく、むしろ淡々としているのですが、祈りのような歌唱が印象的です。それに寄り添う管楽器の伴奏が、歌唱に寄り添いつつも存在感を示していて、聞きものです。コレギウム・ヴォカーレ・ゲントの合唱も切れが良く、迫力は十分ながら、圧迫感はありません。ヘレヴェッヘはリズムよりメロディーに傾きがちな印象が強いのですが、この曲については、リズム感も際立っていて、それらの対比があってこそ、音楽が生きてくることを教えてくれます。バッハの音楽に引き込む力は、鈴木雅明も負けていませんが、この演奏には、何とも云えない温もりがあります。総じて、音楽の喜びがより感じられ、親しみやすさという点では随一でしょう。
J.S.バッハ ヨハネ受難曲 BWV 245
このヨハネ受難曲も、アマティで聞き直すということを始めて、その魅力を知った曲の一つです。マタイ受難曲に比べて知名度も低く、ガーディナーの指揮によるCDは持っていたものの、ほとんど聞くことはありませんでした。確かに壮大なマタイ受難曲に比べれば、規模も小さく、演奏会で取り上げられることもほとんどありません。先のマニフィカートについて、切迫感と優しさの両面で、変化に富んだ魅力ある曲が多いと書きましたが、このヨハネ受難曲こそ、その表現がぴったりではないかと思います。
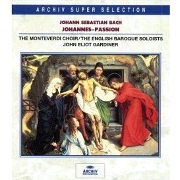
このガーディナーのヨハネ受難曲は1986年の録音で、この頃は個人的に、新しく購入するソースをレコードからCDに切り替えていった時期かと思います。CDの発売は1982年ですが、やはり長年聞き馴染んだレコードの方に愛着があり、しばらくはデジタル録音のレコードを購入していました。バッハの宗教曲で当時所有していたのは、カール・リヒター指揮/ミュンヘン・バッハ管弦楽団のレコードで、そのレーベルがアルヒーフでした。そのアルヒーフからこの頃に続けて発売されたのが、ガーディナー/イングリッシュ・バロック・ソロイスツのバッハで、古楽器による演奏で、従来の重厚なバッハとは違うアプローチのバッハということで話題になりました。ガーディナーのバッハのCDは、このヨハネ受難曲のほか、マタイ受難曲とロ短調ミサ曲もありますが、あまり記憶もなく、長年CDラックに収まったままとなっていました。今回、改めて聞き直して、一聴ハイ上がりの印象ですが、よく聴くと、分解能も高く、各声部も明瞭に把握できて、演奏の質を正しく伝えるという意味で、優秀録音と思います。当時は古楽器特有のギスギスした印象があり、あまり馴染めなかったのかもしれません。
このヨハネ受難曲、第2部のイエスの死のくだりはマタイ受難曲同様、壮絶なのですが、アリアは優しいタッチの曲が多く、より親しみやすい曲です。マタイ受難曲は、何度も聞きたいという曲ではありませんが、こちらはBGMとして聞くのも許されるのではないか思える親しみやすさがあります。モンテヴェルディ合団のハーモニーが美しく、No.26のコラール、No.39の合唱など、天国的な美しさで、清楚な響きは心に残ります。全体的に透明感のある演奏で、節度ある演奏とはこのことと思う一方、説得力や暖かさもあり、この曲の教科書的な存在といえるでしょう。

ガーディナーのCDでヨハネ受難曲の良さを再発見したので、ヘレヴェッヘの最新録音のCDを購入しました。ジャケットからして、いかにも現代風ですが、これはouthere
musicのPHIというレーベルで、ヘレヴェッヘは、かつてはharmonia mundiでしたが、最近このレーベルに移ったようです。さすがに2018年の録音らしく、音数、空間的アンビエンスの情報量が圧倒的に違います。コレギウム・ヴォカレ・ゲントの合唱が聞きものですが、消え際の余韻が残るところなど、臨場感に溢れていて、やはり録音の違いは無視できない要素です。
もちろん演奏も素晴らしく、ヘレヴェッヘの特質が発揮された、より親しみ易く、慈愛に満ちた音楽が楽しめます。第1部#14のコラール、ガーディナーでも引用した#39のコーラスなど、よりリアルな合唱の響きが楽しめます。その#39の前、イエスの死を嘆く#35の切々としたアリアなど、こういう美しい音楽の時間がいつまでも続いて欲しい、と思わずにはいられません。
J.S.バッハ ロ短調ミサ曲 BWV 245
このロ短調ミサ曲、よく知られた曲ですが、改めて聞いてみて、やはり外せないと思い、取り上げることにしました。ロ短調ミサ曲はヨハネ受難曲に比べると、比較的良く聞いた曲ですが、最近は遠ざかっていました。その理由は、冒頭のキリエとそれに続くグロリアがキリストの栄光を讃える、輝かしい曲が続くため、聴いていて疲れてしまうためです。そういうイメージを覆したのが、2023年2月にNHKBSのプレミアム・シアターで再放送された、ブロムシュテット/ゲバントハウス管弦楽団によるミサ曲の公演です。これは2017年6月18日にドイツ・ライプチヒの聖トーマス教会で演奏されたのですが、教会にもかかわらず残響が過多ではなく、コンサート・ホールのイメージに近い響きです。加えて、現代の楽器ゆえ、管弦楽の音色が艶やかで、低弦の動きもよくわかります。CDではうるさくなりがちな合唱も、抜けの良さがあり、この曲の魅力を余すところなく伝えてくれます。テレビの音の方が楽しめるという稀有な例ですが、残念ながら、DVDでしか発売されていないようです。
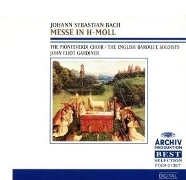
先のヨハネ受難曲で書きましたが、レコードからCDに切り替えていった時期にまとめて購入したのが、ガーディナーのバッハ・シリーズで、手元にはヨハネ受難曲、マタイ受難曲とロ短調ミサ曲があります。このガーディナーのロ短調ミサ曲は、ヨハネ受難曲とほぼ同時期の録音で、当時の古楽器演奏の特徴である、切れの良い、活気のある演奏です。もちろん厳しさだけではなく、優しさも十分感じられるのですが、この曲が宗教曲であることを意識させられる演奏です。澄んだ合唱と、過度に感情的にならない節度のある演奏は、この曲の美しさを際立たせ、ヨハネ受難曲と同様、バッハ演奏の教科書的な存在といえるでしょう。ただ、そういう良さが感じられるのは、後半のクレド、サンクトゥス、そしてアニュス・デイあたりで、前半は、録音の影響もあり、合唱がきついく感じられ、あまり楽しめません。それがお蔵入りになっていた理由ですが、全体にハイ上がりで、高域のサラサラした幕が全体を覆っているような印象を受けます。声楽の得意なアマティですが、このCDをリラックスして聞くには、駆動系も含めた更なるチューニングが必要なようです。

ヘレヴェッヘはこのミサ曲を3回録音しています。こちらは2回目のもので、1996年の録音です。先のガーディナーの録音は1985年ですから、11年の違いがありますが、デジタル録音の進化を加味すると、その差はもっとありそうです。実際、こちらはスケール感が随分と違います。そして、ヘレヴェッヘらしい、柔らかく優しいタッチで、淡々としていると思ったガーディナーが、これに比べると厳しい表現であることがわかります。空間一杯に広がる合唱は迫力十分ですが、一方で焦点が甘く、各声部の動きが把握しにくく、全体の響きの中に埋没する感じです。その傾向は音量をあげると顕著で、合唱部分を圧迫感なく再生するのは難しいCDです。コレギウム・ヴォカレは古楽器の楽団ですが、ガーディナーの方が、いわゆる古楽器らしい切れのある演奏であるのに対して、こちらは、ゆったりした音の運びと表情の豊かさがあります。例えば、クレドのソプラノとメゾ・ソプラノのデュエットの「しかして信ず、一なる主」は、ポップス調の楽しい曲なのですが、各楽器の動きが不明瞭なため、リズムが重く感じられます。その分、表現は濃く深く描かれますが、もう少し軽快さが欲しいところです。

こちらは同じくヘレヴェッヘとコレギウム・ヴォカレ・ゲントによる2011年の録音です。一聴してわかるのは、すっきりとして見通しが良くなっていることです。そういう録音の違いも大きく影響していると思いますが、旧盤に比べるとあっさりした印象で、リズム感のある軽快な響きが楽しめます。ヘレヴェッヘが同じ楽団で再録した理由は、旧盤のゆったりした演奏スタイルに加えて、明瞭さを欠く録音にも不満があったのではないか、と思えるほど違いがあります。冒頭のキリエも合唱が明瞭で、各声部が聞き取れる分解能があり、ともすれば混濁しがちなこの曲から優しく透明な響きが聞こえてきます。ロ短調ミサ曲はアリアも捨てがたいのですが、やはり真骨頂は合唱で、旧盤で感じた圧迫感はなく、歌手の存在が見えるかのような演奏は、冒頭のブロムシュテット/ゲバントハウス管弦楽団の演奏と共通する点です。
筆者も忘れていたのですが、実はこのCD、アキュフェーズのSACDプレーヤ、DP-750の試聴記に引用しています。そこでは、「K-01は隅々まで澄んだ合唱を聞かせるのに対して、DP-750は肉声を感じさせるもの」とコメントとしています。今回も、サンクトゥスを聞いた時、神聖という感じではなく、人間の肉声による賛歌という印象を受けました。
ハイドン テレジア・ミサ Hob.XXII:12
ハイドンはどの分野でも作品数の多い作曲家ですが、ミサ曲も14曲あります。なかでも良く知られた作品は、イギリスの旅を終えてウィーンに帰国した1795年以降に作曲された後期の6つのミサ曲です。有名なオラトリオ「天地創造」と「四季」もこの時期に作曲されています。これら6つのミサ曲には、ハイリゲ・ミサ(1796)、戦時のミサ (1796)、ネルソン・ミサ(1798)、テレジア・ミサ (1799)、天地創造ミサ(1801)、ハルモニー・ミサ (1802)があります。毎年作曲するだけでも大変な作業ですが、これらのミサ曲の構成と歌詞はすべて同じというのは驚異的です。しかも、これらすべてが聞き応えのある大曲であるのも、ハイドンならではというところです。それぞれ魅力のあるミサ曲から一曲選ぶのは、これまた悩ましいのですが、ブルーノ・ヴァイルと古楽器オーケストラ、ターフェルムジークによる「テレジア・ミサ」が素晴らしかったので、これを取り上げることにしました。
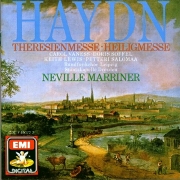
これはネヴィル・マリナーがドレスデン国立歌劇場管弦楽団と1986年に、ドレスデンのルカ教会で録音したもので、テレジア・ミサとハイリゲ・ミサが収録されています。どういういきさつでこのCDを購入したのかまったく記憶がありませんが、ハイドンのミサ曲への関心はこの頃からあったということでしょう。マリナーがアカデミー室内管弦楽団で成功し、各地の名門オーケストラの指揮を始めた頃の録音ですが、先に書いたブルーノ・ヴァイルとは対局の、大編成の現代オーケストラで演奏したらこうなるという見本のような演奏です。分厚い響きのオーケストラと合唱が、圧倒的な迫力と音響で迫ります。もちろん、迫力だけでなく、軽快さを感じる部分もあり、次のヴァイルの演奏を知らなければ、不満に感じることはなかったと思われます。この演奏スタイルの良さがもっとも発揮されるのが、10曲目の Augus dei で、ミサというより、壮大な物語の終わりいう印象です。1986年の録音ですが、現代の録音に比べても劣ることはなく、オケに負けない迫力の合唱も混濁することなく楽しめます。マリナーは、可もなし不可もなしという指揮者と思われがちですが、一連のハイドンの交響曲の演奏と同様、真摯で正攻法な姿勢は好感が持てます。

ブルーノ・ヴァイルとターフェルムジークによるハイドンのミサ曲は、ハーモニー・ミサを除く全5曲がセット発売されています。このCDについても、先のマリナー同様、購入したいきさつは記憶にありませんが、アマティで手持ちのCDを聞き直すという企画で、その良さを再発見したCDの一つです。ハイドンの曲はミサに限らず、いわゆる心地よい、耳に馴染みの良い曲が多いのですが、この演奏は心に迫ります。最初のキリエから透明で、美しい響きに圧倒されます。このCDの特徴は、合唱にテルツ少年合唱団を起用していることで、清楚な印象を受けるのはそのためでしょう。ただ、云われなければ少年合唱団と気づかないくらい、レベルの高いハーモニーを聞かせます。第2曲グロリアの Gratias agimus tibi が聞きもので、悲しみをこらえて前進する、といった感じの曲なのですが、心地よいテンポによる表現に魅了されます。ハイドンはミサにおいても心地よく感じる曲が多くありますが、こういう演奏を聞くと、訴求力というのは、曲そのものよりも演奏による違いが大きい、と思わざるを得ません。クレドはハイドンらしい美しい曲ですが、しみじみとして、それでいて力強さを秘めた祈りを感じさせます。ベネディクトゥスを経て、最後のアニュス・デイに至るまで、一貫しているのは「祈り」の精神で、それがこの演奏を感動的なものにしています。
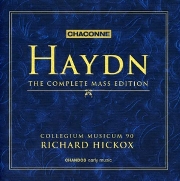
これは上記のCDよりだいぶ後になりますが、ハイドンのミサ曲をいくつか聞いて、他の曲も聞いてみたくなり購入した、ヒコックス指揮、コレギウム・ムジクム90による全集物です。ところが、よくあるように、購入したものの、14曲もあるミサ曲を片っ端から聞いても印象に残らず、たまに引っ張り出すような状況になっていました。このCDはコンサート・ホールでの録音にしては残響が多く、合唱が管弦楽の上に被さったように感じることがあり、802SDでは今一つ楽しめなかったのですが、そのあたりがアマティでかなり改善されたように思います。
改めて聞いてみると、合唱が支配的であることは変わりませんが、各楽器の音色や、合唱の配置が明瞭になっているように思います。分解能という点では802SDの方が勝っていると思いますが、違うのは音のバランスで、それが、聴感上の分解能があがったと感じられる要因と思います。古楽器による演奏ですが、よくある引き締まった音ではありません。例えば、ブルーノ・ヴァイルで感動的だったグロリアなど、ゆったりした歩みを連想させる演奏で、緊張感が伝わってきません。しかし、次のサンクトゥスでは雄大で、スケール感のある演奏に引き込まれます。最後のアニュス・デイも聞き応えがあり、合唱のハーモニーと迫力が圧巻です。先にあげた6曲のうちでは、ハイリゲ・ミサが最も印象に残る演奏ですが、教会でのミサというより、コンサート・ホールで合唱曲を聞いている感じがします。

バッハで何度か登場したガーディナー/イングリッシュ・バロック・ソロイスツですが、ハイドンのミサ曲も、天地創造ミサと、ハルモニー・ミサのCDを所有しています。こちらも優れた演奏で、実はハイドンのミサに関して、テレジア・ミサにするか、天地創造ミサにするか迷いました。 最終的にブルーノ・ヴァイルを選びましたが、このガーディナーの天地創造ミサも、ヴァイルのテレジア・ミサと甲乙つけがたい演奏です。クレドで魅せる、優しさと力強さの対比による劇的な構成、サンクトゥスのドラマチックな表現、ベネディクトゥスでの多彩なメロディーなど、テレジア・ミサより表現の幅が大きく、ハイドンの特色が良く現れた曲です。しかし、それは曲自体というよりも、ガーディナーの優れた演奏に起因するものと、久々にハイドンのミサを続けて聞いた今、自信を持って言えます。古今の名曲は、演奏にかかわらず良いものは良いと思っていましたが、ことハイドンのミサに限っては、そう言い切れないようです。
バッハ クリスマス・オラトリオ BWV 248
再びバッハで、クリスマス・オラトリオ。同じキリストを讃える曲でも、ハイドンはあくまでも明るいのに対して、バッハはただ輝かしいのではなく、理性的かつ思索的なものを感じます。もちろんハイドンの曲にも陰りを感じる部分もありますが、ハイドンの場合、どの曲も深刻さよりも明るさが勝っています。このクリスマス・オラトリオは、クリスマス時には演奏会でもよく登場しますし、受難曲より親しみ易い曲です。

このページですでに何度も登場している、鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパンによるクリスマス・オラトリオです。録音は1998年1月で、さいたま芸術劇場での収録です。同年の12月に録音されたマニフィカートはお馴染みの神戸松蔭女子学院大学のチャペルで録音されていますが、この時はまだ定着していなかったのでしょうか。ただ、さいたま芸術劇場での公演はその後も定期的に行われていて、バッハ・コレギウム・ジャパンとの関係は継続しているようです。
演奏はいつもの鈴木らしい、テンポが早く、きびきびした軽快なバッハ。フットワークが軽く、最初のティンパニーの連打から高揚感に溢れていて、楽しい気分にさせてくれます。独唱陣は、ソプラノ:モニカ・フリンマー、アルト(カウンターテナー):米良美一、テノール:ゲルト・テュルク、バス:ペーター・コーイ。カウンターテナーの米良は女性のアルトと比べても、気になるところは少なく、違和感はありません。ソプラノのモニカ・フリンマーの言葉が聞き取りにくいので、ドイツ人ではないのかと思ったほどで、原因は発声にあるようです。例えば、第二部の13曲のレチタティフの天使のセリフなど、天使の声を意識してのこととは思いますが、もう少し余裕のある歌い方でも良いのではと思います。アリアでは歌唱もさることながら、各楽器の存在が明瞭に聞き取れる、コレギウム・ジャパンの名演が聴きものです。

こちらはアーノンクールとコンセンタス・ムジク・ウィーンによるクリスマス・オラトリオ。コンセンタス・ムジク・ウィーンはマニフィカートでも登場していますが、こちらは2007年録音のSACDで、マニフィカートの録音とはまったく別物で、同じ古楽器楽団とは思えないほど、豊かで柔らかい響きに魅了されます。演奏も、表現の幅が大きく、ドラマチックで力感に溢れています。コンパクトに引き締まった鈴木と、スケール感のある重厚なアーノンクールといったところでしょうか。その違いは同じ曲とは思えないほどです。ひとつ前のハイドンでもそういった違いがありますが、バッハではより明確に表出されるようです。重厚なアーノンクールといっても、決して重くはなく、大作をゆったりと寛いで聴いている趣があります。響きの豊かなムジークフェラインでのライブ録音ということも、そういった印象に大きく寄与していると思われます。同じ楽団が、2013年にムジークフェラインで録音した、モーツアルトの「最後の交響曲集」は力み過ぎで、楽しめないのですが、このバッハは同じ指揮者と思えないほど違います。独唱陣は、ソプラノ:クリスティーネ・シェーファー、アルト:ベルナルダ・フィンク、テノール:ヴェルナー・ギューラ、バリトン:クリスティアン・ゲルハーヘル、バス:ジェラルド・フィンレイ。ソプラノのクリスティーネ・シェーファーが素晴らしい。高域でも伸びがあり、余裕のある歌い方で、宗教曲はこうあって欲しいものです。

バッハのオラトリオでは、上記クリスマス・オラトリオが規模も大きく、よく知られていますが、復活祭オラトリオと、昇天祭オラトリオも小品ながら、魅力ある曲です。マニフィカートを独立して取り上げたので、これらもそうすべきかもしれませんが、一連のオラトリオということで、ここに追記することにしました。
この復活祭オラトリオの特徴は、第1曲がシンフォニア、第2曲がアダージョと、冒頭の2曲が管弦楽の演奏になっていることですが、それらがとても魅力的な曲なのです。ヴァイオリン協奏曲を思わせる曲想で、特にアダージョは、現代でも通用する新鮮さが感じられます。復活祭らしく、心の傷みや悲哀に満ちたアリアが多いのですが、イエスの復活に対する称賛と感謝の力強い合唱で終わります。特に、第5曲のソプラノのアリアは味わい深い曲で、第1、2曲とともにこのオラトリオの聴きどころです。これはヘレヴェッヘとコレギウム・ヴォカレのCDですが、いつもながら親しみやすく、味わい深い演奏で、この曲の魅力を余すことなく伝えてくれます。

もう一つのオラトリオが昇天祭オラトリオで、こちらもヘレヴェッヘとコレギウム・ヴォカレによるものです。ヘレヴェッヘのCDは、これら二つのオラトリオをカップリングしたものも発売されていますが、これはカンタータ BWV 43と、BWV 44とのカップリングとなっています。昇天祭オラトリオは、復活祭オラトリオ(演奏時間42分)より更に規模が小さく、30分足らずの演奏時間です。活力に満ちた楽しい合唱から始まりますが、シンフォニアと言っても良いくらい管弦楽が活躍します。第4曲のアルトのアリアは哀愁漂う旋律で、次のコラールも静けさに満ちた曲です。第8曲のソプラノのアリアは慈愛を意識した優しい歌い方ですが、もう少し力強くても良いのではと思います。最後のコラールは締めに相応しく、最初の合唱と同様、力強く生き生きした曲です。復活祭オラトリオと比べてまとまりが良く、統一感があります。

こちらは鈴木雅明と、バッハ・コレギウム・ジャパンの復活祭と昇天祭オラトリオです。いささかコレクションが偏っていますが、バッハの作品となると、やはり鈴木雅明の演奏を聴いてみたくなります。これは2004年の録音で、一連のカンタータと同様、SACDです。復活祭オラトリオから聴き始めましたが、いつもの輝かしいバッハとはいささか趣が異なり、より落ち着いた色調です。第2曲のアダージョのリードは楽器の指定がないのでしょうか。ヘレヴェッヘのオーボエに対して、こちらはフルートですが、この曲の魅力は変わりません。第5曲のソプラノのアリア、「魂よ、お前の香料は・・」は、マニフィカートでも登場した、野々下由香里が歌っているのですが、ひっそりした感触が、この演奏の雰囲気に良くマッチしています。終曲は鈴木らしい力強い演奏ですが、全体的に襟を正すというか、張り詰めた感じはなく、くつろいで聴く雰囲気です。他方のヘレヴェッヘですが、鈴木のようにリズムが立つことはないのですが、思わず引き込まれる説得力があります。抑揚のあるフレージングが印象的で、表現の多彩さが、この曲の特色を良く引きだしています。
鈴木らしさがより現れているのは、昇天祭オラトリオの方です。いつもの端正で、充実感のあるバッハが楽しめます。第4曲のアルトのアリアですが、鈴木はカウンターテナー、ヘレヴェッヘはアルトを起用しています。嗜好の問題ですが、やはりアルトの方が発声が自然で、安心して聴いていられます。

これはフランス・ブリュッヘン&18世紀オーケストラによる復活祭オラトリオ。鈴木雅明のオラトリオ集を購入した時に一緒に発注したのですが、入手が遅れて追記する形になりました。2011年のライブ録音ですが、ブリュッヘンが亡くなる3年前の録音です。ライブ録音のハンディはまったく感じられない音で、若干響きが過多ですが、混濁感はありません。合唱はカペラ・アムステルダムが参加しており、独唱陣も名歌手が揃っていますが、これはやはり「18世紀オーケストラ」ならではのオラトリオで、第1曲から管楽器が雄弁で、色彩感に溢れています。クリスマス・オラトリオで、アーノンクールとコンセンタス・ムジク・ウィーンの演奏が「古楽器とは思えないくらい豊かな響き」と書いていますが、これも同じ傾向で、ブリュッヘンで予想される緊張感のある演奏とは異なります。響きが豊かで、その分音像も大きめの録音も、そういう印象に寄与しているようですが、第2曲のアダージョや第5曲のソプラノのアリアなど、深々とした響きでじっくりと聞かせてくれます。改めて鈴木を聞き直すと、空間がすっきりしていて、洗練されたクールな印象を受けるのに対して、こちらは、全体を通して素朴な暖かさが感じられるオラトリオです。
ベートーヴェン ミサソレニムス
バッハからベートーヴェンに跳びますが、時系列で云えば、一つ前のオラトリオ以降、ずっとバッハのカンタータを聴いていましたので、ようやく古典派まで来たという感じです。このミサソレムニスですが、ベートーヴェンの作品のなかでも親しみにくい曲、というよりも、その良さがこれまで分からなかったと言うのが正直なところです。それを取り上げることになったのは、スピーカがアマティに替わったからではなく、ヘレヴッヘや鈴木雅明といった、古楽器楽団のCDが発売され、それまで聞いていたジェームズ・レヴァインとウィーンフィルのCDにはない、見通しの良い演奏が聴けるようになったことがきっかけです。

これはジェームズ・レヴァインとウィーンフィルによるミサソレムニスですが、1991年のザルツブルク音楽祭における、祝祭大劇場でのライブ録音です。書いた本人も忘れていましたが、このCD、プリアンプC-3800の導入記に登場します。当該ページでは再生の難しいCDとして取り上げていますが、その点はアマティでも変わりません。ただ、冒頭に書いた最新録音の同曲を聴いて、再びこのレヴァインに戻ると、当初の、合唱の分離が悪くうるさいだけ、という印象が随分と違って聞こえるのがわかりました。言うまでもなく、曲そのものの理解が進んだためですが、さりとて積極的に聴く気にならないのは変わりません。ウィーンフィルに加え、独唱陣もジェシー・ノーマン とかプラシド・ドミンゴなど、ザルツブルク音楽祭ならではの豪華メンバーです。ただ、そのオペラ歌手を集めたことが裏目に出て、ヴィブラートがたっぷり聴いた歌唱はおよそこの曲に相応しくありません。フルオーケストラの重厚な響きは迫力十分ですが、大上段に構えたような演奏は聞いていて疲れてしまいます。当時、ベートーヴェンの代表作ということで購入したものの、ほとんど聞くことがなかったのは納得です。

これはヘレヴェッヘとシャンゼリゼ管弦楽団が2011年に録音したミサソレニムスで、期待して購入したのですが、レヴァインのように拒否したくなるようなことはないものの、感動するには至りませんでした。とはいえ、最初のキリエから、ミサ曲であることを意識させられる整った美しさがあります。独唱陣はマルリス・ペーターゼン(ソプラノ)やベンジャミン・ヒューレット(テノール)など、古楽で実績にある人たちを起用しています。オペラでも活躍しているようですが、独唱陣だけが目立つようなことはなく、合唱や管弦楽と良く溶け合った歌唱が楽しめます。ただし、次のグロリアはレヴァインに比べると、古楽器らしくこじんまりしている印象は拭えません。そのため、合唱が声を張り上げる部分では響きが薄くなる傾向があり、依然として音楽に浸るという気分にはなりません。レヴァインとヘレヴェッヘ、いずれもこのグロリアは再生が難しいという点で共通しており、CDでミサソレムニスを楽しむには、ここがクリアできるかにかかっているという印象です。

こちらはヘレヴッヘより更に新しい2017年に録音した、鈴木雅明とBCJのミサソレニムスです。ここでようやくミサソレムニスが楽しめる音楽になった、記念すべきSACDと云えます。冒頭のキリエから、こんなに美しい音楽だったんだと思わせる、情感豊かでありながら、透けて見えるような演奏です。次のグロリアも、キリエの美しさが引き継がれていきますが、前の二つが飽和状態だったので、音量をあげたくなるほど余裕のあるグロリアを聴けるだけでも感激です。SACDの効果もありそうですが、空間的プレゼンスが圧巻で、合唱や管弦楽の音の動きが良く分かります。鈴木の特徴が最も発揮されるのが、このグロリアでのフーガの部分です。ヘレヴェッヘもフーガということは分かりますが、鈴木の場合、ポリフォニーの提示が明瞭で、更にそれにリズム感が加わり、真に聴いていて楽しめる音楽になっています。それにしても、この違いは何?と思えるほどです。録音の違いもあるものの、演奏も、この複雑な曲の構造が見通せるように意図したものであることは間違いありません。全体を通じて、この作品が、ベートーヴェンらしい力強さと荘厳さ、それに慈愛に満ちた音楽であることを、初めて認識した次第です。

鈴木雅明のCDでミサソレニムスの良さをようやく理解したところで、ブロムシュテットがゲバントハウス管弦楽団と、ベートーヴェンの交響曲全集を出した少し前の2012年に、このミサソレニムスを録音していることを知り、購入したものです。ベートーヴェンの交響曲全集も、すでに何種かあっても、やはり買っておいて良かったと思った経緯もあり、購入したのですが、こちらも鈴木雅明に勝るとも劣らない名演です。鈴木より更にゆったりした、余裕のあるテンポで始まり、こちらはCDですが、音が柔らかく、ライブとは思えないほど良い録音です。レヴァインと同じく、フル・オーケストラらしい分厚い響きながら、ヒステリックなところはまったくなく、美しさに満ちたミサソレムニスです。グロリアのフーガは、鈴木ほどポリフォニーを明示しませんが、各声部は、はっきりと聞き取れます。鈴木の理性的な美しさに対して、こちらはよりヒューマンな暖かさに満ちており、暖かく包み込むような、独自の世界があります。いわば、演奏しているという感覚のない世界と云えばよいでしょうか、ミサ曲らしい神聖な雰囲気に溢れています。バッハを得意にする鈴木やヘレヴェッヘですが、ベートーヴェンの場合、理性よりヒューマニズムが色濃く表出される世界であり、美しさを超えた、感動をもたらす演奏は、ブロムシュテットならではというところです。
ブラームス ドイツ・レクイエム
有名曲が続きますが、このドイツ・レクイエム、先のミサソレムニスより、はるかに親しみ易い曲とはいえ、頻繁に聞く曲ではありませんでした。こういう機会に改めて聞いてみると、この曲が、ブラームスが一連の交響曲を作曲する前の、大規模なオーケストラ曲の最初の作品である、という位置づけが良く理解できます。交響曲に負けないくらい多くのCDが出回っていることも、その現れなのでしょう。ちなみに、何故"ドイツ”が付いているかといえば、通常のラテン語のレクイエムとは異なり、ブラームスが聖書から抜き出したドイツ語の句によるものだからとのことです。どのみち言葉は分からないので、私を含む多くの日本人にとっては、あまり意味を持たないことかもしれません。

本格的なオーケストラ作品なのに、何故いきなりヘレヴェッヘの古楽器楽団なのかですが、たまたま最初に買ったのがこのCDだったということです。1996年のライブ録音ですから、30年近く前に購入したCDですが、あまり興味がわかず、聞き直した記憶はほとんどありません。それにも関わらず、ここに掲載したのは、以下に登場する演奏を聞いて、ようやくこの曲の良さが分かったからですが、アマティがこういう曲の魅力を、良く伝えてくれるということも、その要因です。第1曲は序奏は重苦しいのですが、合唱が力強くも優しく、暖かい日差しを感じるような演奏です。第2曲は男声合唱が主体の、抑圧されたような曲ですが、古楽器特有の軽さはまったく感じられません。さりとて重苦しさはなく、耐えた先に希望を見出すかのような、前向きの感情が支配的になっています。そういった傾向は、次の第3曲も同様で、バリトンの独唱を、バックの合唱と管弦楽が支え、更に盛り上げていく、劇的な曲なのですが、感情表現はあくまで控えめです。第5曲に至るまで耐え忍んでいたものが一気に開放される(と感じられる)のが第6曲で、この演奏は感動的です。合唱付き管弦楽曲と言っても、そこはブラームス、ミサソレムニスのような複雑さはなく、シンプルな構成ですが、それゆえに素直に入れる親しみやすさがあります。このCDを通じて感じられるのは合唱の美しさと暖かさで、それはブラームスの曲そのものの魅力でもあります。

こちらは2007年の録音で、アーノンクールがウィーンフィルを指揮したCDです。合唱はカンタータ BWV 29で登場したアルノルト・シェーンベルク合唱団。録音会場もこの時と同じ、ムジーク・フェラインです。第1曲から、現代オーケストラらしい深々とした響きで、思わず聞き耳を立てしまうような、説得力に溢れた演奏です。第2曲は第1曲より更に暗く、足取りが重くなります。それだけに、So seid nun geduldig...からの明るさは印象的で、その変化を伝える合唱は素晴らしい。ここにはヘレヴェッヘで感じた「穏やかさ」はないものの、感情表現の幅が大きく、緊迫感が圧倒的です。もちろんブラームスですから深刻さもほどほどで、親しみ易い曲であることは変わりません。第3曲は感動的で、思索的な歌唱に対して、バックの合唱と管弦楽が効果的な変化をもたらします。アーノンクールの演奏では、この第3曲は前半の終曲か、と思われるほど重要な位置づけとなっていて、この曲の魅力を引きだした演奏として随一の存在です。第4曲はアルノルト・シェーンベルク合唱団が美しく、この合唱団の表現力は秀逸です。第6曲は第3曲同様、バリトンの独唱がリードしていきますが、更にスケールアップした合唱と管弦楽の壮大な響きが圧巻です。死者の復活らしく、第2曲のような暗さはなく、明るくはないものの前向きに進む雰囲気が感じられます。このCDは全体的に合唱の歌詞が聞き取りやすい特徴があります。録音の良さもありますが、合唱のパートが混濁しないことがその要因と思います。第7曲は「苦労から解かれて安らぎを得る」という歌詞の通り、死者のためのミサ曲らしい終曲です。ここで取り上げた3つのCDのなかでは、最も熱く、感動的な演奏です。
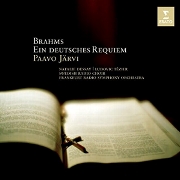
宗教曲でパーヴォ・ヤルヴィが登場することは予想していませんでしたが、2009年の録音で、アーノンクールと同じ頃に発売されて、話題となりました。オーケストラはフランクフルト放送交響楽団で、合唱はスウェーデン放送合唱団、ソプラノはナタリー・デセイ(過去には"ドーセ"と書いていましたが、英語読みが一般化したようです)と、バリトンにルドヴィク・テジェを起用した豪華キャストとなっています。こちらも現代のオーケストラで、アーノンクールとの違いも興味がありますが、"熱い"アーノンクールに対して、"クールな"ヤルヴィというところです。第1曲から美しさに溢れた演奏で、静謐な雰囲気につつまれ、表現は豊かでありながら、醒めた印象を受けます。第2曲も、アーノンクールのような「暗さ」はないものの、思慮深く、沈み込むイメージがあります。第3曲はアーノンクールに劣らず感動的で、こちらの方がドラマチックで、感情の動きをよりダイナミックに表現しています。デセイの登場する第5曲は、このHPで再三登場する、バッハのカンタータ集を思い出される、チャーミングな歌声が楽しめます。この声質がはたしてミサ曲に相応しいかは異論あるところですが、彼女の声の愛らしさが、このCDの魅力になっていることは確かです。第6曲の盛り上がりも十分なのですが、美しく透明感に溢れた演奏には、どこか醒めた印象がつきまとうのも事実で、それが素直に感動できない要因になっているように思われます。全体を通じて、クールさというか、洗練されたセンスの良さが光る演奏であることは確かで、それがドイツ・レクイエムの美しさを際立たせている、という見方も出来ます。
このCD、SACDプレーヤ、X-01XDの導入記に登場します。そこには、「再生の難しさもあり、どうもこの曲には馴染めなかったが、K-01 XDでは、空間的な見通しのよさに加えて、団子状になりやすい音の重なりを解きほぐすかのように提示してくれる」とあります。これはX-01XDによる違いであって、ではアマティではどうかですが、残念ながらそれについてコメントできるほど聞き込んでいないので、何とも云えません。ただ、改めて聞いてみて、アーノンクルーとヤルヴィについては言うまでもなく、これらに比べて録音が劣るヘレヴェッヘさえも、音を気にせず、この壮大な音楽を楽しめるようになったことは間違いありません。
ブルックナー ミサ曲 第2番
ようやくブルックナーまで来ました。ブルックナーのミサ曲といえば、第3番 ヘ短調でしょう。確かに最も規模が大きく、シンフォニーに匹敵する壮大さがあります。しかし第1番から第3番まで改めて聞き直すと、それぞれ良さがあり、なかでも第2番は合唱と管楽のみという、ちょっと変わった構成になっていて、ここでは第2番 ホ短調を取り上げることにしました。シンフォニーで見られる、美しいメロディーを中軸に構築されるブルックナーらしさは、むしろ第2番の方ではないかと思います。この第2番、合唱と管楽器という編成だからでしょうか、第3番は著名なオーケストラや指揮者が多く録音しているのに対して、こちらは合唱団が主体で、それと管楽オーケストラが組んだ、マニアックなCDが少なくありません。

最初は、冒頭に書いた合唱団が主体のCDの一例で、シュトゥットガルト室内合唱団とドイツ管楽フィルハーモニー管弦楽団の組み合わせです。指揮は、このシュトゥットガルト室内合唱団を創設したフリーダー・ベルニウス。そういう背景を知れば、この演奏の予想がつく通り、冒頭のキリエから、透明感あふれる極上の合唱が聞けます。ppが特に印象的で、まるで教会で讃美歌を聞いているかのような雰囲気です。合唱の美しさという観点で、これを超えるものは望めないのでは、と思われる演奏です。合唱が主体というのは、ブラスは十分聞こえてくるものの、その存在を主張せず、柔らかい響きで支えることでも一貫しています。次のグロリアは、キリエに比べれば力強いのですが、やはり控えめな表現、というよりppの部分の方が印象に残ります。ffもフワッと来る感じで、爆発的ではなく、とても上品なブルックナーです。ブルックナーといえば、シンフォニーでのこれでもかという、輝かしい金管の響きを連想しますが、このミサ曲はそういった「攻め」のブルックナーではありません。ミサ曲としてのあり方を示す演奏であり、美しい合唱はとても魅力的ですが、これがブルックナーかと問われれば、いささか違う方向に焦点を当てた演奏のように思います。
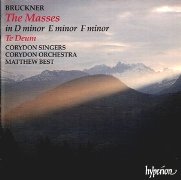
これは、ブルックナーのミサ曲を聞き始めて、全部聞いてみたいと思って購入した全集です。こちらもフリーダー・ベルニウスと同様、コリドン・シンガーズという合唱団を創設創設したマシュー・ベストによるミサ曲。このCDは3枚組ですが、それぞれ個別に録音・発売されたものをセットにしたもので、ミサ曲 第2番は1986年の発売です。このコリドン・シンガーズは1973年の設立で歴史は古く、CDも1990年代が多いのですが、現在も活躍しているようです。管楽隊はコリドン・オーケストラとなっていますが、この楽団についてはCDにもコメントなく、どういう楽団なのかは不明です。シュトゥットガルト室内合唱団と同じく合唱が主体ですが、こちらはシンフォニーを思わせる、分厚いブラスの響きが聞けます。合唱はただ美しいのではなく、ちょっと素人っぽい人間の肉声を感じさせるところがあって、存在感があります。この演奏、合唱と管楽器とのバランスが良く、あくまで合唱が主体であるものの、ブラスの良さも十分感じられ、ブルックナーらしい雰囲気に溢れています。グロリア、クレドなど、十分ドラマチックでありながら表現は控えめで、まさに正攻法なアプローチ。それがこの宗教曲自体が持っている真摯さと誠実さを引き出し、聞く者に感動を与える演奏になっています。

ヘレヴエッヘはブルックナーのミサ曲はもちろん、シンフォニーもいくつか録音しています。このCDは古楽器のシャンゼリゼではなく、現代楽器のアンサンブル・ミュジック・オブリク。最近の録音はほとんどシャンゼリゼですが、この楽団はブルックナーやマーラーの演奏に登場しているようです。最初のキリエから表情が豊かで、フリーダー・ベルニウスの演奏を「静」とすれば、こちらは「動」。このCDは1989年の録音ですが、先のバッハのミサ曲 ロ短調で、1996年の濃厚な演奏に対して、2011年の新録音は随分とあっさりした演奏になっていました。1990年頃のヘレヴッヘは濃く描く傾向があったのか、あるいはブルックナーということで、より近代的な演奏を目指したのか、真相はわかりませんが、この3枚の中で、最も表情が豊かな演奏になっています。実はこの曲を取り上げた時点で、ヘレヴッヘは2019年に、この第2番を再録音してることがわかり、その違いも興味あるところです。積極的なアプローチが奏功しているところは多くあり、グロリアでのホルンの分厚い響きや、オーボエとクラリネットが合唱と絡み合う部分、クレドでアップテンポの劇的な部分と、Et incarnatus est de Spiritu Sancto以降のpp部分との対比など、圧倒的です。積極的表現ではあるものの、押しつけがましさがないのはさすがで、宗教曲というジャンルに拘らず、ブルックナーの音楽としてのあり方を示した演奏と云えるでしょう。
 この稿を書いている時にヘレヴエッヘがシャンゼリゼ管弦楽団と同曲の再録音をしたということが分かり、追加購入したCDです。まず、空間的広がりが圧倒的で、ffでも圧迫感がなく、すべてにおいて余裕を感じます。録音会場はエッセン・フィルハーモニーで、ここでの録音が奏功しているのは一聴して分かります。旧録音と新録音の違いですが、新録音はあっさりしたというより、すっきりした傾向になっています。大きく違うのは合唱とブラスとのバランスで、旧録音では、ともすればブラスが合唱より目立ちがちだったのが、こちらはあくまで合唱が主体。ブラスの音が目立たなくなったというより、柔らかく響き、耳に刺さないというのが正しい表現で、それでいてブラスの動きは旧録音より分かりやすくなっています。合唱団も、新盤はコレギウム・ヴォカーレ・ゲントのみ参加、というのも要因なのでしょうか、シュトゥットガルト室内合唱団に劣らず、洗練された合唱が楽しめます。音に余裕があるのは合唱も同様で、圧迫感のない、深々とした響きは宗教曲に相応しく、充実感があります。特に、最後のアニュス・デイは感動的です。
この稿を書いている時にヘレヴエッヘがシャンゼリゼ管弦楽団と同曲の再録音をしたということが分かり、追加購入したCDです。まず、空間的広がりが圧倒的で、ffでも圧迫感がなく、すべてにおいて余裕を感じます。録音会場はエッセン・フィルハーモニーで、ここでの録音が奏功しているのは一聴して分かります。旧録音と新録音の違いですが、新録音はあっさりしたというより、すっきりした傾向になっています。大きく違うのは合唱とブラスとのバランスで、旧録音では、ともすればブラスが合唱より目立ちがちだったのが、こちらはあくまで合唱が主体。ブラスの音が目立たなくなったというより、柔らかく響き、耳に刺さないというのが正しい表現で、それでいてブラスの動きは旧録音より分かりやすくなっています。合唱団も、新盤はコレギウム・ヴォカーレ・ゲントのみ参加、というのも要因なのでしょうか、シュトゥットガルト室内合唱団に劣らず、洗練された合唱が楽しめます。音に余裕があるのは合唱も同様で、圧迫感のない、深々とした響きは宗教曲に相応しく、充実感があります。特に、最後のアニュス・デイは感動的です。
シューベルト ミサ曲 第6番 変ホ長調 D.850
ミサ曲の次はレクイエムと思っていたら、まだシューベルトがありました。シューベルトのミサ曲は6曲ありますが、拙宅にあるのは第5番 変イ長調 D.678と、第6番 変ホ長調 D.8502曲。これらの2曲はCDも多く出ていて、演奏会でも取り上げられる機会の多い曲です。第5番と第6番は大分性格が違い、第5番はこれがシューベルト?というくらい攻めの姿勢が感じられる曲であるのに対して、第6番はシューベルトらしさが成熟した形で表現された音楽となっています。どちらを取るか悩みましたが、第5番は斬新さがあるものの、それは第4曲のサンクトゥスまでで、ベネディクトゥスとアニュス・デイは拍子抜けするほど平凡です。第6番は全体を通じて完成度が高く、ミサ曲でありながらシューベルトらしさが溢れていて、こちらを取り上げることにしました。

ブルーノ・ヴァイルはハイドンのミサ曲でも登場しましたが、こちらはエイジ・オブ・エンライトゥンメント管弦楽団を指揮したCDです。エイジ・オブ・エンライトゥンメント管弦楽団といえば、フランツ・ブリュッヘンが録音したハイドンの「疾風怒涛」期の交響曲集を思い出します。ヴァイルは同じ古楽器楽団のターフェルムジークが多く、この楽団との共演は多くないようです。このCDの特徴はウィーン少年合唱団を起用してることで、その清楚な歌声はこのミサ曲に相応しい雰囲気を醸し出しています。ピリオド楽器らしく、次のコルボに比べて響きは薄い感じを受けますが、物足りなさを感じることはありません。グロリアで、Domine Deus..から凄味が出てきますが、このあたりの劇的な表現はいささかクールな印象を受けるのは、やはり少年合唱団ゆえでしょうか。古楽器特有の切り込みが鋭い感じはまったくなく、透明感があります。クレドのEt incarnatus est de..からはまるで歌曲のような美しさ。これぞシューベルトという感じですが、ここも少年が加わることで、清涼剤のような効果があります。その分、暗さと明るさの対比が強調される作用もあって、ドラマチックな展開が楽しめます。宗教曲というよりも、シューベルトらしさを、より感じる曲ですが、この演奏における素朴さや純粋さこそが、宗教曲であることを物語っていると言えるでしょう。

ミシェル・コルボと言えば、多くの人は名盤と言われたモーツアルトのレクイエムを思い出すのではないでしょうか。そのCDについては電源ケーブルのPC-Tripple-Cのページに引用しています。コルボは2021年に亡くなりましたが、このCDは、レクイエムから31年後の2007年のライブ録音です。レクイエムで感じられるヒューマンな暖かさはこの指揮者の特徴のようで、このミサ曲も暖かく包み込まれるような演奏です。最初のキリエから豊かな響きに満たされ、ゆったりとした演奏ですが、充実していて緩慢さはまったくありません。ヴァイルの古楽器楽団に対して、こちらはブラス始め、オーケストラの楽器が心地良く響きます。ヴァイルでコメントした「クレドのまるで歌曲」の部分も表情豊かでありながら、濃厚ということはなく、節度ある演奏となっています。このミサ曲はいたるところシューベルトらしい優しさに満ちていますが、グロリアとクレドの終わりの部分はいずれもフーガで構成されています。シューベルトとフーガははあまり結びつかないのですが、宗教曲ということで、やはりバッハやベートーヴェンの影響を受けたのでしょうか。特にクレドの方はスケールが大きく、バッハを思わせる壮大な構成で、深みのある音楽となっています。そういった宗教曲の伝統に倣った部分もありますが、シューベルトならではの美しい旋律がとても魅力的で、コルボの暖かく包み込むような演奏は、聞く者を幸せな気持ちにさせてくれます。
ドボルザーク スターバト・マーテル 作品58
スターバト・マーテル(悲しみの聖母)は、数多くの作曲家の題材となっていますが、拙宅にもペルゴレージ、ハイドン、ドボルザーク、シマノフスキのCDがあります。なかでもドボルザークのスターバト・マーテルは美しい旋律で、印象的な作品です。ドボルザークは、1875年に長女ホセファが出生後わずか2日後に亡くなったのをきっかけに、スターバト・マーテルの制作に着手したものの、1年半近く中断。そうした中、次女と長男を立て続けに亡くし、それがきっかけで再び作曲を再開し、長男を亡くしてから約2ヶ月経った1877年11月に完成というのが、この曲の解説によく引用される逸話です。確かにそういう背景はあったのかもしれませんが、悲しみに打ちひしがれたというイメージではなく、ドボルザークらしい親しみやすさとメランコリーな旋律に溢れている名曲です。

シノーポりが急逝してすでに22年経ちますが、これは亡くなる一年前の2000年にドレスデン国立歌劇場で演奏した時のライブ録音です。この一つ前のシューベルトのミサ曲で登場したコルボもすでに故人ですが、自分の年齢を考えれば当然のこととはいえ、保有CDの演奏家の多くが故人になっていくのは寂しいものです。歌劇場での演奏だからということではないのでしょうが、これはこのページの表題である「宗教曲」とは対局のような演奏です。ライブ録音ということもあるのでしょうが、第1曲から気合十分で、オペラの序曲のような雰囲気に満ちています。こういった類の曲にしてはいささか大上段に構えた感じも否めませんが、最後まで緊張感が維持されるのはライブならではです。とはいえ、独唱者については、この曲に必ずしも合っているとは言えません。特にテノールが活躍する第6曲「あなたと共に、私に真の涙を流させてください」を例にとると、ここでのテノールは歌謡性が強すぎて、まるでカンツォーネのよう。いかにも美声を聞かせるという感じなのですが、その後14節の「十字架の傍らにあなたと共に立ち」では、今度はオペラの悲劇のようで、どうも聞いていて落ち着きません。このページは「宗教曲」というテーマで書いてきましたが、ドボルザークの時代までくれば、宗教曲であることに拘る必要もなく、スターバト・マーテルというテーマによる音楽物語と捉えるのが良さそうです。第7曲の合唱「処女よ、処女たちの中で最も気高い処女よ」では崇高なイメージの合唱が美しく響きますし、やや濃厚ではあるものの、説得力のある演奏を楽しむことができます。

これはヘレヴェッヘが、現代楽器オーケストラであるロイヤル・フランダース・フィルと2012年に録音したスターバト・マーテルです。予想通り、シノーポリの濃厚な世界とは異なり、淡白ながら厳粛な雰囲気で始まり、静けささえも感じる、節度ある演奏が繰り広げられます。それ故に、抒情的なメロディーの美しさが一層、心に響いてきます。第2曲もロマンチックに流れることなく、清楚でストレートな表現となっていて、素直に音楽の魅力に引き込まれます。独唱陣も、そういった演奏に相応しい素直な歌い方で、オペラにはなりません。とはいうものの、曲自体が持つ性格から、宗教曲を聞いているという雰囲気にならないのはシノーポリと同じで、もはや古典的な宗教曲の時代ではないということなのでしょう。第3曲はドラマチックな曲ですが、それを強調することはなく、むしろ悲しみの心情が感じられるような演奏です。テノールはドイツ出身のマクシミリアン・シュミットで、モーツァルトやワーグナーの作品を多くやってるようですが、第6曲では「あなたと共に、私に真の涙を流させてください」の歌詞に沿った、暖かく包み込むような歌い方。その基調は、劇的な第14節以降も変わりません。テノールに限らず、独唱歌手陣の自然な発声は、やはりこの曲が宗教曲であることを意識させてくれます。合唱はいつものコレギウム・ヴォカーレ・ヘントで、澄み切った合唱が美しく響きます。全体を通じての自然体が、この曲の美しさを際立させ、聞いている者を幸せな気持ちにさせてくれる名演です。
ベルリオーズ レクイエム ト短調 Op.5
レクイエムは先のスターバト・マーテルより更に多くの作曲家の作品があり、有名なモーツアルトからブリテンまで、作曲年代も広範囲に渡ります。中でもモーツアルトとフォーレは、CDもこれでもかというくらい多く出回っていますが、ここではベルリオーズの最高傑作とも云われるレクイエムを取り上げます。拙宅には次のロジャー・ノリントンが指揮したレクイエムがありますが、最初の第1曲で丁度良いボリュームにセットすると、第2曲の「怒りの日」で、Tuba mirum spargens..の部分で8対のティンパニと、4群のバンダが加わるところから物凄い大音量になり、聞くに耐えなくなります。逆にそのピークに合わせてボリュームをセットすると、今度は出だしの音量が小さすぎて、冴えない音になり、最後まで聞きとおすこともなく、長年CD棚に収まっていたCDです。そんな経緯があり、この曲を取り上げたのは、その音楽よりも、はたしてアマティでこのCDを上手く再生することができるかが関心事でした。

上述のとおり、このノリントンのCDはオーディオ的観点から取り上げたのですが、ようやく楽しめるようになったのは、実はアマティよりも、プリアンプをC-3900に代えたことが大きく寄与しています。C-3900については当該ページを参照いただくとして、このCDはノリントンが、シュトゥットガルト放送交響楽団を指揮した2003年のライブ録音です。ノリントンはN響の定期公演で指揮したことがあり、その時は遊び心のある軽妙な指揮ぶりでしたが、こちらは正攻法というか、極めてシリアスな演奏です。第1曲から荘厳な雰囲気で始まり、合唱も冷静というか、感情を抑えた表現で、ベルリオーズらしいドラマチックさはあまり感じられません。冒頭述べたように、このCDの第2曲「怒りの日」の迫力は圧倒的なのですが、この演奏というよりも、この曲自体がおどろおどろしく、音楽的にはやり過ぎの感もあります。通して聞いてみて改めて思うのは、このレクイエムの本当の良さは、第4曲以降ではないかという気がします。その第4曲「われを探し求め」は力強く、かつドラマチックな曲で、高揚感に溢れています。第2曲のような力づくでないのが何より楽しめます。ただ、ここでもノリントンは美しい演奏ですが、そういった内から湧き上がってくるような情熱は感じられず、教会でミサをきいているような雰囲気です。第6曲のラクリモザも美しい曲ですが、ここでも迫力は十分ながら、ちょっと遠くを見ているような、客観的な雰囲気が感じられます。飛躍しすぎかもしれませんが、ガラス細工のような美しさに満ちている演奏ゆえ、カラヤンの演奏を連想してしまいました。

これもライブ録音ですが、アントニオ・パッパーノが、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮したCDで、2019年の録音です。これだけの規模の曲はライブとならざるを得ないようで、どちらもライブ録音ですが、ノリントンのほどダイナミックレンジは広くなく、ボリュームの設定で迷うことはありません。パッパーノはオペラの指揮が多いことと関連しているのか、ノリントンとは対局のヒューマニズムに溢れた演奏です。第1曲から合唱の響きが異なり、実在感があります。その分、宗教曲という雰囲気は乏しいのですが、一方で親しみ易く、素直に音楽に入っていけます。第4曲もタッチが柔らかく、合唱も悪く言えば統制感に欠けるのですが、そこがかえって親しみ易く、訴求力があります。第6曲の「ラクリモザ」も感動的で、後半の盛り上がりも第2曲と違い構えたところがなく、素直に楽しめます。この演奏の聞きどころは第7曲「奉献唱」です。前半は祈りの曲で、ベルリオーズ得意のファンタスティックなイメージはなく、宗教曲らしい音楽となっています。しかし、後半は管弦楽が主体となり、低弦の動きなど、幻想交響曲を彷彿とさせる曲想で、ミサのためというよりも、音楽的趣向を優先させたイメージがあります。第9曲「サンクトゥス」ではテノールに合唱が応えるという古典的手法が取られ、しかも締めにはフーガ形式も採用するなど、第7曲以降は古典回帰が見られます。全体を通じて、音楽が生きているのがパッパーノの演奏で、ベルリオーズがこの曲に込めた熱気を存分に味わうことができます。

ベルリオーズの壮大なレクイエムの対局ともいえる、サン・サーンスのレクイエムを追記しておきます。同じフランス人作曲家で、年代も近いのですが、その音楽はベルリオーズの方が前衛的で、サンサーンスの方がより近代に近いというのは意外に思います。このレクイエムですが、傑作ということでもなく、あまり知られていませんが、サン・サーンスらしい美しい旋律に溢れていて、個人的にはベルリオーズより好きな曲です。
全部で8曲で構成されていますが、第3曲のRex tremendaeとか、第4曲のOro supplexとか、あまり聞きなれない表題が付いています。第1曲のRequiem
Kyrieから、ロマン派のレクイエムであることを知らされるドラマチックな入り方です。管弦楽に独唱者が加わると、すぐ静かな祈りの音楽になりますが、ハープが聞こえてくるのは、いかにも近代のレクイエムらしいところです。第2曲の怒りの日はオルガンと金管が分厚い響きを聞かせて、交響曲
第3番を思わせます。テノールがLiber sciptus profereturを歌うところから抒情的になり、力強いながらも美しい合唱に引き継がれます。第6曲のSanctusも、この怒りの日と同様、オルガンと力強い合唱が聴けますが、決して威圧的ではありません。全体的に美しい旋律と、ひっそりとした雰囲気に満ちていますが、最後のAgnusは演奏時間は8分で最も長く、感動的な曲です。一度聞いたら忘れられない劇的な旋律で始まりますが、まるでイタリアオペラの一節かのようで、とてもレクイエムとは思えません。そのメロディーが独唱と合唱に引き継がれて、展開して行きますが、この曲だけでも、このレクイエムの存在価値があると思える名曲です。
ヘンデル メサイア
ベルリオーズまで行って、またバロック時代に遡りますが、バッハと並んで宗教曲の傑作と云われるヘンデルのメサイアです。あまりに有名な曲なので、あえて取り上げなくても良いかと思っているうちに、宗教曲のページもほぼ終わりに近づいてきて、やはりこの曲は書いておきたいと考え直して追加しました。拙宅にある2種のCDはいずれもライブ録音で、一つはネヴィル・マリナーとアカデミー室内管弦楽団が、メサイアの初演から250年目となるのを記念して、1992年4月にダブリンで行なわれたコンサート。もう一枚は、アーノンクールとウィーン・コンツェントゥス・ムジクスによる、ウィーン、ムジークフェラインでの2004年12月の公演です。この2枚が対照的な演奏で、そういう違いを記録しておくのも良いと思った次第です。

まず、ネヴィル・マリナーの方ですが、250年記念コンサートらしく、独唱陣は豪華メンバーで、シルヴィア・マクネアー(S)、アンネ・ソフィー・フォン・オッター(Ms)、マイケル・チャンス(C-T)、ジェリー・ハドリー(T)、ロバート・ロイド(Bs)。記念コンサートという一大イベントですが、気負うことなくいつものスタイルを貫くのは、さすがマリナーと思う一方で、あまりに心地良いメサイアなのでBGM的に聞いてしまう恐れもあります。しかも豪華メンバーでありながら、独唱陣も自己主張することなく、素直な歌い方で好感が持てます。このメサイアは3部で構成され、第1部は予言・降誕、第2部は受難、第3部は復活・昇天・罪の贖いの約束となっています。題材からも予想されるように、最も劇的なのは第2部で、ここでの合唱やアリアは聞きものです。一方、第1部は主を讃える曲が多く、あまり面白くないのですが、マリナーの演奏は祝典のような華やいだ雰囲気に満ちていて、物語の流れに素直に入っていけます。管弦楽は現代楽器ゆえに、艶やかで美しく響くのも、明るく軽快な音作りに寄与しています。例えば第1部 #18のメゾソプラノとソプラノのデュエットなど、優しく柔らかい響きに思わず聞き入ってしまいます。さすがに第2部では厳しさや迫力も増していきますが、切れ込みはほどほどで、基調は明るく、美しい音楽が続きます。この演奏を聞いて真っ先に思い浮かべたのは、指揮者は違いますが、管弦楽曲で取り上げた、アカデミー室内管弦楽団によるヘンデルの合奏協奏曲集です。もちろん、こちらは合唱団も加えた大編成で、曲のスケール感はまったく別物ですが、演奏スタイルが似ています。アーノンクールと比べると、いささか物足りない印象もありますが、親しみ易さや暖かさに満ちたヘンデルの世界を過不足なく味わえる演奏です。

アーノンクールの方は古楽器による演奏で、マリナーに比べると響きが薄く感じますが、表情が豊かで彫りが深い管弦楽の動きがよく聞き取れ、それが劇的な効果を高めています。第1部は荘厳なイメージで始まりますが、すぐ軽快な協奏曲風に展開していくといった、曲の構成が透けて見えるような演奏です。比較的単調な第1部でも各曲の表現は多彩で、さすがアーノンクールと思う一方、力強い曲が続くせいか、あまり感情移入できないで進んでいきます。とはいえ、#10のバスによるアリア「For behold, darkness...」では、暗さが出てきて、引き込まれていきます。次の#11の合唱「For unto us a Child is born...」は第1部の聞きどころですが、このあたりの劇的な変化には、マリナー盤にはない凄味があります。マリナーと比較して聞いてしまうと、そういった読みの深さに気を取られますが、これだけ聞いていれば、ヘンデルらしい暖かさとぬくもりも十分感じられる演奏です。アーノンクールの真骨頂は第2部にあり、冒頭の#19から#25に至る合唱は悲痛な叫びが聞こえてきて、圧倒されます。合唱はアルノルト・シェーンベルク合唱団ですが、いつもの緻密な素晴らしいハーモニーを聞かせてくれます。独唱陣はクリスティーネ・シェーファー(S)、アンナ・ラーソン(A)、ミヒャエル・シャーデ(T)、ジェラルド・フィンレイ(Bs)で、各場面に相応しい歌唱で応えます。第3部終盤#46のソプラノのアリアも魅力ある曲ですが、このメサイアには宗教曲という一連の流れから切り離して、純粋に音楽として楽しめる曲が多くあります。このアーノンクールの演奏、云ってみれば、濃い酒のような味わいがあり、曲としての魅力を最大限に伝える貴重なCDですが、圧倒的な演奏は時には重すぎると思うこともままあります。そんな時にはマリナーの"淡白さ"が貴重な存在となって、まさに補完的な関係です。
メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」
「宗教曲」の最後はメンデルスゾーンです。メンデルスゾーンといえば、忘れられていたバッハのマタイ受難曲を上演したことで知られていますが、メンデルスゾーン自身も、二つのオラトリオ「エリア」と「パウロ」を残しています。パウロは1836年、エリアは1846年の作品で、10年の開きがありますが、二つを聞き比べると、パウロがエリアに比べて未熟ということではなく、曲の性格が違います。確かにエリアの方が、壮大でドラマチックなのですが、パウロの方はより抒情的で、優しさに溢れた曲が多くあります。特にパウロにはエリアにはないコラールが5つもあり、これまた静かに語りかけるような音楽で、心に染みる名曲です。個人的にはパウロの方が好みですが、エリアは、そのスケールの大きさから、ロマン派時代のマタイ受難曲と言っても過言ではない傑作です。そういった経緯を踏まえて、バッハから始まったこの宗教曲のページの最後として、メンデルスゾーンほど相応しい作曲家はいないように思います。
この「エリア」というのは旧約聖書の「列王記」に登場する預言者エリヤの生涯を描いた作品で、第1部と第2部で構成されています。ストリーを知らなくとも、それなりに楽しめる曲ですが、第一部の主テーマである、エリアとバアルの預言者との対決と、それをはやし立てる民衆(合唱)など、やはり対訳を見ながら聞いた方が、より理解が深まります。第2部は、エリアは王妃の迫害から逃れて神の山ホレブに身を隠しますが、そこで神のお告げに勇気づけられて再びイスラエルに戻り、バアル崇拝者たちを迫放し、イスラエ
ルを真の神エホバの国とする、というストリーです。ストリーからも予想されるように、第1部、第2部ともにドラマチックな音楽が展開されます。
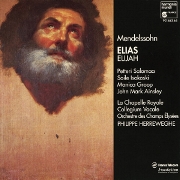
先のメサイヤ同様、こういった大編成の曲ではセッション録音は困難なようで、ここに掲載するCDはいずれもライブ録音です。こちらは大分前に購入したヘレヴェッヘとシャンゼリゼ管弦楽団による「エリア」です。合唱はブルックナーのミサ曲第2番と同じ、コレギウム・ヴォカーレとシャペル・ロワイヤルで構成されています。この演奏で真っ先に感じるのは古楽器特有の響きの浅さですが、それはあくまで比較の話で、力感も十分ある美しい響きが楽しめます。冒頭、管弦楽が盛り上がったところで、合唱が加わりますが、やはりこれは宗教曲というよりも、ロマン派の音楽というのが第一印象です。アリアを始めとする美しいメロディーはいかにもメンデルスゾーンなのですが、オラトリオという古典的な様式が加わりますので、まさに「古典の衣を纏ったロマンチシズム」といったところです。ヘレヴッヘらしい親しみ易さは随所で聞かれ、たとえば第1部の#8、神の力で子供が生き返るシーンでは、神の力を信ずるというよりも、人間同士のやりとりであるかのような、身近で節度ある表現となっています。とはいえ、ドラマチックな表現も不足なく、#10のアハブ王とのやりとりのシーンはマタイ受難曲を思わせる迫力があります。次の#11から#12は第1部の山場ですが、#11ではヘンデルのハレルヤを思わせる輝かしさ、#12での凄味を感じる合唱は素晴らしく、感動的かつ充実感があります。#19のエリア、少年、そして民衆(合唱)とのやり取りも聞きどころですが、独唱陣ののびやかな歌唱が印象的です。ここには次のサバリッシュのような伝統を感じさせるものはありませんが、美しくも暖かい日差しのような音楽には、自然に引き込まれる魅力があります。

こちらはバイエルン国立管弦楽団の創設500周年を記念して始まった、バイエルン国立歌劇場のアーカイヴからのCD化プロジェクトの第1弾ということで、2023年8月に発売されたCDです。そういう経緯のため、発売は新しいのですが、録音は1984年7月の4日で、40年も前の公演です。演奏はサヴァリッシュ指揮のバイエルン国立管弦楽団で、合唱はデュッセルドルフ市楽友協会合唱団です。独唱陣は、エリアのディートリヒ・フィッシャー・ディースカウや、テノールのペーター・シュライヤーなど、それこそ「歴史的名歌手」が出演しています。サバリッシュは長年N響の指揮を務めていますが、残念ながら当時は時間的余裕もなく、生の演奏に接する機会がなかったのは残念です。昨年、N響の2000回定期公演の時に、1986年のN響の第1000回定期公演がサバリッシュだったのも話題になりました。そのエリアですが、まず冒頭のエリア(ディースカウ)の余裕のある歌い方に意外な感じがしますが、その後の管弦楽は活気に満ちていて、まさに生きた音楽。40年前とは思えないくらい音も良く、雄弁な管弦楽と合唱が楽しめます。ヘレヴェッヘが「古典の衣をまとったロマンチシズム」とすれば、こちらはオラトリオ(つまり演奏会形式のオペラ)そのものです。そう感じさせるのは、表現力に優れた管弦楽の存在で、歌手だけでなく、全員でこの壮大なドラマを作るという、まさにオペラの世界が展開されているためです。この演奏を聞いていると、ドイツの伝統といった概念に囚われてしまいますが、古さはまったく感じず、本質に迫る演奏とは何かを教えてくれます。ディースカウは歌謡的とも言える歌い方で、エリアのイメージには似合わない気もしますが、声に余裕があり、力みのないゆったりとした歌い方には、強い精神力を感じます。個々の曲にコメントするのは控えますが、同じようにドラマチックでありながら、第1部は現実世界、第2部は精神世界といった違いもあり、いずれ劣らず充実感の味わえる演奏です。(2023年1月)