CD再探訪
CDのコレクションは多くても、比較的良く聞くCDと、ほぼCD棚に収まったままとなっているCDがあることは、オーディオマニアに限らず、よく見られる傾向と思います。特に、オーディオ装置に手を加えた場合には、その傾向が顕著となり、試聴のために、せいぜい10数枚程度のジャンルの異なるCDを繰り返し聴くことになります。スピーカーをB&Wからソナス・ファベールのAmati Traditionに代えて丸半年。バーン・インも兼ねていろんなソースを聴いてきました。その過程でイコラーザーもほぼ最適化できたと思われ、そろそろ音を確認するための試聴から離れても良い、というよりも手持ちのCDを片っ端から聴いてみようという段階に移行しました。
実はスピーカを交換する前に、このページの表題の写真に掲載した村上春樹の「古くて素敵なクラシック・レコードたち」という、本というより写真集みたいな読み物を購入し、興味のあるページを眺めていました。村上春樹は私とほぼ同年代で、この本には若い頃に聴いたレコードもいくつか登場するのですが、村上春樹はその後も中古のレコードを集めて、1950年代から60年代のコレクションを維持して来たのに比べて、私の方は2001年に手持ちのレコードは全部処分してしまい、当時の演奏を聴くことはほとんどありません。そんなこともあり、まだ802SDの時に自分のコレクションをもう一度全部聞き直してみようと思い立ち、管弦楽から聞き始め、そこで感じたことや、改めて発見したりしたことを「ディスク」のページに纏めるつもりでいました。ところが、Amati
Traditionの登場で、またしても試聴のためのCDだけを聴く作業が続いてしまったというわけです。
過去にはオーディオ機器の試聴時に使ったCDとその鳴り方については、当該機器の導入記として記載していました。しかし、アマティについは、バーン・インに多くの時間を費やしたこともあり、特定のCDがどう聞こえたかといったことは当該ページにはほとんど書いていません。当初はアマティのレポートの続編とすることも考えましたが、このサイトで「DISC」のページ数が、他のテーマに比べて極端に少ないこともあり、改めてアマティで聴き直した結果としての感想、いう意図を込めて「CD再探訪」とした次第です。
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル 合奏協奏曲集 Op.6
CDの保管はアルファベット順なので、管弦楽曲に限らず、バッハから始まることになります。バッハの管弦楽曲といえば、まず管弦楽組曲やブランデンブルク協奏曲、さらには音楽の捧げものとかフーガの技法(これは楽器の指定がないので、管弦楽曲とはいえませんが)などもあり、久々に聴いたのですが、何故かあえて書く気にはなりませんでした。ということで、いきなりBからHに飛びますが、最初に登場するのはヘンデルです。もちろんバッハがつまらないのではなく、ヘンデルの方が今の自分には何故かしっくり来るというのがその理由です。
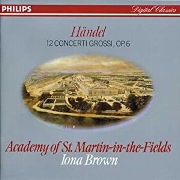
これはデジタル録音が始まった頃のCDで、古式ゆかしきアイオナ・ブラウン指揮のアカデミー室内管弦楽団のもの。アカデミー室内管弦楽団といえば、ネヴィル・マリナーですが、このCDはアイオナ・ブラウンが指揮しています。古式ゆかしきと書いたのは、購入当時(恐らく40年近く前)にそう思った次第で、当時から非常に心地良いものの、物足りなさがつきまとい、たまにしか聴かなかったCDです。改めて聞き直してみて、古式ゆかしきどころか、新鮮かつ豊かな心情が感じられる、とても良い演奏と思います。
アイオナ・ブラウンについて調べると、「1964年にアカデミー室内管弦楽団に加わり1974年からリーダー、ソリスト、監督をつとめた。1986年に大英帝国勲章のオフィサーを授与されている。1990年代より体調の関係でヴァイオリン演奏から指揮者へ比重を移した。」とのことで、指揮者については何の知識もなく聞いていましたが、女性ヴァイオリニストという経歴を知って、妙に納得しました。
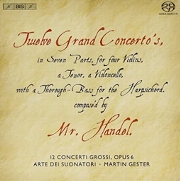
これは現在のオーディオ装置になってから購入したものですが、マルタン・ジェステル指揮、アルテ・デイ・スオナトーリによる合奏協奏曲です。あまり聞かない楽団ですが、ポーランドを拠点に結成された古楽器の楽団です。購入当時(2010年頃?)のことは記憶ありませんが、当時はSACDなら音が良いと信じていた頃で、アカデミーの音に物足りなさを感じて、新しい演奏を聴いてみたく、購入したものと思います。今から思えば無駄な買い物をしたものですが、演奏比較という点では意味があるかもしれません。演奏はアカデミーとは対照的で、古楽器の楽団らしく、溌溂としてメリハリの効いた演奏です。意外に低音が豊かですが、混濁せずとてもクリアな音が聞けます。購入した当時は音の良さは期待通りだったものの、古楽器特有のギスギスした音で、これもあまり馴染めなく、ラックに収まったままとなっていました。
この合奏協奏曲ですが、12曲もあり、全曲の演奏時間は2時間40分程度で、最初から聴いていくと、同じような感触の曲なので、途中で飽きてしまいます。お蔵入りになっていたのは、そのためもありますが、今回改めて全曲聞いてみてこれならば、と思いついたのは、第8曲から第10曲をまとめて聞く方法です。3曲でトータル40分程度ですので、短時間でヘンデルの世界を堪能できます。第8曲と第10曲は短調で、日本人の感性に合うこと、第9曲は、ヘンデルの全ての要素が入ったような曲というのが、この3曲を選んだ理由です。
というわけで、アカデミーとスオナトーリの演奏をこれらの曲で比較することにします。まず、アカデミーですが、アマティで聴くととてもクリアで、この音のどこに不満があったのだろうかという感じです。第8番はゆったりしたテンポで、伸び伸びとした軽快な演奏ですが、さわやかさだけではない大人の音楽。過不足のない演奏で、時代を超えた存在価値があります。第9曲はヘンデルの全ての要素が入ったような音楽。ここでは、安らかさ、喜び、切なさなど、音楽が持ついろんな要素を感じ取ることができます。第10曲の序曲は荘厳そのもの。壮大な物語の始まりを感じさせます。現代なら、さしずめ大河ドラマのテーマ音楽みたいです。その序曲に応えて、その後の曲も実にドラマチックな展開です。
対するスオナトーリですが、弾力性のあるリズム感に溢れた演奏です。古楽器の切れの良い特性を生かした演奏ですが、強弱あるいは緩急の差が大きいので、活気はあるのですが、どうも落ち着きません。確かにヘンデルの音楽は、オペラなど、激しい感情を表出した曲も多いのですが、この合奏協奏曲は悠然とした演奏の方が似合います。第8番はメリハリの効いた演奏で、音楽のスケールは大きいのですが、常に緊張感がつきまといきす。第9番はこの楽団の真骨頂で、第1曲のラルゴがしっかりした足取りで、この楽団の演奏スタイルが生きています。第3曲は短調で、シチリアーナ調の曲ですが、最後の、これまた短調のメヌエットともども絶品です。ドラマチックな表現も過剰にならず、素直に楽しめます。第10番は別の曲かと思うくらい、アカデミーの演奏と違います。第1曲の序曲、楽器の音色は軽いにもかかわらず、重厚さを出そうとしているのですが、それが「重い」印象を与えます。アリアも深刻過ぎて、楽しむという雰囲気ではありません。第9番ではあれだけ自然な音楽を奏でることができる楽団なのに、短調の2曲では何故こうも重くなってしまうのか、実に不可解です。
アルバン・ベルク 抒情組曲
実はこのページで取り上げる曲の順序について少し悩みました。バッハから聴き始めれば、アルファベット順で次はヘンデルではなくアルバン・ベルクになります。となれば、これが最初に来るべきで、当初はそのように書き始めました。しかしながら、当然ながら聴いてみたいと思うCDや、書き残しておきたい思うものは、その時の気分にも左右されます。カタログならアルファベット順にすべきですが、その時の印象に残ったものを記録するのが最も自然な姿ではないかと思い、時系列での記載を優先しました。

このCDは1996年の音楽展望で紹介されたCDで、当時の評を引用すると、「円熟といえばアバドのベルクもりっぱなものになってきた。今年もウィーン・フィルその他と入れた≪アルテンベルク歌曲集≫≪抒情組曲≫ほか(POCG1970)は70年代ロンドン交響楽団と入れたものと曲はいくつか重なるけれど、演奏の純度に一層磨きがかかってきただけでなく、内容的にも一層痛切味がましてきている。ブーレーズの主知主義的解釈も悪くないけど、私はこちらの音色により親しみを覚える。」この記事からもう26年も経過したというのは信じられませんが、当時は吉田秀和がいうほど親しみやすい曲ではないと思ったのを思い出します。
新ウィーン学派で思い出すのは、カラヤンがベルリン・フィルを振ったレコード(1972-74の録音)で、確か3枚組だったと思います。当時はこれらの作品を収録したレコードは少なく、まずはどんな音楽なのか聴いてみようということで購入したのだと思いますが、シェーンベルクの初期の作品がマ―ラーみたいで、予想と違ったのを覚えています。一方で、12音技法の作品は親しみ易い曲とはいえないものの、気になる存在だったのは確かで、その後、新ウィーン学派と云われる作品のCDはいくつか購入しています。



手元にあるのはジェームズ・レヴァイン/ベルリンフィルの管弦楽曲集(1986年の録音)、およびシノーポリがシュターツカペレ・ドレスデンを指揮した時のものです。シノーポリのは2019年に8枚組で再発されたシェーンベルク、ウェーベルン、ベルクの作品を収録したセットで、録音時期は1988年から1998年の長期に渡り、大部分がライブ録音です。

これは電源ケーブル改修のページで取り上げたCDですが、上記のカラヤンの3枚組のレコードから一部を収録したものです。改めてこれらのCDを聞き比べたのですが、最初のアバドのベルク作品集(アルテンベルク歌曲集、「叙情組曲」からの3つの楽章、「ルル」からの交響的小品)は、吉田秀和の評のとおり、とても親しみやすい音楽となっています。もっとも、これはベルクの作品、それも抒情的な作品ばかりを集めたものなので、余計そのように感じるということはあります。録音もデジタル化初期のグラモフォンは高域の目立つ録音が多かったのですが、これはバランスが良く、ウィーンフィルの分厚い響きが楽しめます。カラヤン、シノーポリとの比較という観点で、「抒情組曲」について云えば、アバドはとても丁寧な作りで、洗練され、都会的センスに溢れた演奏です。特に何かを強調したり、表現するということはなく、節度のある演奏ですが、それが心地よい音楽を作り出しています。
元祖ともいえるカラヤン/ベルリンフィルでは表現の幅が広がり、一聴、同じ曲とは思えない感じがします。より大胆な演奏と云えますが、一方で、この曲の持つ親しみやすさは薄れ、前衛的な印象が強くなります。表現力という観点では、現在もこれを上回る演奏はないのではないでしょうか。第3曲では弦がうねるのですが、ハイ上がりのバランスもあり、曲の美しさは十分伝わるものの、これでもかという張り出しが気になります。このカラヤンの「新ウィーン学派」は最近SACDで発売され、この部分がどのように聞こえるか、興味あるところですが、恐らく本質的な部分は変わらないでしょう。少なくともSACDを買い直す気にはなりません。
シノーポリはカラヤンほどではないけれど、表面的な美しさに留まらない、劇的な演奏です。ライブ録音というのも、気迫に満ちた演奏と感じる要因と思いますが、後半ほど、その特徴が出てきて熱気を感じるのですが、寛いで美しい音楽を楽しむという雰囲気にはならず、何故かあまり印象に残りません。ただ、カラヤンのように人工的ではなく、より素朴というか、素直な表現は好感が持てます。
レヴァインのCDには「抒情組曲」は入っていないので、同じベルクの「オーケストラのための3つの小品」で聞き比べました。抒情組曲が抒情的かつ静謐とすれば、この曲は前衛的かつ攻撃的。とてもスケールの大きな作品で、表現の幅が広く、ドラマ性もあります。レヴァインの演奏は、そういった特徴を良くとらえていて、三つの作品というより、三楽章で構成された組曲のような印象を受けます。基本は抒情性に置いていますが、それだけに攻撃的なシーンとの対比が鮮やかで、曲全体のバランスが良く、古典派に通じる音楽という印象を受けます。
同じ作品6をカラヤンで聴くと、随分と印象が異なり、曲が持つ物語性を、一層スケールアップした印象です。爆発的シーンでも圧迫感はなく、冷静さと緻密さを保った演奏で、抒情組曲以上に「カラヤンの美学」を強く印象付ける演奏です。同時期の録音なのに抒情組曲と比べて音が厚く、ベルリンフィルの能力を最大限に引き出した演奏をこのCDでも十分楽しめます。50年も前にこういう演奏が存在したことは驚きである一方で、抒情組曲以上に、やりすぎという感じがつきまとい、疲れてしまうのも事実です。
なお、前述のレヴァインのCDにはベルクのほかに、ウェーべルンの「管弦楽曲のための6つの小品」およびシェーンベルクの「管弦楽のための5つの小品」が含まれていて、これらの演奏を聞いていると、新しい手法による音楽というより、後期ロマン派を基本としつつも、それをより先鋭化したという感じで、違和感なく楽しめる音楽となっています。
セルゲイ・プロコフィエフ ロミオとジュリエット
プロコフィエフのロミオとジュリエット(音楽界では”ロメオ”が使われていますが、ここでは戯曲に合わせて”ロミオ”と表記します)は、すでにSACDのページで取り上げました。従って、ここでまた同じ曲について書くのは気が引けるのですが、当該ページを書いたのは2006年で、もう16年も前のことですし、改めてアマティで聴いてみて、こんなに楽しい気分になる曲はそうないと思い、再掲することにしました。このロミオとジュリエットはもともとバレエ曲ですが、プロコフィエフも気に入っていたのか、要望があったのか知りませんが、管弦楽組曲とピアノ曲に編集されています。オリジナルのバレエ曲は4幕全52曲からなり、演奏時間は2時間半もかかります。これを演奏会用に組みなおしたのが組曲で、第1組曲(作品64A)、第2組曲(作品64B)、第3組曲(作品101)の3つがあります。ピアノ曲は全10曲で、演奏会でも良く取り上げられ、拙宅にはリーズ・ドゥ・ラ・サールと上原 彩子のCDがありますが、ここでは管弦楽について。

これはロメオとジュリエットの定番とも云える、シャルル・デュトアとモントリオール交響楽団の演奏です。このアルバムはバレー曲からの抜粋で、24曲構成となっています。多くの人にとって、オリジナルのシェークスピアのロミオとジュリエットは読んだことがなくても、有名な戯曲ですので、断片的な知識はあると思います。私もそのたぐいですが、このCDの構成はストリーに沿っていますので、すんなりと楽しめます。この曲を得意とするデュトアらしく、物語を連想させる演出で、何度聴いても引き込まれる魅力があります。12曲目の「バルコニー・シーン」は、コマーシャルなどにも登場する有名なシーンですが、ミュージカルのような甘美な曲です。デュトアの指揮はとても繊細で、心の高まりを、まるで波が押しよせるように表現しています。不安を抱えつつも、今という時を大切にしたいという気持ちを感じさせる、素晴らしい演奏です。全体を通じては統制のとれた、抑制の効いた演奏で、オリジナルであるバレエ曲としてのリズムや流れを重視した演奏と云えるでしょう。以前、デュトアがN響でマーラーを振った時も、演出の上手さを感じましたが、セクハラ疑惑の騒動があったせいでしょうか、その後、N響に登場しないのは残念です。

このロミオとジュリエットはパーヴォ・ヤルヴィがシンシナチ・オーケストラと録音したもので、三つの組曲がすべて収録されています。前述のシャルル・デュトアのCDは全曲からの抜粋ですが、3つの組曲を収録したCDは珍しいと思います。ただし、この組曲は、それぞれ単独で演奏されてもまとまりが良いように組み込まれているため、3つの組曲を続けて聴くと、後戻りするような違和感があって、落ち着きません。そういう意味では、アルバムとして必ずしも最適な構成とは云えないでしょう。
バレエ曲での「バルコニー・シーン」は、この組曲では、第1組曲の「ロミオとジュリエット」となります。改めて聴くと、弦の響きが心地よく、管楽器とのハーモニーも美しく、それでいてブラスの切れもよい、オーケストラの見本のような演奏です。ダイナミックレンジの大きさや、切れの良さなど、録音の良さが楽しめる反面、音像が大きくて解像度が甘く、圧倒されるような迫力を感じるものの、大仰な印象がぬぐえません。このSACDが発売された2003年当時のことを考えれば、SACDの登場が1999年ですから、TELARKが当時、SACDのサラウンド効果を狙って作ったのではないかと思われるふしがあります。組曲を三つも並べたのは、意図的にバレエ曲という縛りから離れて、管弦楽曲としての面白さを追求したということかもしれません。


最後は同じシャルル・デュトアの指揮ですが、オーケストラはN響です。このCDのジャケットですが、いつもはネットから借用しているのですが、同じデザインのものが見当たりません。どのサイトも右側の「N響」の文字がやけに大きい野暮ったいジャケットです。大抵は輸入盤と国内盤は同じジャケットなのですが、これはN響だからでしょうか。それにしても、この違いを見たら、国内盤を買う人はいないのではと思えるほどで、いくらN響が人気でも、ちょっとセンスが無さすぎるのではと思います。対して、左の輸入盤は「N響」の文字がどこにあるかわからない程で、N響と分かると売れないのかなと思えてきます。
演奏は、この3枚の中で抜きんでています。同じデュトアの指揮ですが、録音会場がすみだトリフォニーホール(カップリングの交響曲 第6番はウィーン・コンツェルトハウス)で、低弦のフワァとした響きに、ヴァイオリンの弦の揺らぎがはっきりと聞き取れ、楽器の明瞭さはパーヴォのSACDを上回ります。オーケストラが柔らかく、優しいながらも、抜けの良い分厚い響きを聞かせます。スケールは大きいのですが、整然とした印象を受けるのはN響らしいところです。同じ指揮者の演奏ながら、あか抜けた都会的な雰囲気が感じられるのは録音(もしくはホール)の良さも寄しているのは間違いありません。なお、このCDもバレエ曲からの抜粋ですが、「バルコニー・シーン」ではなく、何故か組曲と同じ「ロミオとジュリエット」となっています。
モントリオールとN響はいずれも英国DECCA制作で、モントリオールのバランスエンジニアはJohn Dunkerley、N響は、交響曲 第6番を収録したウィーン・コンツェルトハウスとすみだトリフォニーで異なり、前者はモントリオールと同じJohn Dunkerleyですが、後者はJonathan Stokesが担当しています。ロミオとジュリエットでこれだけ良い演奏をするN響ですが、カップリングした交響曲 第6番は冴えません。これを目当てにCDを買った人は、間違いなく後悔するでしょう。交響曲の方は、ホールの違いでしょうか、音像が小さくまとまり、スケールが一回り小さくなった感じです。バランスは悪くないのですが、控えめで、生気のない演奏で、とにかく聴いていて面白くありません。ロミオとジュリエットで、あれだけ生きのよい演奏をした楽団とは別物で、管楽器も引っ込みがちで存在感が薄く、N響の良さがまったく感じられません。
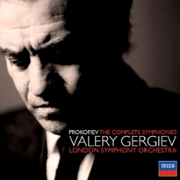
第6番って、こんなにつまらない曲だったかと、比較のために、ゲルギエフの第6番を聴いてみたのですが、リズム感があって、印象がまるで違います。ちなみに、ゲルギエフのプロコフィエフはロンドン交響楽団で、録音担当はバービカン・ホールではいつも登場する、Jonathan Stokesです。同じN響でこれだけ違うのは、ホールの違いよりも、録音担当の違いが大きく影響しているのではないかと推察します。というのも、N響の第6番を担当したJohn Dunkerleyですが、モントリオールの録音も同様な傾向で、あのデュトアにしては控えめな演奏、という印象を受けるからです。N響の実際の演奏がどうだったのかは知る由もありませんが、収録したホールが異なるとはいえ、同じ指揮者と楽団でこれだけ違いがあるとは考えにくく、録音技術者で次第で、オーケストラの力量まで左右されるというのは看過できないことです。
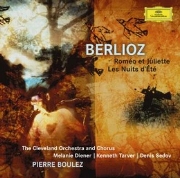
管弦楽曲から離れたついでに、もう一つ付け加えておきたいのが、ベルリオーズのロミオとジュリエット。幻想交響曲に比べて認知度は低いようですが、これも素晴らしい曲です。プロコフィエフの "バレー曲" に対して、こちらは ”交響的絵物語” といった趣。実際、ベルリオーズは「合唱、独唱、および合唱によるレチタティーヴォのプロローグ付き劇的交響曲」と銘打っていたらしい。バルコニー・シーンは、第3部の「愛の場面」として管弦楽により描かれます。これもチャーミングでイマジネーションに満ちた曲ですが、ワーグナーのトリスタンとイゾルデを先取りしたような印象もあります。この大曲の真骨頂は、第5部の「ジュリエットの葬送」以降。まさに絵物語という感じで、ドラマチックなシーンに溢れています。音楽のスケールの大きさという観点では、プロコフィエフの比ではありません。幻想交響曲に並ぶ傑作と思いますが、合唱も含む大編成な曲なので、演奏会で取り上げられる機会が少ないのは残念です。
イーゴリ・ストラヴィンスキー 火の鳥
ストラヴィンスキーといえば春の祭典、というほど有名、かつ演奏会にもよく登場しますが、ここでは「火の鳥」をとりあげました。火の鳥はストラヴィンスキーのいわゆるバレエ三部作の最初の作品で、1910年に初演されています。ちなみに、火の鳥の後は、1911年のペトルーシカ、そして1913年の春の祭典と続きます。この三部作の印象ですが、火の鳥はロシアのバレー音楽の伝統を最も感じる作品で、イマジネーション豊かな作品、ペトル―シカはファンタジーの世界、そして春の祭典はエネルギッシュで、エキサイティングな作品と、それぞれの性格はかなり違います。確かに春の祭典は、従来の優美なイメージのバレー音楽からはかけ離れた存在で、この曲で演じるバレーがエキセントリックで不気味なものになるには容易に想像できます。

春の祭典は、その音色の多彩さやダイナミックさにおいてオーディオマニアにとっても欠かせない楽曲で、2001年に発売されたゲルギエフとキーロフ歌劇場管弦楽団のCDは、発売当時はオーディオショーでは必ずというほど登場していました。実はこのCD、このHPでも「室内音響特性」のページで、音響特性の測定のための音源として使っています。当時は聞きばえのする演奏というイメージしかなかったのですが、改めて聴いてみると、優秀録音であることは間違いなく、SACDを先取りしたような空間一杯に広がるオーケストラサウンド、しかも混濁しないのは特筆すべき点です。演奏も凄味を感じさせるもので、2曲目の「春の兆しと乙女たちの踊り」では弦楽器の切れ込みが鋭く、ダイナミックでありながら、極めて統制のとれた演奏を聞かせるのは、いかにもロシアのオーケストラという感じです。ロシアのウクライナ侵攻で、聞き手のロシアに対するイメージが影響しているせいか、指揮者というよりも指揮官というのが相応しい印象を受けるのは仕方ないことなのかもしれません。

このCDはサイモン・ラトルがロンドン交響楽団に就任して間もないころのライブ録音ですが、発売されたのは比較的最近です。録音はバービカンホール専属のJonathan
Stokes。ラトルらしい、情景描写が精緻で、表情がとても細やかです。この火の鳥は、バレー音楽としての全曲盤と演奏会用に再構成された組曲があり、その組曲も1911年版と1919年版、さらに1945年版があり、いずれも全曲盤からの抜粋ですが、構成が微妙に異なります。組曲については、この後のマリ・ヤンソンスのところで触れるとして、聞いた印象では、先のロミオとジュリエットと同様、全曲版の方が圧倒的に面白い。加えて、ロミオとジュリエットと違い、全曲といっても50分足らずですので、長いと感じることはありません。とはいえ、CDに収めるとなると、これ一曲で終わってしまうので、CDの売れ行きに影響するのは間違いなく、他の曲とカップリングするために、組曲の方になってしまうのは仕方ないことかもしれません。
全曲盤ならではと思うのは、組曲にはない6曲目の「火の鳥の歎願」での悲しげな旋律がとても印象的。10曲目の「王女たちのロンド」は、ロメオとジュリエットの「バルコニーシーン」に相当する場面。この旋律にはロシアのバレー音楽の伝統が強く感じられます。18曲の「カスチェイの部下たちの凶悪な踊り」のリズム感は春の祭典を先取りしたような曲。ラトルはここでも見通しのよい演奏で、一つひとつの音の動きがよく聞き取れます。そういう演奏スタイルゆえに、登場人物の性格付が見事で、バレーを見たことがなくても、それぞれのシーンがイメージでき、聴いていてとても楽しい音楽となっています。
 ゲルギエフと同じくロシア(現ラトビア)出身のマリス・ヤンソンスですが、演奏スタイルはだいぶ異なり、どのような曲でも素直に受け入れられる演奏で、親しみやすさを感じる指揮者です。こちらの「火の鳥」は組曲で、1919年版です。組曲に6曲目がないのは寂しいと書きましたが、聴きどころである「王女たちのロンド」と「カスチェイの部下たちの凶悪な踊り」は入っていますので、火の鳥の面白さは十分楽しめます。ヤンソンスの演奏は流麗さに溢れ、楽器の存在感よりもハーモニーの美しさが勝ります。ラトルが個々の楽器の存在感を示すのに対して、こちらは音楽の流れのなかに各楽器が置かれた感じです。
「カスチェイの凶悪な踊り」では、ラトルの場合、一人一人のダンサーの動きが見えるようですが、ヤンソンスは全員の踊りを見ているようで、よりエキサイティングな演奏。リズム感が強調された、いわゆる乗りの良い演奏で、盛り上げ方が実にうまい。音楽家というより演出家というのが相応しく、高揚感があります。(2022年10月)
ゲルギエフと同じくロシア(現ラトビア)出身のマリス・ヤンソンスですが、演奏スタイルはだいぶ異なり、どのような曲でも素直に受け入れられる演奏で、親しみやすさを感じる指揮者です。こちらの「火の鳥」は組曲で、1919年版です。組曲に6曲目がないのは寂しいと書きましたが、聴きどころである「王女たちのロンド」と「カスチェイの部下たちの凶悪な踊り」は入っていますので、火の鳥の面白さは十分楽しめます。ヤンソンスの演奏は流麗さに溢れ、楽器の存在感よりもハーモニーの美しさが勝ります。ラトルが個々の楽器の存在感を示すのに対して、こちらは音楽の流れのなかに各楽器が置かれた感じです。
「カスチェイの凶悪な踊り」では、ラトルの場合、一人一人のダンサーの動きが見えるようですが、ヤンソンスは全員の踊りを見ているようで、よりエキサイティングな演奏。リズム感が強調された、いわゆる乗りの良い演奏で、盛り上げ方が実にうまい。音楽家というより演出家というのが相応しく、高揚感があります。(2022年10月)