SACD

最近個人的に注目のレーベルは旧Philipsのスタッフが立ち上げたという、オランダのPENTATONEです。オランダといえばPhilips、ConcertgebouやHerrewegheなどを思い浮かべますが、いずれもメジャーなレーベルで、PENTATONEに登場するのは聞いたこともないような演奏家ばかりです。(注、最近HerrewegheはPENTATONEからも出ています)ではなぜPENTATONEかというと、SACDの音のよさです。児玉麻里というピアニストのベートーベンを聞いたときは、まず左手の低音階がはっきりと聞こえるのにびっくりしました。最初がピアノソナタ14番の月光で、3楽章の低音部分など気にしたこともなかったのですが、このSACDを聞くと、まるで楽譜を読んでいるかのようです。この低音がこのピアニスト特有のものなのか、あるいはCDでは単に気づかなかっただけなのか、興味のあるところです。早速、同じ曲(ピアノソナタ8番、悲愴)でブレンデル、ポリーニと比較してみました。

一番ドラマチックに弾いているのがポリーニで、最初の有名な和声と、次の流れるような部分とは普通は楽想が違って聞こえるのですが、ポリーニの場合、その分け目がなく、全体が一つの流れとして構成されているという感じです。肝心の低音ですが、もちろん歌になっています。ただし、それが浮き立つのではなく、和音としての響きの中に埋もれてしまうといったところでしょうか。ブレンデルはスタジオ録音のせいでしょうか、かなりきつい音で、802Dで聞くとかつてのPHILIPSのイメージとはだいぶ違います。打鍵が強いので、よけい高音域が目立つ音になっているのかもしれません。ポリーニよりゆったりしたテンポで、その分テンションの維持が難しいと思いますが、さすがにベートーベンらしいがっちりとした構成を感じさせる演奏です。要するにこの二人の巨匠は、低音域がどうのこうのと言わせない説得力があるということです。

では児玉麻里はどうか。低音域の明確なことはやはり演奏スタイルです。細部まできちんと考え、それを音にしている演奏といえるでしょう。全体を貫く説得力、あるいは構成力は感じられませんが、音の良さと相まって、巨匠の演奏とは違ったベートーベンを楽しめます。このピアノ録音のすばらしさを発見したつもりでいたら、すでにステレオサウンドで紹介している評論家がいました。802Dのところで登場した楢大樹氏で、ワルトシュタインの2楽章から3楽章への移行部の響きが透明で美しい!と絶賛しています。これを含む2枚のSACDを早速ネットで注文しました。
SACDとCDとの違いを一口で言えば、空間表現力です。それはまさにハイエンドオーディオが求めてきた世界であり、特に私がオーディオで重視してきた要素です。空間表現力が最も威力を発揮するのは、何といっても大編成のオーケストラです。ところがこの空間表現という概念はかなり最近になって認識されたものではないかと思います。その証拠として一例を挙げると、ハイティンクがロイヤルコンセルトへボーオーケストラの常任指揮者だった時代の1985年から1987年にかけてデジタル録音したベートーベンの交響曲全集があります。ハイティンクは1964年から1988年まで常任指揮者を勤めていますので、終盤のころの録音です。これを聞くと、オーケストラ全体のバランスは悪くありませんが、第一バイオリンなど、フォルテになると左のスピーカが鳴っているという感じがします。オーディオ用語では、スピーカに音がまとわりつくという表現をしますが、それほどではないにせよ、最近の音離れの良い音を聞きなれた耳にはかなり気になります。
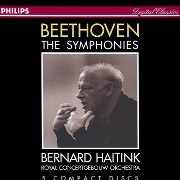

1985年といえば、すでにデジタル化されてから5年位はたっていますし、録音技術は現在と大きな差はないはずで、やはり空間表現という概念が欠落していたためではないかと思います。ハイティンクは、はっとするようなところはありませんが、心に響く音楽をやる人で、これが25年も続いたコンセルトへボーとの総仕上げのCDにしては、少し残念です。この録音年代の後半に交差するように開始された、シャイー指揮、コンセルトへボーによるブルックナーの交響曲全集は、第一バイオリンはハイティンクのベートーベンほど目立たず、ずっと落ち着いたバランスです。全体のクオリティは同じようなレベルですが、空間表現の観点では、より深みを感じさせます。
(後日談)このSACDのページを書いたのは2006年11月ですから、デノンのCDプレーヤでの印象ですし、スピーカのセッティングにしても現在はこの頃と比べると随分と改善されています。もちろん基本的な印象は変わりませんが、大きく訂正しなくてはならないのが、このハイティンクのベートーベンのシンフォニー全集です。ここでは空間表現という概念が欠落していたのではないかと書きましたが、これはまったくの見当違いで、改めて聞き直した結果、むしろ当時としては優れた録音だと思います。何故誤った判断をしたかですが、ここにも書いているように、第一ヴァイオリンが左のスピーカにまとわりつく現象です。確かにトゥッティでそのように聞こえる部分もあり、音量によってヴァイオリンの位置が移動するところがありますが、それは枝葉末節なことで、全体的には奥行きもよく表現されており、現在の優秀録音に比べれば見劣りするものの、当時の標準よりも優れています。先のスピーカにまとわりつくという現象も、むしろスピーカの前面に出てくるという表現が正しいでしょう。装置が良くなると、聞きなじんだCDから新たな発見があるものですが、これもその一例と言えばそうですが、録音技術に比べ、再生側の技術がまだまだ追いついていないと、改めて感じました。その意味では、本ページで紹介したソースも、もう一度全部聞き直す必要がありそうです。(2009年9月)
コンセルトへボーは何故か縁があって2回生で聞いていますが、評判ほど良いホールとは思えません。ステージが高く、客席がちょうど船底のような感じですので、間接音が多く、明瞭さに欠けます。場所の影響もあるでしょうが、あの構造では1階席は似たようなものでしょう。独奏バイオリンがまるで2丁か3丁で引いているように聞こえます。言い換えればブルックナーのシンフォニーには向いていて、金管楽器も間接音が多いのでうるさくなく、深みが出るのではないかと思います。
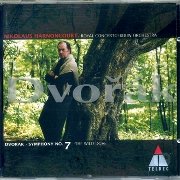
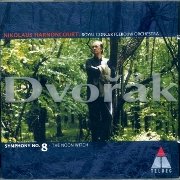



このホールではこれ以上の解像度を求めることは所詮無理かと思いきや、2000年からコンセルトヘボーの客員指揮者となったアーノンクールによる一連のドヴォルザークのシンフォニーの録音は、はるかに良くなっています。低音もぐっと明瞭さを増して、曲の良さと相まって大いに楽しめます。考えてみれば、録音マイクの設置場所はかなり高い所にありますので、その分客席より直接音が多くなり、明瞭になるはずです。客席よりマイクの方が良い条件というのも納得がいきませんが、おいそれとアムステルダムまで通えませんし、CDも楽しんでいるわけですから文句は言えません。アーノンクールのドヴォルザークは写真のようなアルバムがあり、どれも私の好みです。中でも晩年の作品である交響詩集はお勧めです。
ラトルとベルリンフィルも2004年にまったく同じ曲集を出しています。アーノンクールに比べると、オーケストラの音色が明るく、管楽器も鮮やかで、オーケストレーションの楽しさでは間違いなく上です。ただ、私の場合、ドヴォルザークは明るいのより、少し暗いほうがしっくりくるので、アーノンクールの方を良く聴きます。このCDは1997年から2001年に渡って録音されていますので、ブルックナーの録音と入れ替わりという位置づけになります。TELDECというレーベルの違いも大きいのでしょうが、コンセルトへボーの録音はここで大きく飛躍したと思います。
2004年からシャイーを引き継いだのが、現在の常任指揮者のヤンソンスで、すでにSACDが何枚か出ています。アーノンクールの録音からどれだけ進化したか楽しみですが、実はまだ聞いていません。あまり魅力的な曲目がないというのがその理由ですが、いずれこの場でご紹介したいと思っています。

SACDについて書くつもりが、過去のCDの紹介になってしまいました。そこで、今回はこれぞSACDというものを紹介します。まずはコンセルトへボーで、シャイーの指揮によるマーラーの3番です。またまたコンセルトへボーで恐縮ですが、このSACDを聞くと、生よりはるかに良く聞こえます。まずは力強いホルンの後、いきなりバスドラムの強打に圧倒され、つづいて力強い低弦の響きが続きます。この録音の優れているところは、ただ力強いだけでなく、同時にこれらの打楽器や弦楽器が作り出すホールの空気を揺るがすような振動が伝わってくる点です。若干作られた音という感じも否めませんが、ダイナミックさと繊細さをこれほど良く捕らえたオーケストラ録音は少ないでしょう。マーラーとかブルックナーなどの大編成のオーケストラ曲というのは、食傷気味の時も多いのですが、この演奏を聴くと、そんなことはお構いなく、ひたすらマーラーの世界に引き込まれてしまいます。名演奏が録音によってより価値を高めた顕著な例です。

とにかく聞いていてハッピーになるのがこのSACD。シンシナチオーケストラとパーヴォ・ヤルヴィの指揮ですが、残念ながら生で聞いたこともなく、どんなオーケストラなのかよく知りません。このSACDはラベルの管弦楽曲を詰め込んだもので、ダフニスとクロエの第二組曲から始まりますが、映画音楽のような「夜明け」の次は「パントマイム」。ここでは夜明けで本物の鳥のさえずりのように活躍したフルートが今度は独奏で、息使いがリアルに聞こえます。次の「全員のダンス」は、まるで打ち上げ花火のような楽しさ。我が家の狭いスピーカの空間で、あちこちに次々と打ち上げ花火ならぬ、様々な音が飛び跳ねる様は快感です。ラベルのオーケストラ曲というのは、とかく音の面白さはあっても、あまり心に訴えるようなところはないのですが、このSACDを聞くと、そんなことはどうでも良くて、ただひたすら聞いてしまいます。まさにオーディオにお金をつぎ込んだ甲斐があったと実感できるひと時です。

同じくTELARCレーベル、しかもシンシナチオーケストラとヤルヴィのコンビで、プロコフィエフのロミオとジュリエットも楽しめる1枚。ロミオとジュリエットはN響の音楽監督だったシャルル・デュトアの得意な曲で、モントリールシンフォニーと、N響と2枚あります。N響の方は抜粋で、交響曲6番とのカップリング。演奏はシンシナチよりN響の方が上で、このCDを聞くと、N響というのはメジャーレーベルでもまったく引けをとらないどころか、トップレベルのオーケストラであることがよくわかります。しかもDECCAの録音もよく、SACDだから音が良いのではなく、CDでも録音技術が良ければ何ら遜色ないことを実感させてくれます。

パーヴォ・ヤルヴィという指揮者は録音に関心が高いのではないかと勝手に想像していますが、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンを指揮したものも何枚かSACDで出ています。このオケと仲道郁代のピアノとの競演による、ベートーベンピアノコンチェルト(3,5番)は古楽器アンサンブルを思わせる切れの良さと透明感のある響きが両立した心地よい音。

もうひとつ、こんどはパーヴォ・ヤルヴィの父親だそうですが、ネーメ・ヤルヴィ指揮、イェーテボリ交響楽団(スエーデン国立管弦楽団)によるシベリウス交響曲全集。このSACDはスピーカの前方に音の広がりを感じさせる録音で、TELARCが迫力で聞かせるとすれば、こちらは繊細さで聞かせる音。もちろん繊細さだけではなく、ティンパニーの空気を揺るがす様子は遜色ない迫力で聞かせます。弦の流麗さは曲(2番)の特色でもあるのでしょうが、このSACDの際立っているところです。SACDならではと思わせるのは、音を出す直前のわずかな間や、弦のピチカートの弾む音。シベリウスの故郷であるフィンランドと同じく、北欧スエーデンのオケだからというこじつけではなく(実際、隣国でもまったく違う国なのはアジアを見れば明らか)、シベリウスの楽曲にぴったりのオーケストラサウンドと思います。
(注)SACDの紹介ということで、あえて取り上げませんでしたが、シベリウスで個人的に好きなのは、オラモ指揮、バーミンガム市シンフォニーオーケストラの全集です。イギリスのオケですが、こちらの方がより透明感あふれるオーケストラサウンドで、初めて聴くと馴染みにくい後期のシンフォニーも素直に心に響いてきます。(2008年5月追記)

いささか音に偏ったので、心に残る演奏を1枚。エッシェンバッハとフィラデルフィアオーケストラのライブ録音で、バルトークのオーケストラのための協奏曲。このSACDは第二次世界大戦で犠牲になった3人の作曲家への鎮魂歌であると、エッシェンバッハによるメッセージがあり、ボフスラフ・マルチヌーのリディツェへの追悼、およびギデオン・クラインの弦楽のためのパルティータとの3部構成になっています。マルチヌーという作曲家は、その死後に彼の祖国(チェコ)でその業績が認められたそうですが、この作品はナチスドイツによって抹殺されたリディツェへの追悼と題された曲。もう一人のギデオン・クラインはナチの強制収容所でわずか26歳の悲惨な生涯を終えた作曲家の作品。これらの重苦しい曲の後で演奏されるバルトークも、こんな悲痛な曲だったのかと思い知らされる演奏です。エッシェンバッハは知的な演奏スタイルですが、この演奏会は思い入れが強いようで、曲の持つ悲劇性を引き立てています。このオケの活動拠点のVerizonホール(未だ行ったことがありません)でのライブですが、音響の良さが感じ取れるホールです。(2006年11月)