ディスク
オーディオ装置をアップグレードすると、まずスケール感に圧倒され、オーケストラに目が行きます。私も例外ではなく、システム導入当時はSACDなどの新しい優秀録音盤を買い求めていました。システムを更新したのは2006年ですが、その頃はSACDがようやく市場に出回り始めた頃で、試聴会などでもSACDが盛んに使われていました。それから3年で早くもSACDから撤退する企業が増えてきたことは市場経済の故とはいえ、いかにも商業主義という感じがしてなりません。ましてやSACDの開発元であるソニーがBlue-Spec CDなるものを売り出し、その高音質を宣伝するという姿勢は、ユーザ無視といわざるを得ないでしょう。それはともかく、当時はようやくSACDが再生できるプレーヤを入手したこと、CDに比べて刺激のない、非常に聴きやすい音がしたこともあり、当時購入したいくつかのSACDについて紹介しました。
あれから丸3年、そしてSACDプレーヤ交換から2年、ようやく落ち着いてくると、SACDなどの新しい優秀録音を追うことより、かつて購入したものの、音が悪かったり馴染みにい曲だったりして、お蔵入りになっていたCDを引っ張り出して、聴くことが多くなりました。我が家のシステムはどちらかといえば、ヴァイオリンなどは苦手なジャンルで、切れの良い音はピアノを含む打楽器に向いています。確かにダイナミックレンジの大きさなど、オーディオの醍醐味を味わわせてくれるのはオーケストラであり、圧倒的な音はそれ自体が快感です。しかし、クラシック音楽を楽しむにはやはり弦楽器、特にヴァイオリンの再生が重要な要素となります。ヴァイオリンの再生はオーケストラでももちろん気になる部分ですが、名曲の宝庫であるヴァイオリンソナタや弦楽四重奏はともすればきつい音になりがちで、弦を擦る生々しい音を損なわず、その上で心地よい響きを再現することはオーディオの最も困難なテーマでしょう。
もう2年近く前になりますが、CDプレーヤX-01 D2導入時の刺激的な音に悩んでいた頃を思い出すと、この装置でヴァイオリンがここまで楽しめるようになることなど、想像もできませんでした。

ヴァイオリンの再生に注目するようになったきっかけは、最近システムの音決めのソースとして活躍しているアーノンクールのシューベルトで、このHPで再三登場するCDです。このCDを最初聴いたときは、ヴァイオリンはシャリシャリで全体に音が薄く、とても鑑賞に耐えないものでした。ケーブルのページでラインケーブルをCaldasからAudioquestに変えたことを報告しましたが、このCDを再生すると、Coloradoは少しハイ上がりの印象で、Caldasの方が落ち着きます。Caldasの特徴はなんと言っても高域が穏やかなこと。それに低音の豊かさが加わるので、よけいそのように感じます。このケーブルは一聴、物足りないのですが、しばらく聴き続けるとその良さがわかってきます。もっともこれは比較試聴の常で、メリハリの利いた音のほうが良く思えるということは良くあります。といっても、その差はごくわずか。ピアノなどはむしろColoradoの方が明快で良いと思えることもあり、そのうち再登場ということになるかもしれません。
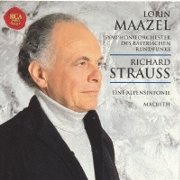
オーケストラ物で、どうしてもうまく鳴らないCDがもう一つあります。それはマゼール指揮、バイエルン放送管弦楽団による、リヒャルトシュトラウスの管弦楽集。このCD(4枚組み)の特徴はダイナミックレンジが狭いことで、金管の音がまるでリミッターがかけられたかのように物足りなく、リヒャルトシュトラウスらしい、圧倒的な管弦楽の迫力が楽しめないことです。何度か再生するうちに耳の方がなじんでくることもままありますが、こればっかりはあきらめざるを得ない状況です。我慢して聴くこともないのですが、過去に購入したソースで聴くに耐えないものがほとんどなくなった今、これだけが残っているというのも気になります。
もっとも、そのようなCDにこだわる事が無意味と思えるようなすばらしい録音のリヒャルトシュトラウスが最近多く出回っています。代表的なものをあげると、ラトル、ベルリンフィルの英雄の生涯、ビリー、ウイーン放送交響楽団のドンファン&イタリアより、最近出たヤンソンス、コンセルトヘボウのアルプス交響曲。ラトルのは普通のCD、あとの二つはいずれもSACDですが、どれもすばらしい録音で、このようなCDがどんどん出てくると、過去の鳴らないCDこだわっていることがばからしく思えてきます。
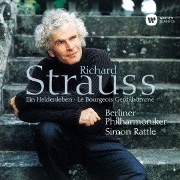


上記は2009年4月に記載した「ヴァイオリンの音」の前半部分を転記したものですが、その後イコライザーDG-48を導入し、マゼールのR.シュトラウスのCDを聴きなおしました。その結果、予想通りかなり改善され、少なくとも聴くに耐えないというレベルではなくなりました。イコライザーと言えども、ダイナミックレンジの改善にはならないのではないかと思われましたが、以前は高域に埋もれがちだった低域が持ち上がってバランスが良くなり、管楽器群がダイナミックにぐっと迫ってくるようになりました。

このマゼールのCDは比較的新しい録音(1998年)ですが、これとほぼ同時期の2000年に録音されたティーレマン、ウィーンフィルの同曲を比較すると、冒頭の夜から日の出でを聴くだけで、演奏者の熱気が伝わってくるような躍動感に圧倒されます。これを聴いてしまうと、マゼールのも聴けるようになったとはいえ、音楽自体が平板で、盛り上がりに欠けます。これは果たして演奏の違いなのか、録音なのか。ともあれ、感動的なのは録音が良いからであるはずはなく、やはり演奏の違いと捕らえるのが正しいでしょう。さらに言えば、DISCは録音も含めた総合芸術であり、仮に実演が優れたものでも、それが録音やオーディオ装置のためにつまらなく聴こえたら、それはあまりにおおきな損失です。
オーディオは音源であるソースを抜きにして語るわけにはいきません。このホームページでも音のことを書いていますが、実は特定のソースがどのように聞こえたかということを書いているに過ぎません。つまり、オーディオにおいてはDISCはその違いを聞き取るためのツールであり、その目的には聞き馴染んだDSICでないと使えません。上記はその一例ですが、うまく鳴ってくれないCDがどの程度改善されたのか、オーディオに手を加えた結果、気になる部分がどのように聞こえるか、といったことの確認のために特定のソースを使うわけです。
一方で、すでに1000枚を超えるCDがあるにもかかわらず新録音を買い求めるのは、オーディオのためではなく、心に響く音楽を聴きたいという欲求からであることも明らかです。こうなると話はまったく逆転して、良い音楽を良い音で聞くためのオーディオということになり、極めて健全なアプローチです。現実はこの両方のアプローチを行ったり来たりして、相互に切磋琢磨しているというところでしょうか。最近オーディオ再生のテーマとして注目しているヴァイオリンも、それらの曲をできるだけ弦楽器らしい、響きの良い音で聴きたいという要求からであることは言うまでもありません。
オーディオをやり始めた頃からずーと思っていたことは、果たしてオーディオはソースのクオリティの差を越えられるのかということです。つまり、オーディオのグレードを良くしても、結局はソースのばらつきの方が大きく、どんなソースでも良い音で再生することは不可能ではないかと思っていました。本格的なオーディオ装置を持つに至り、その思いは依然としてありますが、現時点でいえることは、どんなソースでもそれなりに鳴らすことはできるということです。これは当たり前のように思えますが、すくなくとも音が悪いからこのDISCは聴きたくないというものは無くなりました。これは大きな進歩で、ソースのばらつきは越えられないが、努力すればそれなりに十分音楽を楽しめるレベルで鳴らすことができる、というのが答えではないでしょうか。
このコーナーは良い音で聴くために、オーディオの試行錯誤を行ってきた過程で登場したDSICを紹介するものですが、同じDISCでもオーディオが進化すればその印象は大きく異なってきます。かつて購入したものの、もう一度聞いてみようという気になれず、CDラックに置かれたままだったCDが実はこんなに面白い曲だったのかと再発見することはよくあります。言い換えれば、それだけDISCの印象はオーディオによって左右されるということです。そのため、ここで記載したことも普遍的なものではなく、オーディオシステムあるいは自身の未熟さのために、そのときの判断が間違っていたということもままあります。(2009年11月)