復刻版SACD
オーディオに興味を持ってからすでに50年。当然、アナログレコードの時代から続いている趣味ですが、約300枚所有していたアナログレコードは2001年に全て売却してしまいました。それらのアナログレコードを集め始めたのは1960年代からですので、たとえばカール・リヒターのバッハの受難曲や管弦楽曲、バックハウスのベートーヴェンのピアノソナタ、比較的新しいところではグールドのバッハといったコレクションです。まさに青春時代から聞き馴染んだレコードも多くあるのですが、CD時代になって、そういった過去の録音を買い直すということはめったにありません。理由は、そういった昔の演奏より、現代の演奏の方が面白く、また音質もはるかに優れているからです。
ところが最近になって、こういった昔の名演奏と言われるレコードの復刻版が、それもSACDとして発売されることが多くなりました。当然、そういうものを買う人がいるということなのですが、これはオーディオマニアが高齢化していきていて、過去の名演奏をもう一度聞いてみたいというニーズが多いということの表れだと思います。
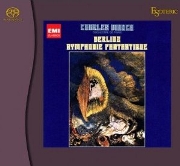
そういった過去の名盤と言われたレコードの復刻版で、地道な作業を続けているのが、エソテリックです。発売されたSACDには当時名盤と言われたものが多いのですが、中には私がアナログレコードで所有していたものもかなりあります。たとえば、シャルル・ミュンシュ、パリ管のベルリオーズの幻想交響曲、カラヤンのワーグナーの管弦楽集や新ウィーン楽派の管弦楽集、グルダ、アーノンクールのモーツアルトのピアノ協奏曲23、26番、オイストラフ、セルのブラームスのヴァイオリン協奏曲など。これらを持ち続けていれば、今ではプレミア物としてもっと高く売れたかも知れません。とはいえ、アナログレコードを保有しているのはごく少数の、それも高齢のマニアですから、そういったレコードはすでに持っているはず。手間をかけるのはオーディオに限らず、趣味の世界では共通の楽しみですが、現在、レコード・プレーヤをCDに対抗できるレベルに維持するには膨大な費用がかかり、私の場合にはそこまでの愛着はありません。
アナログレコードで所有していたものを買い直すことはめったにないとはいえ、やはり個人的な思い出と結びついた演奏や曲というのは当然あります。今でこそ、オーケストラを満足できる音量で再生できる環境にありますが、当時は子育ての最中で、とてもそんなことは望めません。そこで、聞く音楽も室内楽や器楽曲が主となり、アナログレコードのコレクションも半分以上がピアノだったように思います。

これは誰もが知っているリヒテルのバッハの平均律ピアノ全集です。このアナログレコードは一巻と二巻に分かれて豪華な装丁のケースに入っており、それぞれが3枚組みだったと記憶しています。1970〜73年の録音ですが、当時としては決して悪くなく、それ以上に、バッハの平均律がこんなに美しく、感動的な音楽であることを教えられた演奏です。当時から話題となったレコードですので、その後CDとして再発売され、私も再度聞きたくて購入しました。
ところがこれが曲者で、アナログレコードの音とは大違いで、音像がぼやけているだけでなく、まるで品のない、録音レベルが大きいだけの音でした。アナログ録音をCD化した音質が良くないのは、たとえば、マリナーのハイドンのネイム・シンフォニー集も同じです。残念ながらアナログレコードを持っていないので、直接比較ができないのですが、このCDはイコライザーの設定がおかしいのではないかと思えるほどハイ上がりのバランスで、ヴァイオリンがやたらと耳につきます。結局、リヒテルのCDは聞くに堪えず、ほとんど聞かずに売却してしまったのですが、昨年、今度はSACDで発売されました。売却した矢先に同じものを買うのはいかにももったいないのですが、アナログ録音の音が再現されているとの口コミを頼りに購入しました。
さて、このSACD化されたリヒテルの平均律、CDとは全く違い、アナログレコードで聞いたあの感動がよみがえってきました。録音も非常に残響が多いとはいえ、ピアノの音そのものは明快で、当時としては決して悪くありません。それがSACDで見事に再現されたのみならず、第二巻はスタジオ録音と思っていたのですが、いくつかはクレハイム宮殿で録音されたのがはっきりと聞き取れ、そういう意味ではアナログレコード(もちろん当時のプアな再生装置との比較ですが)以上の出来と思います。先のエソテリックの場合もそうですが、SACDだから音が良いのではなく、SACD化する限りは、音源に何を使うかも含めて、出来るだけ良い条件で製作しようという、プロデュース側の思い入れの違いによるものと思われます。それに比べて、単に商業ベースでアナログ録音をCD化した製品はあまりにお粗末で、オーディオマニアの存在を無視した行為と思わざるを得ません。もちろん、中には良心的なものもあるのでしょうが、一部の粗悪品が全体の印象を悪くするのは困ったものです。

これも思い出の一枚ですが、ホロヴィッツのクライスレリアーナ。ただし、これはSACDではなく、通常のCDです。アナログ音源をDSD処理しているので、何故SACDにしないのかわかりませんが、音は悪くありません。もともとニューヨークの30番街スタジオでの録音なので、ホール録音に比べて直接音が強いのですが、CD特有のささくれ立った、いわゆる角の立つ音質です。現在のCDの音はもっとまろやかですが、アナログレコードも強い打鍵が印象に残っていますので、これは当時の録音の特徴ではないかと思います。
アナログレコードは、クララ・ヴィークの主題による変奏曲とクライスレリアーナのカップリングでしたが、このCDはさらに子供の情景が入っています。クライスレリアーナは1969年の録音、子供の情景はカーネギーホールでカムバック演奏をした1965年より前の1962年の録音です。演奏はいわゆるヴィルトゥーゾという感じで、当時、19世紀からの生き残りと言われたように記憶しています。今ではこんなに多彩なディナーミクやアゴーギクを効かすピアニストはいません。ただし、それが不快になるのではなく、シューマンの幻想的な音楽とマッチしているところが素晴らしく、こんなに心がうきうきする演奏はめったにありません。ただ、子供の情景は、そういうところが耳障りで、あまり好みません。ホロヴィッツのヴィルトゥーゾらしさは、やはりスケールの大きな曲で発揮されるようで、子供の情景はもっと親しみやすい素直な演奏の方がしっくりきます。
アナログレコードの復刻版で外すわけにいかないのが、グールドです。なかでもデビュー作のバッハゴールドベルク変奏曲は1955年のモノラル録音と、1981年のデジタル録音がありますが、もちろん保有していたアナログレコードは前者のモノラル。グールドは今でも人気があり、それこそデジタル化の格好の材料と思っていたら、2000年のゴールドベルク変奏曲を始め、2012年には平均律、パルティータ、イギリス組曲、フランス組曲と、このところSACDが急に増えつつあります。

これは1981年のデジタル録音の方ですが、2000年にSACDで再発されたものです。デジタル録音なのに何故SACDかというと、デジタル・マスターと並行して収録されていたアナログ・マスター素材から編集用のスコアをもとに再編集し、DSD化した音源をそのままSACDハイブリッド化したとのこと。「アナログ完成期ならではの、のびやかで安定感のある音楽的なサウンドは、グールドの超絶的に美しいピアノ・サウンドを再現」とはSONYの宣伝文句ですが、オリジナルのCDとの比較はしていないので、真偽のほどはわかりません。
久々に聞いたグールドのゴールドベルク変奏曲ですが、まず最初のアリアの遅さ。思わず次の音はまだかと思ってしまいます。SONYの言う「超絶的に美しい」ということはありませんが、音もスタジオ録音らしい明快な音で、かつ一つ一つの音に力感があり、スタッカートが効果的です。そういえば、最初のゴールドベルク変奏曲が発売された時、グールドが初めてピアノで弾くことを可能にしたという評がありましたが、あれはこのスタッカート奏法を踏まえてのことだったように記憶しています。同じスタジオ録音と言っても、最近のピアノの録音はもっと響きを取り入れていて、ずっとまろやかに響きます。その点では先のホロヴィッツも同様で、きつく聞こえたのは、現代のピアノ録慣れてしまったせいかもしれません。
このSACDを聴いて改めて思ったのは、このグールド節ともいえる独特の演奏はそれなりのテクニックがあってこそ、実現できたということです。たとえば第3変奏や第9変奏など、下声部を担当する左手がとても雄弁で、同じ人が弾いているとは思えません。その左手が、第13変奏や第15変奏になると、今度はあたかも通奏低音のように、重みと長さを持って響いてきます。こうした音色の違いは、まずこうあるべきという思考がなければできないことであり、それを具現化する努力の積み重ねが、見かけの虚飾を超えた説得力をもたらすのではないでしょうか。
グールドの演奏は、極端なテンポの設定や、独自の装飾音符など、あえて異端と思わせるところがありますが、とにかく聞いて楽しくなる音楽です。もちろんバッハも良いのですが、この聞いていて楽しい演奏の最右翼はモーツアルトです。あんまり面白くて、アナログレコードは5枚セットで所有していました。そのモーツアルトもCDで出ていますが、ここはできるだけ良い条件でデジタル化されたものを聴きたいところです。
そんなニーズを感じてか、SONYからオリジナル・アナログ・マルチトラック・マスターを使ったSACDが今月の15日に発売されました。その中には、モーツアルトに加えて、これまた感動もののブラームスの間奏曲集もあります。国内版なので、当面値下げは期待できず、いつ買えるかわかりませんが、今から楽しみです。(本稿続く 2014年1月)
グールド再び
かつてのグールドの一連のレコードがSACDで発売されたのは2014年ですが、その時にモーツアルト全集については、割引となるのを待つと書いています。しかし、実際にはすぐ値下げとなったようで、その2014年の8月には購入していました。それ以来すでに7年近くなるわけですが、2018年の電源工事のレポートにその音ついて触れています。確かに音は良くなったのですが、かつてのような新鮮さは感じられず、今日に至ったという次第です。とはいえ、グールド以降にアファナシェフ、プレトニョフ、それからファジル・サイなど、多くの"一風変わった"モーツアルトも多く聞かれるようになり、改めてグールドについて記録しておくのも良いかと思いました。
吉田秀和はプレトニョフのモーツアルトについて、「こうまで技巧的に弾くのも、この名手がモーツアルトの音楽は楽譜に書いてある通りに弾いているのではあんまり淡白すぎて、聞き手が退屈してしまうのではないかと心配しているからではないかと思ってしまうのです」と書いています。ファジル・サイが装飾音を多用しているのも、そういうことの表れではないかと思いますが、プレトニョフの場合、かなり気になるくらいアゴーギクを多用しているものの、旋律はいわゆる球を転がすような美しい音で弾いていますので、従来のモーツアルトのイメージを壊すものではありません。しかし、グールドは彼らとは違い、いわゆる「心地よい」と感じさせる要素はすべて取り除いて、というよりも、そういう余地を与えないよう、速く弾いたり、バッハのようにアルページョや和音をスタッカート奏法で浮きたつようにしたり、モーツアルトの音楽の「サロン的なもの」を否定することに意義を見出すような演奏です。平たく言えば、プレトニョフはBGMになるが、グールドのモーツアルトはBGMには使えないということです。
再発されたSACDのパンフレットにはグールドとブリューノ・モンサンジョン(音楽家・映像作家)との対談があります。話の内容はとても難解で、理解できない部分が多いのですが、その中で本人はモーツアルトの音楽、特に後期の作品に共感できないと言っています。とはいえ、改めて聴いてみると、モーツアルトへの共感なしには二つの幻想曲、あるいは多くのソナタの第二楽章を、あのように劇的かつ情緒的には弾けないでしょう。ただ、グールド自身は、モーツアルトの音楽に情緒的なものを持ち込むことは避けている、つまり(ショパンの音楽のように)主旋律やハーモニーを浮きあがらせて聞き手の感情に訴えるのではなく、ひたすら、ポリフォニー的な音の動きを追い求めて、それらの入り組んだ音の流れを明示することに専念しているように思えます。従って、伴奏のような部分が主旋律に聞こえたりして、それがいわゆる洗練されたモーツアルトに聞こえない理由と思います。そのような試みをどう捉えるかは、結局、聞き手次第ということなのではないでしょうか。
今回聞き直してみて面白さを発見したのがK284で、この曲はグールドもお気に入りと言っていますが、特に第三楽章は変化に富んだ変奏曲で構成されているのですが、それぞれの曲想の変化がテンポの変化と相まってとても印象深く、それでいてごく自然な音楽を形成しています。あのトルコ行進曲で有名なK331も、最後の変奏に向かってテンポあげていくという、変奏曲の構成に関する”実験的”なアプローチとしてとらえると、グールドの意図も少しは理解できるように思います。グールドのモーツアルトの特徴はいろいろやっているにもかかわらず、わざとらしさがないことです。変わったモーツアルトの雄である、アファナシェフの幻想曲(K457)はグールドよりさらに遅いだけでなく、重くて暗いのですが、まるでベートヴェンのような深遠な音楽をやっているという”わざとらしさ”を感じてしまうのです。
また、K.330ですが、このSACDにはボーナス・トラックとして、1958年の最初の録音が収録されていて、1970年の再録音との比較ができます。1958年の録音では1楽章は非常にゆっくりというより、軽快なテンポで弾いていて、退屈とは言わずとも、穏やかな音楽。一方、1970年の再録音では、他のソナタと同様、とても速いテンポで弾いていますが、同時にデュナーミクの変化が大きく、緊張感をもたらすとともに、劇的な音楽となっています。
全曲通して聴いてみて、もちろんすべての演奏が面白いわけではありません。単調さを吹き飛ばすためのスピードなのかと頭では理解しても、K310、K311などは速すぎて、いかにもせわしない感じがします。この時期の作品は、モーツアルトのピアノソナタの一つの頂点を形成する作品と言われていますが、残念ながらCD-2に収録された作品は、K331以外、総じてあまり良い出来とは思えません。一方で、K332以降(CD-3、4に収録された作品)はグールド節も絶好調のようで、いわゆるノリの良い演奏。テンポも何故かK332以降は極端に速くなく、K457の第二楽章など、まるで幻想曲のような趣です。美しいモーツアルトではないかもしれないけれど、思わず引き込まれる説得力があります。その点ではK570、そしてK576も聴いていて楽しいモーツアルトです。
グールドのモーツアルトにどっぷりと浸かった一方、「普通のモーツアルト」を聴きたくなって、ピリスのK310を引っ張り出したのですが、実にニュアンス豊かで、普通に(ピリスは普通のピアニストではないかもしれませんが)弾いても、十分劇的な音楽ですが、ベートヴェンの激しさとは違う、もっと聞き手に寄り添う音楽です。さりとて今風の癒しとは違い、軽薄すぎず、哲学的と言うほど重くなく、音楽を聴いていながら音楽から離れて人生に思いを巡らすような、そんな気持ちにさせる演奏です。これが正統なのでしょうけど、グールドもまた聴いてみようと思う時が必ず巡ってくるような気がします。(2021年4月)