2013-2014 N響定期公演
2013年9月 定期演奏会
昨年まで続けた二階席は2010年からですから、すでに丸3年となります。二階席といっても前から2列目で、ホール全体の響きを聞ける良い席でしたが、オーディオマニアとしてはやや物足りない思いがあり、今年は一階席に変更してみることにしました。一度会員になると、席替えは新規入会より優先してくれるとはいうものの、思うような席が確保できないのは、すでに2010年の席替えで経験済みです。そういうリスクがあるとはいえ、違った席で聞いてみたいという気持ちが勝り、7/15の電話受付にチャレンジしました。案の定、電話がつながったのは開始時間の10時から45分経過した時で、タイミングの差はあれど、2010年より遅れること15分でした。その時点ではすでに真ん中の列はなく、左側の列の前から6列目の通路から2番目という、まあ妥協できる席となりました。サントリーホールで行われるBプロはN響の定期公演の中でも人気が高いらしく、メンバーが固定されていて、ウィーン・フィルの死ぬまでと言われるほど極端ではないにしても、一度良い席を確保すると、それを手放すことはほとんどないのではないかと思います。
そんな経緯で迎えた2013年度の最初の定期公演は9月11日で、厳しかった暑さがようやく緩んできた頃とはいえ、まだ演奏会の雰囲気ではありません。今月はおなじみのブロムシュテットで、ブラームスの大学祝典序曲、ハイドンの主題による変奏曲、休憩を挟んで、交響曲第1番というプログラム。ちなみに、今月はAプロが交響曲
第1番、第2番、Cプロが第4番で、ブラームスの交響曲チクルスという定期公演です。
さて、新しい1階席の音ですが、まず感じたのは弦楽器群のそれぞれの音が良く聞こえること。当然予想された違いですが、2階席はオーケストラ全体を俯瞰するような印象があるのに対して、今度はオーケストラの中に頭を突っ込んだような感じです。当夜はいわゆる古典的配置で、第一ヴァイオリンが左右に展開し、右側からヴィオラ、チェロ、コントラバスと並び、左の第一ヴァイオリンの奥がコントラバスとなります。で、以前はどうだったのかと読み返してみたら、ブロムシュテットは2010年4月が最後で、私が聞いたのは実に3年ぶりですが、その時の配置も同じでしたので、これは彼の趣向であることは間違いありません。各楽器が良く聞こえたのは、そのためもあると思いますが、やはり席による違いが大きく、二階席ではあまり聞こえないヴィオラの音が良く聴き取れます。一方で、管楽器や打楽器は音は良く聞こえるけれども姿が見えません。音が聞こえれば良いではないかと思われますが、やはり視覚的要素は重要で、その点では思わず音のありかを探したりしてしまいます。今度の席は、あたかも楽譜を読むように、音楽を分析的に聞くには良いものの、一方で、二階席でのオーケストラ全体の響きを楽しむ聞き方も悪くないなと、改めて思いました。
肝心のブロムシュテットのブラームスですが、ブルックナーの指揮などから予想される通り、ドイツ音楽の伝統に従った分厚いオーケストラの音を基調としつつも、現代の方向である、各パートの動きも良くわかる音作りです。そういったスタイルは、少なくとも第1番持つ、形式的かつ重厚な音楽にはぴったりでした。ただ、個人的には当夜は夏の疲れがでたためか、久々に眠気に襲われ、あまり楽しめなかったことを付け加えておきます。(2013年9月)
2013年10月 定期演奏会
ようやく本格的な音楽シーズン到来という季節ですが、当夜はあの厳しかった夏を思い出すような暑い日でした。とはいえ、先月の眠気はやはり夏バテのせいだったようで、今回は体調も良く、久々に楽しめる演奏会となりました。
10月のプログラムはロジャー・ノリントンのベートーヴェンシリーズで、グルックの歌劇「アウリスのイフィゲニア」序曲、ピアノ協奏曲 第2番、休憩をはさんで、交響曲
第6番。ベートーヴェンのピアノコンチェルトといえば、昨年4月の河村尚子の第4番の素晴らしさを思い出しますが、当夜はやや期待外れ。ピアニストはロバート・レヴィンという、米国生まれの人で、まず感じたのは音の多さ。音が多いというのは、言い換えれば楽譜に書かれた音をすべて出しているということですが、それが音楽として良いかは別問題で、むしろチェンバロを弾いているかのようにせわしなく、ガサガサと聞こえてきます。後でパンフレットを見たら、この人はフォルテピアノ奏者として評価が高いそうで、モダンピアノでも和声を重視するより、一つ一つの音を聴かせるスタイルにはそういう背景もあるのかなと思った次第。
オーケストラの配置は昨年の4番と同様、中心に向かって放射線状に配置し、その中心にピアノと指揮者がいるというもの。ただし、昨年との違いは、ピアノの向きが逆、つまりピアニストは聴衆に背中を向けるのではなく、顔を向けて演奏することになります。このあたりは研究熱心なノリントンらしいところです。昨年とは座席が違うので、単純に比較はできませんが、どうもこちらの方が音がこもった感じがします。そのあたりの違いもピアノがガサガサと聞こえた一因かもしれません。そういう表面的なことに加えて、一番の不満はベートーヴェン特有のいわゆる「ため」がないことです。第2番は第1番同様、ベートーヴェンらしい力強さと、若々しさに満ちた曲なのですが、その肝心のところが聞こえてこないのが、何とももどかしいところでした。
当夜のハイライトは、第6番の田園です。さすがのノリントンも寄る年波には勝てないのか、かつての遊び心は表に出さず、音楽自体にその心を反映するようになったのではないかと思います。古楽器の専門家らしく、奏法はヴィブラートをかけない、いわゆる古楽器的奏法ですが、まったく違和感がないどころか、むしろこの方が音楽がストレートに響く印象です。もっとも最近は、オーケストラ全体の響きより、内声部が良く聞こえる演奏が主流になっていることも、耳に馴染みやすい一因と思われます。この田園、ベートーヴェンにしては珍しくテーマ音楽で、たとえば嵐の表現など、音楽で自然を表現するということに挑戦した、当時としては画期的な作品だったのではないかと想像します。(当夜の曲目解説によれば、自然の音楽的描写の先駆となる作品は、当時すでに存在していたらしい)
嵐の音楽表現といえば、リヒャルト・シュトラウスのアルプス交響曲を思い出しますが、オーケストラを駆使して自然を描画するという点ではさらに上を行く作品と思います。ただ、ベートーヴェンらしいのは、この作品は単なる風景描写ではなく、風景から得られる心情の描写であるというところです。その意図は嵐が去って、雨上がりのうきうきした気持ちが表れる終章で、はっきりと認識できるのですが、ノリントンの音楽はそのあたりが実によく表現されていて、第9の苦悩から歓喜へという流れが、実はこの田園が伏線となっているのではないかと思った次第。ノリントンの演奏で、そんなことを考えさせられるとは思いもよらないことで、久々に実りのある演奏会でした。(2013年10月)
2013年11月 定期演奏会
11月はトゥガン・ソヒエフという、ロシア出身の指揮者。1977年生まれというから、すでに36歳ですが、N響に登場する指揮者としては間違いなく若手です。この人はフランスのトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団とベルリン・ドイツ交響楽団の音楽監督を務めているそうですが、私にとってはCDも含めて初めて聞く指揮者です。プロフィールはともあれ、当夜の演奏は素晴らしい出来で、この指揮者の欧米での評価が高いというのも納得できました。
ロシア出身、かつN響の定期講演に初登場(2008年に客演している)ということを考えてか、演奏曲目はリャードフ(ロシアの作曲家)の交響詩「魔の湖」、ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲
第2番、休憩をはさんで、チャイコフスキーの交響曲 第5番という、全てロシア物。ちなみにNHKホールのプログラムCもラフマニノフとプロコフィエフですから今回は徹底してます。リャードフはリムスキー・コルサコフを師とした時代の作曲家だそうですが、まったく馴染みがありません。この交響詩は幻想的、かつ響きの美しい曲で、曲自体は良いのですが、コンサートの最初の曲目というより、アンコールに適した曲という印象でした。
ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲の独奏は諏訪内晶子で、私にとっては、2008年のNHK音楽祭以来です。ショスタコーヴィチのヴァイオリン・コンチェルトといえば、第1番が有名で、第2番を演奏会で取り上げるのは珍しい。第1番は私も好きな曲で、CDも4種類くらい保有していますが、第2番を聞くのは初めてです。第1番も最初の印象はつまらなかったのですが、この第2番はもっとつまらない、つまり一回くらい聞いてすぐ楽しめるような曲ではありません。従い、諏訪内晶子のヴァイオリンについてコメントできるような状況ではないのですが、この曲は全楽章に登場するカデンツァが聞きもので、しかも演奏が難しいらしく、独奏者には珍しく、楽譜を見ながらやってました。
2008年のNHK音楽祭は、ヴァイオリンをテーマにした年だったのですが、ちょうどこのHPで「ヴァイオリンの音」という記事を書いていた頃で、そういう背景もあり、サラ・チャン、諏訪内晶子、そして庄司紗矢香の3人のヴァイオリンを聞き比べました。この時の諏訪内晶子はシベリウスのコンチェルトを演奏したのですが、その音楽祭で、あのダイナミックなサラ・チャンのヴァイオリンを聞いた後だったこともあり、いかにも日本人の演奏という、線の細い感じがしたものです。(その後、NHKの放送を聴く機会があったのですが、生よりヴァイオリンの音がはるかに大きく聞こえ、録音では本当のところはわからないものだと思ったものです)今回はそのサラ・チャンを上回るくらい力のこもった演奏で、NHKホールとサントリーホールの違いはあるものの、ヴァイオリン一丁の音とは思えないくらい音量豊かな演奏でした。
チャイコフスキーの交響曲第5番は親しみ易い曲で、しかも聞き映えのする音楽。リャードフの交響詩で感じた、響きを重視する姿勢はこの曲でも同様で、それが曲本来の持つドラマチックなイメージとよくマッチしています。たとえば、第1楽章の最後で、コントラバスがディミヌエンドしていく部分、あるいは第4楽章の初めに第一楽章の主題を管楽器がクレッシェンドしていく部分など、単に音を弱めたり強めたりでするだけでなく、そこにも表情を込めていくなど、細部までおろそかにしない姿勢がよくわかりました。チャイコフスキーの音楽は、その甘美な旋律ゆえに、ともすれば通俗的な音楽になりがちで、まるでNHKの大河ドラマのテーマ曲を聴いているかのようです。ただ、ソヒエフの指揮は、細部まで神経の行き届いた緻密な演奏で、その濃厚な味わいの故に、チャイコフスキーの持つロシア民族的というか、泥臭いところが強く感じられました。その指揮ぶりと相まって、あたかもモスクワ音楽院とかサントペテルブルク音楽院(もちろん行ったことはありませんが)などの壇上で演奏されているかと錯覚させられるような印象でした。(2013年11月)
2013年12月 定期演奏会
12月は恒例のシャルル・デュトア。シャルル・デュトアはここ数年、まともに聞いた記憶がないので、以前の記録を調べたところ、昨年は出張で欠席、その前年の2011年は海外出張から帰った日で、疲れきった状態での演奏会と、どうもスケジュールが合いません。それで、今回はどうかというと、これまた約2週間にわたる入院生活から自宅に戻った翌日と、よくもこれだけ悪条件が続いたものだとあきれるほどです。そんなわけで、今年も評を書くには体調が万全ではないものの、これまで感じていたシャルル・デュトアの音楽というものを再確認することになり、どれだけ楽しめたかは別にして、印象というのは条件で変わるものではないということを学んだ一夜となりました。
前置きが長くなりましたが、12月の曲目はラヴェルのクープランの墓、デュティユーのチェロ協奏曲、休憩を挟んで、ベートーヴェンの交響曲第7番。ラヴェルの音楽は、いつも馴染むまで時間がかかるのですが、この人のラヴェルはそういうことがなく、最初からラヴェルの世界に引き込まれます。ラヴェルの音楽は音の遊びというイメージが強かったのですが、実は非常に知的な音楽であることを再認識したことは以前に書きましたが、そういう個人的背景は別にして、最初から違和感のない音楽として聞こえるというのは、やはりこの指揮者の能力でしょう。
デュティユーという作曲家は1916に生まれ、今年の5月に亡くなった、フランス出身の作曲家。まったく未知の人ですが、このチェロ協奏曲に関しては、表題の「遥かなる遠い世界」が示す通り、抒情的で静かな音楽。第3楽章で、盛り上がる部分があるものの、全体を通して詩的な雰囲気に包まれた作品です。ただし、その抒情的な旋律があまりに長く続くので、聞いている方は退屈してしまいます。冒頭記載した体調が万全でないこともあり、すっかり眠気にやられてしまいました。そんなわけで、チェロの独奏者はゴーティエ・カプソンという話題の奏者であったものの、残念ながら、その演奏を楽しむには至りませんでした。
ところで、当夜のオーケストラの構成は、チェロとヴィオラが入れ替わったちょっと変わった配置。その他の楽器は通常の配置なので、これは珍しい。低音を強調するためかと思いましたが。そういう印象はなかったので、いまいち意図がわかりません。しかもこの配置は、最初だけかと思いきや、すべての曲に共通で、最後のベートーヴェンも同じです。そのベートーヴェンですが、よくも悪くもシャルル・デュトア、つまり極めてドラマチックで一気呵成に仕上げる感じ。途中で、この勢いなら、きっと楽章の切れ目は置かないなと思ったら、やはり最後まで一気に盛り上がりました。ラヴェルもそうですが、この人、どんな音楽でもツボを心得ていて、それにふさわしい演出をするといえば良いでしょうか。ただ、かつて感じた演出過剰という印象はなく、もっと自然な姿、つまり曲本来の持つ魅力が素直に表現されるようになったと思います。一例をあげると、金管、木管の表現力はデュトアならではですが、以前はそれがいかにも律儀なN響にもっと自由にやれ、というメッセージに聞こえたものが、ごく自然な流れとして聞こえるようになったという感じです。こういった努力の積み上げが音楽としての完成度の高さにつながっているのではないでしょうか。
最後にオーディオマニアとしての感想ですが、何故かヴァイオリンの音がバランスを欠いた感じが気になりました。チェロの配置とは関係なく、席が左のブロックで、ヴァイオリンが目の前にいるためと思いますが、そうであれば、先月までの演奏会も同じように感じたはずです。ヴァイオリンの音が刺激的にならないというのは、オーディオのバランス上、最も重要なバロメータの一つですが、常時ではないにせよ、今まで感じなかっただけにちょっと気になりました。(2013年12月)
2014年1月 定期演奏会
2014年の最初の定期公演は、ファビオ・ルイージの指揮にルドルフ・ブッフビンダーのピアノという、まさに新年のイベントにふさわしい豪華メンバーです。曲目はモーツアルトのピアノ協奏曲 第20番とブルックナーの交響曲 第9番。モーツアルトのピアノ協奏曲はありそうで、実はあまり定期演奏会には登場しなかったように思います。ブッフビンダーはベートーヴェンのピアノソナタ全集などですでに高い評価を得ている、いわゆる巨匠の一人ですが、個人的にはあまり馴染みがなく、CDも持っていません。さて、そのブッフビンダーのピアノですが、まず音がきれいで、粒がそろっていて、いわゆる真珠を転がすようなという表現がぴったりとの音です。近頃はこういう演奏をする人はあまりいなくて、そういう意味ではルドルフ・ゼルキンとかルービンシュタインとか、一昔前の世代を思わせるところがあります。特に指の動きなどを見ていると、自ずとああいう音楽になるだろうなと思われ、まさに自然体といった感じです。対するルイージ、こちらは見た目の通り、若い音楽をやる人で、切れの良いモーツアルト。軽快かつ爽やかなオケに、まろやかなピアノという組み合わせなのですが、これがとても良くて、極上のモーツアルトでした。このように書くと、穏やかなイメージを受けますが、決してサロン的なモーツアルトではなく、この曲の持つダイナミックさも十分表現されていました。この曲は短調ということで、比較的内省的な印象だったのですが、ベートーヴェンのピアノ協奏曲を思わせるようなきらびやかなピアニズムがあり、ピアニストとしての技量を発揮できる曲作りを狙ったところもあると、実演に接して初めて感じた次第です。
後半のブルックナーは圧巻でした。ルイージという指揮者、当夜のパンフレットによればイタリア出身で、オペラで活躍しているとのこと。この指揮者、とても情熱的な指揮をする人で、そういう意味ではイタリア人らしいのですが、風貌から受ける印象はまるで違い、ちょっと線の細い学者肌の感じです。もう亡くなったシノーポリと似ているかもしれません。そういえば、彼もイタリア出身でした。当夜はとても寒い日でしたが、サントリー・ホールはまさに熱気にあふれた一夜となりました。まず、1楽章のトレモロの開始のすぐ後にくるクレッシェンドで、地響きのような金管群と、粘る弦楽器群にいきなり打ちのめされました。私の知るかぎり、N響からあれだけ分厚い音が聞こえたことはありません。それにしても、最後まで体が持たないのではと余計な心配をするほど、音楽に対する集中度は度を超していて、あの態度に接したら、誰もいいかげんなことはできないでしょう。客演とはいえ、あそこまでオーケストラと真剣に向き合う指揮者はそういないし、そういう意味では常任指揮者になってもらえば、N響がさらにレベルアップすることは間違なしです。まあ、楽団は迷惑かもしれませんが。ブルックナーの第9番は1時間近い曲ですが、1楽章と2楽章はあっと言う間に終わり、3楽章のアダージョになって、ようやくこの曲の長さを実感した次第です。
この時期は昨年の「最も心に残ったコンサート」の投票時期ですが、今年のコンサートはまだ始まったばかりで時期尚早とはいえ、間違いなくノミネートされるでしょう。(2014年1月)
2014年2月 定期演奏会
先月、モーツアルトのピアノ協奏曲はN響の定期公演にあまり登場しないと書いたら、今月の20番に続いて、今月は22番と、たまたま連続演奏会となりました。今月はあのネヴィル・マリナーの指揮。前回聞いたのは2010年9月ですが、この時すでに86歳。定期公演には行けなかったのですが、これが最後かもしれないとの思いで、別の日のプログラムを追加で購入して聞いたほどです。従って、今年は90歳になるわけですが、足腰は確かで、他の同年代、あるいはより若い指揮者と比べてもいたって元気です。この調子なら、来年も登場するかもしれません。
演奏曲はオール・モーツアルトでしたが、聞かなくても想像できる通り、穏やかで整った演奏。このスタイルは生涯変わらないでしょう。従って、サントリーホールでは物足りない、というよりもそぐわないと言うべきで、もっと小さな会場がふさわしい音楽でした。プログラムは前半は、交響曲
第35番ハフナーとピアノ協奏曲 第22番、休憩を挟んで、交響曲 第39番。ピアノはティル・フェルナーというオーストリア出身の人で、若く見えたのですが、1972年生まれなので、もう中堅といった存在です。モーツアルトの音楽ということを意図したのでしょうが、とても柔らかいタッチで、こちらもマリナー同様、奇のてらったところのない、正攻法のモーツアルトでした。
こういうモーツアルトがN響のような現代のフル・オーケストラで取り上げられることが少なくなったのは、やはり単調になり勝ちだからと思われます。マリナーの演奏はハイドンもそうですが、軽快で颯爽としたものですが、現代オーケストラでは、たとえばコンサートのページでも取り上げた、ヘレヴェッヘとシャンゼリゼ管弦楽団のような緊張感のある、研ぎ澄まされた感じにはなりません。とはいえ、後半の39番はさすがという出来で、決して心地良い響きだけではなく、フルオーケストラならではのダイナミックで、密度の高い音楽を聞くことができました。
ただ当夜は、たまたま週末に襲われた大雪の後始末やら、家族の世話やらで連日追われていたこともあり、すっかり眠気に襲われてしまいました。定期公演も、書きたい、あるいは記録しておきたいと思う時と、今回のように、特段書き留めておきたいと思うことがないこともままあります。読んでくださる方には申し訳ないのですが、そんなことも含めて、個人の記録として残しておくことにしています。(2014年2月)
2014年4月 定期演奏会
先月は定期演奏会はお休みで、その間にオスロフィルを聞いてきました。そんなわけで二ヶ月ぶりの定期公演だったのですが、2月よりもっとひどい状態で、ひたすら眠気と戦うだけで終わってしまいました。もちろんこれは体調のせいで、演奏が退屈だったわけではありません。
当夜はメーネ・ヤルビの指揮で、リヒャルト・シュトラウス特集。それもマイナーな曲ばかりで、祝典前奏曲、紀元2600年祝典曲、そしてバレエ音楽「ヨセフの伝説」という組み合わせ。いずれも初めて聞く曲です。冒頭の祝典前奏曲からしていきなりオルガンが鳴り響くような迫力満点の曲で、あっけにとられてしまいました。こうなると曲を聞くというよりも、大音響に酔うというのがふさわしい気がします。まあそういうたぐいの音楽ということでしょう。次の「紀元2600年」というのは、何と日本の紀元(神武天皇が即位した年)に基づく年号で、日本政府が「皇紀2600年」(西暦1940年)にナチスに委託した曲だそうです。リヒャルト・シュトラウスが日本からの依頼に応えたというのは驚きですが、そういういわくつきの曲です。祝典前奏曲よりは楽曲という感じで、物語を感じさせるところもあり、交響詩といった趣の曲です。
最後の「ヨセフの伝説」は曲の規模も大いのですが、これまた大編成のオーケストラで、管楽器の数が桁はずれて多いのに加えて、チェレスタ、4台のハープ、ピアノにオルガンと、舞台からあふれんばかりの楽器群です。ただしこちらはただ大音響というのではなく、バレエの物語に即した音楽なので、独奏楽器のかけあいの部分など、聞きどころの多い曲です。ただ、冒頭述べたように、眠気をがまんするだけで(自宅と違い、眠り込むわけにいかないので)、とても楽しむというわけにはいきませんでした。さすがにこういった状況が続くと、もうN響の定期演奏会もそろそろ潮時と思わざるを得なくなります。この時期はちょうど来年度の更新のタイミングなので、キャンセルしようと思っていますが、5月の公演を聞いてから判断することにしました。やはり演奏会は期待感を持っていくべきところで、参加することが苦痛になるようでは意味がありません。
今後は来日オケを中心に、行きたくなった時に行くことにしたいところですが、問題はチケットの確保です。良い席を確保するには半年前の発売時に確保する必要があり、そうなると、あらかじめ日程が決まっている定期演奏会とあまり違わなくなってしまいます。
今月のフィルハーモニー(定期公演会で配布されるプログラム)に、「最も心に残ったN響コンサート2013」が発表されていました。要するに、定期演奏会の人気投票ですが、第1位から第3位までをブロムシュテットが独占しました。ちなみにサントリーホールのBプロは第3位です。こんなに偏るのも珍しいのですが、それだけ人気があるということでしょう。個人的に興味があったのは第5位にランクされたトゥガン・ソヒエフで、これは11月のBプロで、私もチャイコフスキーの交響曲第5番の演奏に強い印象を受けたのですが(11月の定期演奏会を参照ください)、数名の方が同じようなコメントをされているのが興味深いところです。(2014年4月)
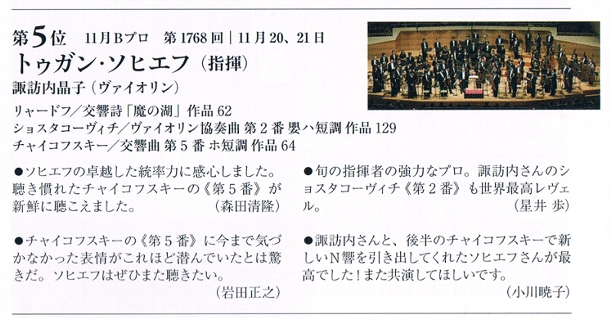
2014年5月 定期演奏会
今月の定期演奏会で配布されるプログラムを見て初めて知ったのですが、Aプロはゲルネを迎えてのワーグナーの楽劇集で、もうちょっと早くチェックしておけばと、後悔しました。これもN響の定期公演がマンネリになっている証拠ですが、ゲルネをフル・オーケストラのバックで聞けるのですから、ちょっとない機会で、惜しいことをしました。
さて、当夜のBプロは、広上純一の指揮で、シューベルトの交響曲 第5番と、マーラーの第4番。広上純一は二度目だと思いますが、その音楽は流れるように軽快で楽しく、まるで映画音楽をを聞いているかのよう。何の違和感もなく、すっと溶け込んでくる親しみ易さがあります。特にシューベルトはもともと穏やかな曲なので、そのスタイルと相まって、眠くなってしまいます。現に周囲の大勢の人が眠っていました。この曲はもちろん管楽器もありますが、それらの音が弦に溶け込み、まるで弦楽オーケストラを聞いているような印象です。これは管楽器の構成がフルート1、オーボエ2、ファゴット2、ホルン2と、小編成なるが故ですが、それ以上に、それがこの指揮者のバランス感覚なのではないかと思います。そもそも、シューベルトの交響曲といえば、真っ先にアーノンクールの、穏やかさを突き飛ばしたような、厳しい演奏を思い浮かべますが、広上の演奏は明るく、楽しいシューベルト。多分これが作曲者が描いた本来の世界のような気がします。だからこそ、その後の未完成のような暗さや、グレートの表現の奥深さが存在するのではないでしょうか。
休憩後のマーラーは、さすがに編成が大きいので、フル・オーケストラの響きですが、ここでもシューベルトと同様、音楽の流れを何よりも大切にした演奏。もちろん、細かく聴いていれば、それぞれのパートは表情豊かで、決して平板ではないのですが、それを感じさせない流麗さがあります。この第4番は歌曲である第4楽章が先にできて、後から他の部分を作曲したという、ちょっと変わった手順で作られた曲だそうです。ただ、聞いてみると、そういった不自然さは感じられず、むしろ第4楽章が通常の交響曲と違って聞こえます。マーラーの交響曲らしく美しい旋律に満ちた曲ですが、ここではシューベルトのような明るさは感じられず、第3楽章など、天国的な安らぎというよりも、悲劇的な印象を与えます。そういう「物語性」を感じさせるところが、まさに映画音楽になってしまう所以ですが、もともとこの曲が「天上の生活」というテーマを持っていることも、その要因でしょう。
ともあれ、あれこれ想像力を与えられるような演奏であるということは、それだけ自分の音楽になっているという証拠でもあり、それこそが、この人ならではの職人気質ということでしょう。その指揮スタイルも独特で、まさに音楽の演出家そのもの。生真面目な指揮者の多い日本では貴重な存在です。
第4楽章の独唱はローザ・フェラオ。新進のソプラノだそうですが、声量がもっとあっても、と言う気はしましたが、基調は明るくかつ素直で、全体の音楽の流れによく合っていました。(2014年6月)
2014年6月 定期演奏会
今年度のシーズンもこの6月で終了となります。今年度は全部の定期公演に参加できたという、かつてない年だったのですが、残念ながら堪能したという印象はなく、2月以降は印象が希薄な状態が続きました。その点では今月も例外ではなかったのですが、中野翔太というピアニストを知ったのが収穫でした。
指揮は毎年6月に登場するアシュケナージ。曲目はシベリウスの組曲「恋人」、グリーグのピアノ協奏曲 イ短調、休憩を挟んでエルガーの交響曲 第一番。シベリウスの恋人は弦楽合奏曲なのですが、恋人という表題から想像させられる甘美なイメージではなく、どちらかというと暗い、どこか抑圧された印象を受ける曲です。グリーグのピアノ協奏曲は演奏会でよく取り上げられる曲ですが、何と言っても華やかな聞き映えのする曲。多くのピアノ協奏曲がピアニストを引き立たせるために書かれたという感じなのですが、この曲はその最たるものの一つ。CDで聞いていそんな感じなのですが、生で指というより腕の動きを見ていると、相当な技巧を必要とする曲というのが良くわかります。ピアニストは中野翔太という、1984年生まれですから、今年ちょうど30歳の若い人。この人についてはまったく予備知識がなかったのですが、この難曲をやすやすと弾きこなす技術にまずは圧倒されます。ところが本人は失礼ながらおよそそういうかっこよさとは縁のない風貌で、むしろ頼りない感じを与えます。それがバリバリと弾きこなすので、外見とのギャップにこれまた興味をそそられます。高度な技巧に加えて、あれだけの和音を透明感を持って響かせるのはこのピアニストの美意識でしょう。当夜のプログラムによれば、有名なコンクールには出ていないのか、入賞しなかったのかわかりませんが、そういう華やかな経歴はありません。それが、この人が知られていない理由と思われますが、そういうことには関心がないというのが、この人のスタイルではないかと推察した次第です。ともあれ、久々にピアニズムの醍醐味を満喫した演奏でした。
休憩後のエルガーの交響曲 第一番は初めて聞く曲で、演奏会でも取り上げる機会が少ない曲と思います。イギリスでは国民的人気のある曲のようですが、ちょっとブラームスの第一番を思い出させるような、肩の力が入った感じの曲です。この曲から例によって睡魔に襲われたため、コメントできるほどの印象はないのですが、何度か聞けばはまるような、ちょっとしつこさの感じられる曲です。当夜のアシュケナージは今までとはだいぶ違う印象を受けました。つまり、誰が聞いても満たされる円満な演奏というより、もっと自己主張の感じられる演奏。たとえば、ややしつこいと感じられるフレーズの繰り返しの部分など、まるで深呼吸を繰り返すような高揚感があり、心情をストレートに表出した印象でした。アシュケナージが祖国を離れ、第二の故郷となったイギリスの作曲家の作品、という思い入れもあるのかもしれません。
4月のレポートで、来年度の更新はしないと書きましたが、その気持ちは5月、6月の公演でも変わりません。一方で、メンバーとしてのメリットを手放すのも惜しいので、シーズン会員として、パーヴォ・ヤルビが登場する冬シーズンのみ購入することにしました。ただ、シーズン会員の場合、会場はNHKホールなので、オーディオマニアとしてはまた不満を抱えることになるかもしれません。(2014年6月)