2024-2025 N響定期公演
2024年9月14日 第2016回 定期公演
今年は、サントリーホールの公演が1万円に値上がりしたことで、シニア割引のある都響に鞍替えすることも考えました。しかし、ファビオ・ルイージの主席指揮者の契約が延長になったことや、昨年は来日がかなわなかったブロムシュテットが今年は来るかもしれない、ということなどを考慮し、少し安価なNHKホールでのAプログラムに変更することにしました。7月の会員優先の席替え時期に旅行に行っていたこともあり、あまり期待していなかったのですが、ステージに向かって右ブロックの17列目、かつ通路側という比較的良い席が取れたのは幸いでした。予約したのは席替えが始まって3日目でしたが、まさか通路側の席が空いているのは思いませんでした。今期はシーズン開始直前になっても、サントリー・ホールを含めて会員を募集していましたので、さすがのN響人気も、この値上げでは年金生活者には負担ということなのでしょう。今年は郵便料金も上がるので年賀状の見直しなど、生活防衛のために固定費削減が必要なご時世になってきました。
2024年シリーズの最初はファビオ・ルイージによる、ブルックナーの交響曲 第8番。初稿ということで、1時間半を超えるため、休憩なしでこの1曲だけですが、聞き応えがありました。第1楽章はあまり気にならなかったのですが、久々のNHKホールで、だんだんと気になるところが出てきました。まず、空調の音。こういう会場は広いこともあって、通常はほとんど気にならないのですが、9月とはいえ、真夏並みの暑い日だったことも影響しているのかもしれません。これについては以前にも書いたような気がしますが、ステージが反射板で覆われているのと側壁面からの反射が少ないので、ステージ付近で音がこもりがちです。オーケストラの音が広がるのではなく、ステージから音の塊が聞こえてくるような感じです。そのため金管はよく響くのですが、前方にある弦がよく聞こえません。特に、オーケストラの弦を支えるコントラバスが貧弱で、金管楽器とのバランスが取れません。ブルックナーの曲はこれでもかというくらい、金管が張り出しますので、余計そのように感じるようです。更に、8月に聞いたサイトウ・キネン・オーケストラの弦が分厚い響きでしたので、その違いが増幅されたきらいはあります。サントリー・ホールではそういう不満は感じなかったので、やはりホールによる違いとみて間違いないでしょう。

演奏はファビオ・ルイージらしい、歌うようなフレーズと爆発的なダイナミズムが緻密に組み合わされた演奏でした。充実感があるので、ブルックナーによくある、一瞬音楽が止まったかのようなブレークも自然につながります。第2楽章は、ともすれば執拗と感じるリズムに支配された音楽ですが、反復に至るまでの過程が丁寧に描かれるので、そのリズムが必然のように感じられます。第3楽章は音楽自体が荘厳そのものですが、こういう息の長い音楽にも適合するルイージの音楽性は、イタリア人らしからぬところです。もっとも、ブロムシュテットもアメリカ育ちですが、ブルックナーを得意にしていますし、このグローバルな時代に、国籍はもはや関係ないのでしょう。かつてCDで良く聞いたブルックナーですが、最近はほとんど聞きません。興味がなくなったわけではなく、ああいう悠然とした流れについて行くのが少し難しくなっているように感じます。
先月、サイトウ・キネン・オーケストラの熱気溢れる演奏を聞いたばかりということもあり、緻密ではあるものの、整然としたN響の演奏に物足りなさを感じたのも事実。金管ではホルンの首席奏者がいつもと違っていて、あれ?という一幕もあり、NHKホールの音が気になったりして、毎度のこととはいえ、あまり楽しめなかったのは残念です。(2024年9月)
2024年10月19日 第2020回 定期公演
去年の10月はブロムシュテットが感染症で来日が不可となりましたが、今年は10月に入ってN響からのダイレクトメールで、予定通り来日し、リハーサルを開始したとの連絡がありました。何しろ今年で97歳という驚異的な年齢ですから、指揮以前に来日することも困難なはずで、N響自身もそんなメールを出すほど気をもんでいたのでしょう。ステージまで歩くのも大変そうでしたが、今月予定されていたA,B,Cの全てのプログラムに登場するというのは驚きです。ともあれ、ファンにとっては、はるばる日本まで来てくれたというだけでも感激ですが、当夜の演奏から聞こえてきた祈りの精神と、哀しくも美しさに満ちた音楽は感動的でした。
当夜のAプログラムはオネゲルの交響曲 第3番「典礼風」と、休憩を挟んでブラームスの交響曲 第4番。最初のオネゲルですが、第1楽章は不穏な雰囲気の複雑な音楽であるにもかかわらず、よく統制された響きが印象的でした。そのため、あまり馴染みのない曲にもかかわらず、曲想がよく理解でき、初めてこの曲の良さを知ったように思います。第2楽章は美しい旋律で、透明感のある演奏から聞こえてくるのは祈りの精神。もともとブロムシュテットはヒューマンな音楽をやる人ですが、オネゲルで表現したかったのは、この祈りだったのだと理解した次第。第3楽章の終盤でその思いが確信になったのは、穏やかで美しい響きはもちろんのこと、曲が終わっても、しばらくその祈りが続いたことです。あたかもミサ曲でも聴いたかのようで、聴衆もそれに応えていたのが印象的でした。

後半のブラームスの交響曲第4番、こんなに哀しい曲だったかしら、というのが演奏中に何度も思ったこと。8月に同じ第4番を、サイトウ・キネン・オーケストラのガッツに溢れる演奏で聴いたから、余計にその違いを感じたのかもしれません。ただ誤解のないように書いておきたいのは、ブロムシュテットの年齢や姿勢ゆえにそう感じられたのではないということです。もちろん座ったままの指揮ですので、身振りも制限されますが、その音楽はむしろ若々しく、ダイナミックさも十分で、弱弱しさなどまったく感じられません。それにもかかわらず第1楽章からして寂しさが感じられるのは何故か。その寂寥感ともいう気分が、より強く現れるのが第2楽章ですが、ここでは寂しさより美しさをより強く感じました。意外なのは、第2楽章までに比べて、快活で明るさのある第3楽章において哀しさを感じたこと。それも後半の力強い響きの部分でその気持ちが高まっていくのは、まったく想定外のことでした。その感情が頂点に達するのが第4楽章でしたが、静かな部分ではなく、トゥッティのような力強い響きの中で哀しみを感じたのは初めてのこと。それはブロムシュテットの指揮が恐らくこれが最後、という感傷がもたらしたのは言うまでもありません。それは純粋に音楽を鑑賞する上では余計なことかもしれません。しかし、そもそも音楽はその時の気分によって大きく変わるのはこれまた自然なこと。次に涙がこぼれるほど感動するのは、コンサートに来るのが困難になった時かもしれません。 添付は10月24日の朝日の夕刊の片山氏の評です。メッセージ性の強い演奏だったというところは共通認識のようです。(2024年10月)
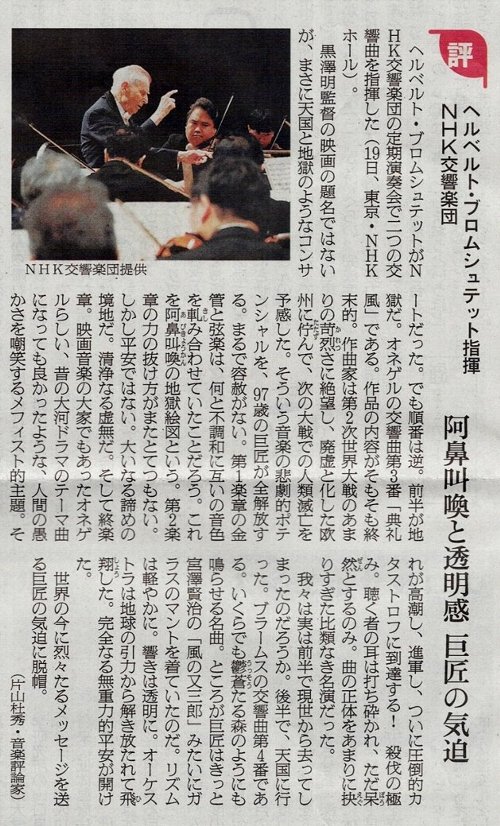
2024年11月9日 第2022回 定期公演
今月はバーミンガム市交響楽団の音楽監督に就任した山田和樹の登場です。バーミンガム市響といえば、2016年の6月の凱旋公演に行っていますが、8年も前ですから、さすがに記憶はあいまいです。実はこの公演の翌日からほぼ2週間の海外旅行に行っていて、4週間後になってこのレポートを書いていますので、すでに記憶の彼方。そうなることは予想されたので、当夜にメモだけは残してあり、ようやくそれらを文章にまとめているという次第です。
当夜のプログラムは山田の得意と云われているフランスもので、ルーセルのバレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」組曲、バルトークのピアノ協奏曲 第3番、休憩を挟んで、ラヴェルの優雅で感傷的なワルツと、ドビュッシーの管弦楽のための映像からイベリア。フランスものは時々聞きますが、これまでで最も楽しんだ演奏でした。更に、そういう「楽しんで聞く」ということが何よりも大切なこと、というのを教えてもらった公演でもあります。フランスものと言えば、特にラヴェルなど、揺らぎのような、フワァっとくるフレーズが多く、リズムを取りにくいというか、入り込み難い傾向がありますが、今回はすーと入っていけたのも従来と違う点。ただ、それについては、聞き手が馴染んできたということも影響していそうです。
2曲目のバルトークのピアノ協奏曲 第3番は従来バルトークに抱いていた前衛的なイメージと違い、第2楽章など実に美しい曲です。ピアノはスイス出身のフランチェスコ・ピエモンテージ。初めて聞くピアニストですが、ピアノの音がよく響いて、NHKホールの音ってこんなに良い音だったかしらという感じでした。乾いた音という印象は変わりませんが、ピアノの音に厚みが感じられ、不満は感じません。ダイナミックでしかもきれいな音を出すピアニストということもプラスに働いたのは間違いないでしょう。そのダイナミックスが見事に発揮されたのはアンコール曲のバッハ「目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ」
BWV645。そういう特質が聞き分けられるのですから、NHKホールも満更ではありません。(座席の位置もありそうです)
ラヴェルとドビュッシーの管弦楽曲ではオーボエが印象的でした。どちらの曲も金管の役割が大きいので、もう少し自己主張しても良いのではないかと思いました。山田もそういう思いがあったのでしょうか、クラリネットに対して、もっともっと、という指示を出していました。時々、ブラス・アンサンブルかと思うようなシーンもあって、それも冒頭述べた「聞く楽しみ」ということにつながります。山田和樹の指揮には、前述の音楽を楽しむというメッセージに加えて、構成の良さがあげられます。全体を通じて充実感があり、最後に「祭りの朝」で盛り上がりを持ってくるなど、さすが音楽監督といったところです。海外で人気があるのは、そういった演出力にも秘密がありそうです。(2024年12月)
2024年11月30日 第2025回 定期公演
日付は11月30日ですが、これは12月の定期公演となります。12月には恒例の第9の演奏会があるため、定期公演は早めに設定されたため、11月に2回(ラトル/BRSOも含めると3回)もNHKホールに行くことになりました。加えて、11月の定期公演で書いたように、翌日から長期旅行に行ったため、2か月分を同時に書くという、変則的な事態となりました。12月公演の指揮はファビオ・ルイージです。今年は第9も演奏するので、一か月間も日本に滞在することになります。主席指揮者とはいえ、日本びいきでないと務まらない役割と、改めて思った次第です。
当夜のプログラムはワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」、R.シュトラウスの歌曲から5曲、休憩を挟んでシェーンベルクの「ペアリスとメリザンド」という意欲的なもの。過密スケジュールのなか、こういう曲を持って来るのは、生真面目なルイージの性格を表しているように思います。2日前にラトル/バイエルン放送管弦楽団の音に圧倒されたばかりで、良くも悪くも比較せざるを得ない状況でした。BRSOに比べると、淡白で薄い音を予想していましたが、ゴージャスとは云わずとも、貧相な音ではなく、安心しました。云わば、たまには高級レストランで特上のコース料理を食べたいものの、日頃は淡白な家庭料理の方が好ましいという感触です。最初がワーグナーだったのですが、独特のうねるような表現も遜色なく、毎年東京・春でワーグナーを演奏している経験も生きているように感じました。R.シュトラウスの歌曲はこの夜のハイライト。歌手はドイツ出身のクリスティアーネ・カルク。R.シュトラウスらしい、愛らしい曲が多かったこともあり、伸びがあり、余裕のある歌声はとても素敵。いくつか知っている曲もありましたが、最後の「明日の朝」は静けさに満ちた爽やかな曲で、ここに至るまでの愛の歌が、幸福感として昇華されるような感じがしました。年間を通じて歌曲がプログラムに組み込まれることは少なく、こういう演奏に接すると、もう少しあっても良いのではないかと思います。
休憩を挟んで最後のシェーンベルクの「ペアリスとメリサンド」は初期の作品で、シェーンベルクの曲では馴染みやすい曲。と思っていたのですが、46分という長い曲にもかかわらず、切れ目がないため、曲想の理解がないと、ついて行くのが困難です。CDはあってもほとんど聞いたことがなく、この長大な曲を予備知識なく聞くのは無理があると感じた次第。そんなわけで、途中から集中力が切れてしまい、ただ音を追っている状態になってしまったのは残念です。(2024年12月)
2025年1月18日 第2028回 定期公演
毎年1月はトゥガン・ソヒエフの登場で、今年もA, B, C3つのプログラムを全て担当します。Aプログラムはショスタコーヴィッチの交響曲 第7番で、ロシア出身のソヒエフですが、この指揮者のショスタコーヴィッチを聞くのは初めてです。もともと、第7番はやたらと鼓舞するような節が続く音楽で、あまり良い印象はありません。その点では今回も例外ではなく、ここで改めて記録しておくこともないのですが、全体を通して聞いてみると、必ずしも戦闘シーンを思い起こさせるだけの曲ではないということを知らされたものの、より深く聞いてみたいと思う気にはなりませんでした。

第1楽章は勇ましい開始の後にしばらく穏やかなひと時が訪れますが、その後、ボレロをパクったのではないかと思われる、小太鼓が刻むリズムに乗って、これでもかと繰り返される闘争心を鼓舞するような音楽。この部分以外はほとんど記憶にない曲なので、ソヒエフの指揮を云々することはできませんが、11月のブロムシュテットのシューベルトで聞かれた深々とした味わいではなく、もっと攻めの姿勢、といっても力ずくというのではなく、ガツンとくる引き締まった響きを聞かせます。第2楽章は第1楽章に比べると、より人間的というか、厭戦的なムードも感じられるものの、途中から戦闘モードになり、やはり来たなという感じ。第3楽章で、ようやく音楽を聞いているという雰囲気になるものの、決して安らぎではなく、闘志を押し殺すような暗いアダージョ。と思ったら、再び鼓舞するような楽曲が始まり、やはりアダージョでは済まされないということなのでしょうか。第4楽章では、第1楽章のように突き進むのではなく、音楽的な充実度が感じられましたが、最後の勝利のファンファーレは、決してお祝いムードのようには聞こえせん。ソヒエフだからと云うべきかもしれませんが、やはりこの曲を取り巻く時代背景は消し去ることができないのでしょう。そういう歴史的視点よりも、音楽そのものに着目した演奏と聞きましたが、フィナーレに向かっての高揚感が素直に楽しめなかったのは、やはりこの曲の宿命のように感じました。(2025年1月)